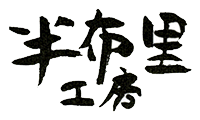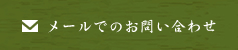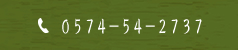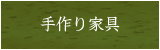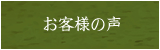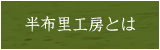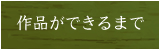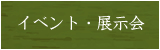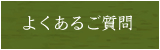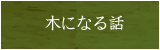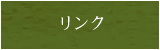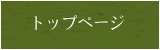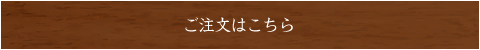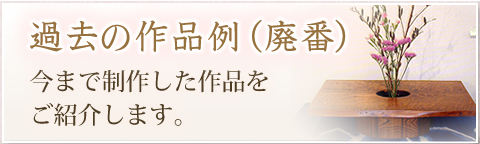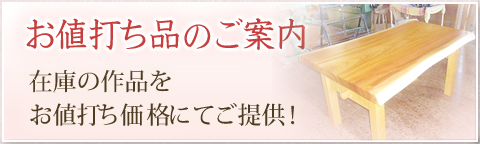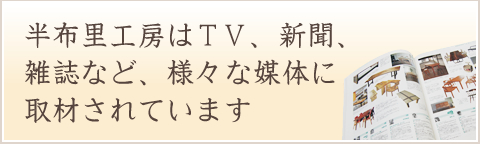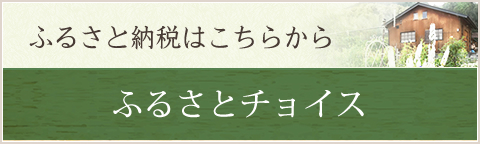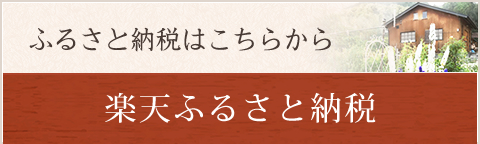蝶番(ヒンジ)
 箱物家具などの扉を取り付けるのにヒンジ(蝶番)を使います。その蝶番には様々なものがあります。ごく一例ですが。こんなものがあります。
箱物家具などの扉を取り付けるのにヒンジ(蝶番)を使います。その蝶番には様々なものがあります。ごく一例ですが。こんなものがあります。これ以外にも本当に多くのものがあります。Pヒンジというようなものもあったり、ガラス扉専用の蝶番があったり、またスライド蝶番などはよく使われます。

 しかし、私は昔からあるごく普通の「蝶番」が好きです。蝶番が美しく決まった姿は箱物家具の装飾の一つになります。
しかし、私は昔からあるごく普通の「蝶番」が好きです。蝶番が美しく決まった姿は箱物家具の装飾の一つになります。
 蝶番の選択にはいろんな要素が絡みます。意匠性、機能性など…画像の右側は私がよく使う蝶番で、強度もあり、少し重い扉でももつように作られています。見た目も美しいものです。
蝶番の選択にはいろんな要素が絡みます。意匠性、機能性など…画像の右側は私がよく使う蝶番で、強度もあり、少し重い扉でももつように作られています。見た目も美しいものです。ところが、この蝶番の取り付けは(同業者ならよくわかると思いますが)結構難しいものです。「たかが蝶番、されど蝶番」なのです。

 蝶番をつけて扉を本体に取り付ける作業は、一発で決まるものではありません。つけてみたら、上下が大きすぎたとか、幅が少し広すぎたとか、枠に対して少し歪んでいるとか…様々な状況が起きます。
蝶番をつけて扉を本体に取り付ける作業は、一発で決まるものではありません。つけてみたら、上下が大きすぎたとか、幅が少し広すぎたとか、枠に対して少し歪んでいるとか…様々な状況が起きます。つけてみては外して少し削り…という作業を何回か繰り返すことになります。そうすると、取り付けるネジ穴も何回かやっている間に緩んでくることになりますから、それでは困ります。そこで、この作業の時は本番で使うネジよりも少し小さいネジを使って行います。しかも最低限の数だけを使います。
 本体の方立や框材は角に糸面が取ってあります。そうすると扉自体はその分(約1mmぐらい)内側に納まるのが美しい納まりということになります。このあたりも気を付けて取り付けます。
本体の方立や框材は角に糸面が取ってあります。そうすると扉自体はその分(約1mmぐらい)内側に納まるのが美しい納まりということになります。このあたりも気を付けて取り付けます。
 そうなるようにするためにあらかじめ蝶番を扉に取り付ける段階で少しだけ(0.5mmぐらい)蝶番が飛び出るぐらいに段欠きの加工をしておきます。(※もちろん後で削って修正するというやり方でもいいです。)
そうなるようにするためにあらかじめ蝶番を扉に取り付ける段階で少しだけ(0.5mmぐらい)蝶番が飛び出るぐらいに段欠きの加工をしておきます。(※もちろん後で削って修正するというやり方でもいいです。)また、画像でもわかると思いますが、扉の縦框は少しだけ内側に傾斜をするように削っておきます。