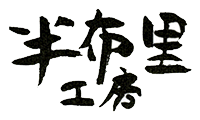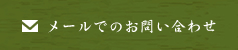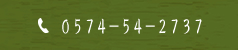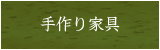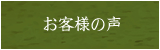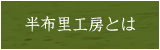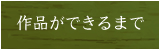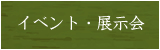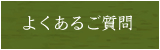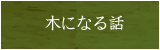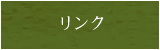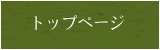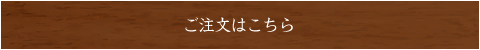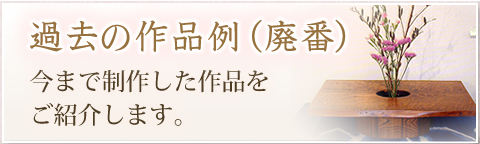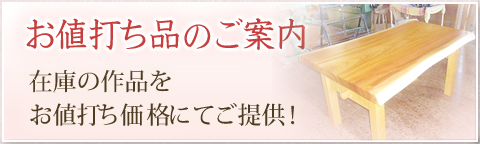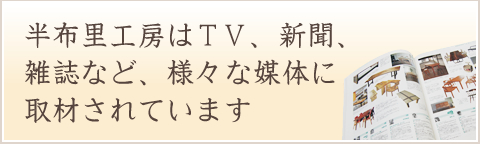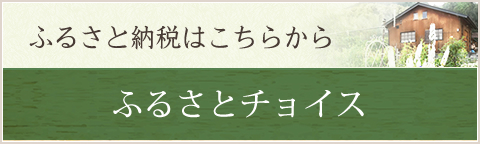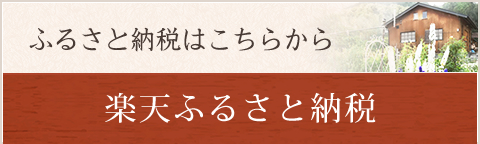蟻組み、手仕事
 定番の学習机3点セット(学習机、デスクサイドチェスト、KOSI-KAKE)が、ようやく完成しました。…ところでこの学習机ですが、引き出しの蟻組みが重要なデザインポイントになっています。
定番の学習机3点セット(学習机、デスクサイドチェスト、KOSI-KAKE)が、ようやく完成しました。…ところでこの学習机ですが、引き出しの蟻組みが重要なデザインポイントになっています。

 蟻組み自体はこれまで様々なものの制作に使用していて、どれだけ加工したか数えられないぐらいです。
蟻組み自体はこれまで様々なものの制作に使用していて、どれだけ加工したか数えられないぐらいです。この蟻組みについてはいろいろな方がいろいろなやり方でやってみえると思います。機械を使って精緻に加工される方もみえると思います。(某有名木工家もそうです。)あるいは手加工だけで、私なんか及ばないほど見事に加工される方もみえるでしょう。

 先日、私も所属していたある団体から連絡メールが来ました。(現在はこの団体には入っていません。)その内容は「留形隠し蟻組み接ぎを機械で加工する」というセミナーのお知らせでした。
先日、私も所属していたある団体から連絡メールが来ました。(現在はこの団体には入っていません。)その内容は「留形隠し蟻組み接ぎを機械で加工する」というセミナーのお知らせでした。私自身は「留形隠し蟻組み接ぎを機械だけで加工する」という発想はこれまで全くありませんでした。そこで「へえ機械でやれるんだ。まぁなんでもやろうと思ったらできるけどね…」と思いました。でも私はそれをやろうとは思いませんし、もちろんそのセミナーに参加してみたいとも思いませんでした。
 私は蟻組み(留形隠し蟻組み接ぎも)はあくまでも手加工で行いたいです。その理由の一つは、先人が残してきたこの美しくも優れた技を将来に受け継いでいくということです。大げさに言うと使命ということになりますが、私はそんな大げさな気持ちではなく、私もそれを受け継いでいく一人でありたいと思っているぐらいのことです。木工に限らず、昔から受け継がれている優れた技や美しい文化は残そうと努力しなければ駄目です。
私は蟻組み(留形隠し蟻組み接ぎも)はあくまでも手加工で行いたいです。その理由の一つは、先人が残してきたこの美しくも優れた技を将来に受け継いでいくということです。大げさに言うと使命ということになりますが、私はそんな大げさな気持ちではなく、私もそれを受け継いでいく一人でありたいと思っているぐらいのことです。木工に限らず、昔から受け継がれている優れた技や美しい文化は残そうと努力しなければ駄目です。

 理由の第2は、機械加工ではあまりにも大きな部材の加工は無理だからです。大きな部材を組み合わせるにはやはり(大工さんのように)手加工でなければ無理になってきます。
理由の第2は、機械加工ではあまりにも大きな部材の加工は無理だからです。大きな部材を組み合わせるにはやはり(大工さんのように)手加工でなければ無理になってきます。その時のためにも日ごろから修練を積んでおきたいということがあります。その時になって、機械加工だけでやってきた人が急に手加工でやったって出来るはずもありません。そんな甘く見てもらいたくはないです。(そんな機会はそれほど無いかもしれませんが…無かったら無かったで結構です。)
私は蟻組みを機械を使ってまでして加工する意味はあまり感じていません。手加工で出来ないならば出来ないで、あえて蟻組みを使わなくても、その他のデザインで勝負すればいいと思っています。どうしても蟻組みを使いたいならば、手加工でやりきるぐらいの気概で行って欲しいです。
話はそれますが、ある工房の方が椅子を作る時のこと、「私はいつも機械の加工精度を大事にしています。だから機械で切った後はすごくきれいなので鉋掛けなどする必要もないです。すぐにサンディングをして終わりです」というようなことを言っておられました。
たしかに鋸目も残らないほどきれいにカットできているかもしれません。(こまめに鋸刃を研磨して、鋸刃のブレが無いように機械をメンテしていればそうなるかも。)でも私は違和感を覚えます。この方は「結果」が大事と考えているのでしょう。でも私は結果以上に「過程」を大事にします。
私の日ごろの口癖は「"何を" 作るかじゃなくて "如何に" 作るかが大事。さらに言えば "誰が" 作るかが大事なんだ」です。そのためにも日々木工のことはもちろんあらゆる意味で精進し、「あの人に作ってもらいたい」と思われるようにならなければと思っています。「あのデザインがいいから買うわ」だけではなく「そういう人がそういう作り方をした家具を買いたいわ」と思ってもらえるようになりたいです。
何かあるとすぐに「治具、治具」と治具作りに腐心するのでなく(少々のことは手業で乗り越える!)、「デザイン、デザイン」と見た目だけを追求するのでなく(ちょっと語弊がありそうで怒られそうですが、ここでは敢えてそう言い方をします)見えない部分に力を注ぐ、本来の職人魂を忘れないようにしていきたいと思って日々取り組んでいます。もちろん、足りないこと、出来ないことばかりでどうしようもないですが……。