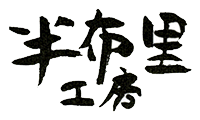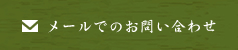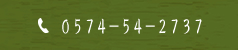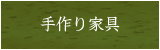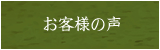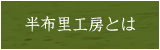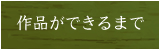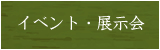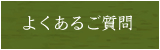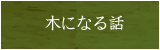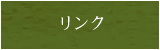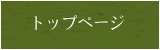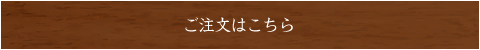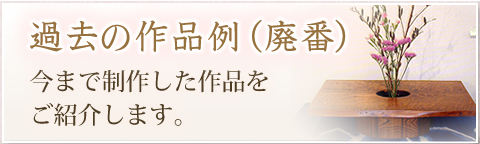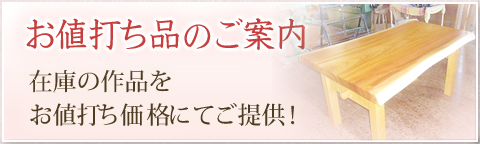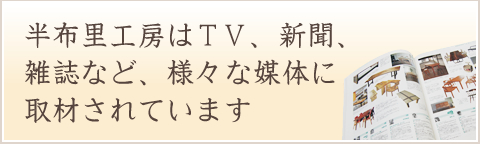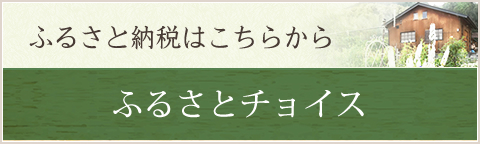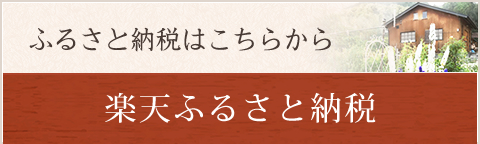吸い付き桟
「木が反る」と書いて「板」と読みます。無垢の木は多かれ少なかれ必ず反るものなのです。もちろん、完成してから反ったり狂ったりしないように、出来る限り乾燥した材を使うようにしています。それでもやはり反る事は避けられません。
そこで反りを最小限に食い止めるために「反り止め」という伝統的な工法を用います。これを「吸い付き桟」あるいは「蟻桟」と言います。板の裏側に蟻型の溝を彫って、それに合わせて同様に蟻型の桟を刻んだ雄木を叩き込んでいくというものです。
以下に、この工法の工程を簡単にご説明致します。
そこで反りを最小限に食い止めるために「反り止め」という伝統的な工法を用います。これを「吸い付き桟」あるいは「蟻桟」と言います。板の裏側に蟻型の溝を彫って、それに合わせて同様に蟻型の桟を刻んだ雄木を叩き込んでいくというものです。
以下に、この工法の工程を簡単にご説明致します。
 雄木の方に蟻型の桟を刻んでいきます。蟻型の刃物をルーターに装着し、治具を使って溝と同じように微妙に先が細くなるように刻んでいきます。
何度も溝に合わせながら、ちょうどいい締り具合になるように気を使って加工します。
雄木の方に蟻型の桟を刻んでいきます。蟻型の刃物をルーターに装着し、治具を使って溝と同じように微妙に先が細くなるように刻んでいきます。
何度も溝に合わせながら、ちょうどいい締り具合になるように気を使って加工します。