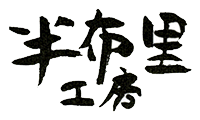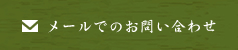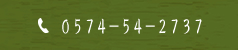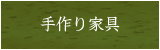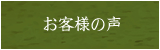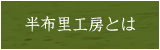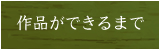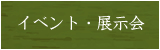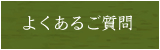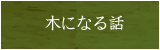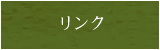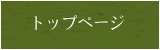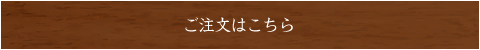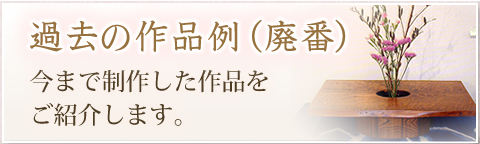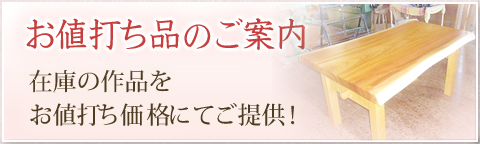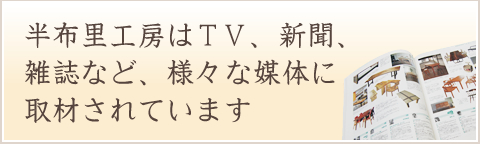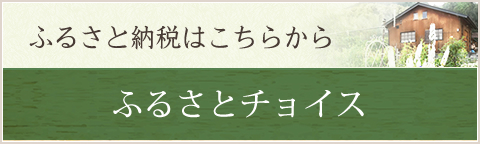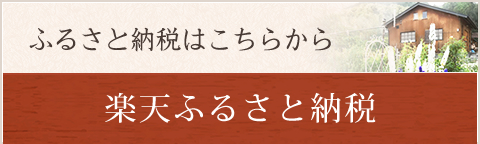- トップページ
- 里山便り2016
2016.12.26
「年末のあいさつ」
今年も無事1年が終わりました。(まだ納品を1件残していますが…。)
先日千葉県の方へ納品した折、すぐ近くに以前ご注文をいただいたお客様のお宅がありましたので、挨拶がてら立ち寄らせていただきました。(当然前もって連絡はしておきました。) ずいぶん久しぶりで懐かしく、楽しくお互いの近況など世間話をさせていただきました。
その時にお客様に「突然図々しくおしかけてすみません」と言いましたら、お客様が「いいえ、覚えて頂いていたのが嬉しいです」と言われました。私はこの言葉がうれしくも不思議な気がしました。なぜならば私は今まで何百人というお客様からお仕事をいただいていますが、ほとんどどの方のことも全て覚えています。(正確に言えば、メールだけのやり取りで直接配達していないお客様のことは当然そのお宅のことや容貌などを知る由もありませんが、そのような場合でもどのようなやり取りをしたかなどは覚えています。)
こんなこともありました。電話がかかってきて「以前桜のちょこっとスツールを買った○○市の者ですが…」と言いかけられたので、私が「ああ!○○さんですか?」と言いましたら「そうです!そうです!」と言って電話の向こうの声が弾んでいました。(この方はメールのやり取りだけでご注文をいただき、宅配便で送らせていただきました。)

 そんな具合に、時にメールを見直してみたり、過去の作品の画像を見ると、たちどころにその時のことが頭の中に蘇ってきます。
そんな具合に、時にメールを見直してみたり、過去の作品の画像を見ると、たちどころにその時のことが頭の中に蘇ってきます。
そのお客様のご容姿やその時のエピソードや、時にはそのお宅へお伺いした時のいろいろな風景が…私にとってはどの一つ一つにもそれぞれに思い出があるので、忘れることができないのであります。
先日千葉県の方へ納品した折、すぐ近くに以前ご注文をいただいたお客様のお宅がありましたので、挨拶がてら立ち寄らせていただきました。(当然前もって連絡はしておきました。) ずいぶん久しぶりで懐かしく、楽しくお互いの近況など世間話をさせていただきました。
その時にお客様に「突然図々しくおしかけてすみません」と言いましたら、お客様が「いいえ、覚えて頂いていたのが嬉しいです」と言われました。私はこの言葉がうれしくも不思議な気がしました。なぜならば私は今まで何百人というお客様からお仕事をいただいていますが、ほとんどどの方のことも全て覚えています。(正確に言えば、メールだけのやり取りで直接配達していないお客様のことは当然そのお宅のことや容貌などを知る由もありませんが、そのような場合でもどのようなやり取りをしたかなどは覚えています。)
こんなこともありました。電話がかかってきて「以前桜のちょこっとスツールを買った○○市の者ですが…」と言いかけられたので、私が「ああ!○○さんですか?」と言いましたら「そうです!そうです!」と言って電話の向こうの声が弾んでいました。(この方はメールのやり取りだけでご注文をいただき、宅配便で送らせていただきました。)

 そんな具合に、時にメールを見直してみたり、過去の作品の画像を見ると、たちどころにその時のことが頭の中に蘇ってきます。
そんな具合に、時にメールを見直してみたり、過去の作品の画像を見ると、たちどころにその時のことが頭の中に蘇ってきます。そのお客様のご容姿やその時のエピソードや、時にはそのお宅へお伺いした時のいろいろな風景が…私にとってはどの一つ一つにもそれぞれに思い出があるので、忘れることができないのであります。
 今後も納品で日本中いろんな場所へ行くことになると思いますが、そんな時お近くで「それならついでにうちへ来てちょっとメンテナンスなどについて教えて欲しい」とか、(あってはならないことですが)「ちょっと家具の調子が悪いから見てほしい」「ちょっと教えて欲しいから寄ってください」などと思われたら、お気軽にお声をかけてください。
今後も納品で日本中いろんな場所へ行くことになると思いますが、そんな時お近くで「それならついでにうちへ来てちょっとメンテナンスなどについて教えて欲しい」とか、(あってはならないことですが)「ちょっと家具の調子が悪いから見てほしい」「ちょっと教えて欲しいから寄ってください」などと思われたら、お気軽にお声をかけてください。(でも期日がはっきりしないとそれもできないですね。いい方法が無いか考えてみます。遠方の納品の時は里山だよりで「今月の遠方納品予定」として書くとか…。)
ところで、近年は毎年のようにここで書いているように思いますが、今年はとりわけリピーターのお客様のご注文やお客様のご紹介によるご注文が多い年になったように思います。引き続き、新年早々にもリピーターのお客様のお仕事(学習机セット3セット)が続きます。本当にありがたいことだと思っています。
同時に、年々ある思いが私の中で膨らんで来ています。それをなんとか実現していきたいなと考えています。来年がそういう意味でよい年になるように頑張っていきたいと思います。皆様、健康でよいお年をお迎えください。
2016.12.22
「師走」
家の方も恒例の年末の仕事がたっぷりあります。我が家が毎年やっている年末の仕事は、これからまだこんなにあります。
ざっとこんなところです。このうち年賀状はすでに書き終えました。(私としては画期的に早い!)
昨日は大晦日と正月に食べる食材のうち、お肉だけ買ってきました。このお店はこの辺では有名なお店で、結構遠い町からも買いに来られます。何と言ってもおいしいし安い!うちでは特に豚肉をよく買いますが、よそで買うのと全然違います。
 ところが普段から人気があって行列ができるのですが、この時期は本当に買うのが難しいくらいです。年末の分はすでに予約分で売り切れです。
ところが普段から人気があって行列ができるのですが、この時期は本当に買うのが難しいくらいです。年末の分はすでに予約分で売り切れです。
昨日は開店時間の30分前に行きましたが、すでに4人並んでいました。開店時間にはもう20人ぐらいの人が並んでいました。
・大掃除(母屋と離れ2軒分、それに工房も。掃き掃除、拭き掃除、窓ガラス磨きなどなどたっぷり。)
・年賀状
・お餅つき(臼で言うと2杯分)
・正月飾り(松と大根と鏡餅。鏡餅も作ります。)
・しめ飾りや神様のお札を設置
・年越しの料理作りとその食材の買い出し
・年賀状
・お餅つき(臼で言うと2杯分)
・正月飾り(松と大根と鏡餅。鏡餅も作ります。)
・しめ飾りや神様のお札を設置
・年越しの料理作りとその食材の買い出し
ざっとこんなところです。このうち年賀状はすでに書き終えました。(私としては画期的に早い!)
昨日は大晦日と正月に食べる食材のうち、お肉だけ買ってきました。このお店はこの辺では有名なお店で、結構遠い町からも買いに来られます。何と言ってもおいしいし安い!うちでは特に豚肉をよく買いますが、よそで買うのと全然違います。
 ところが普段から人気があって行列ができるのですが、この時期は本当に買うのが難しいくらいです。年末の分はすでに予約分で売り切れです。
ところが普段から人気があって行列ができるのですが、この時期は本当に買うのが難しいくらいです。年末の分はすでに予約分で売り切れです。昨日は開店時間の30分前に行きましたが、すでに4人並んでいました。開店時間にはもう20人ぐらいの人が並んでいました。
 そんなわけで、大晦日からお正月に食べる特別なお肉をゲットしました。飛騨牛もも肉(しゃぶしゃぶ用)500g、飛騨牛フィレ肉ステーキ2枚223g、国産若鶏もも肉2枚764g、岐阜県産豚バラスライス1,023g…これだけ買って10,000円しません。(帰ってから「フィレ肉じゃなくてサーロインでよかったのに」と妻に叱られましたが…。)
そんなわけで、大晦日からお正月に食べる特別なお肉をゲットしました。飛騨牛もも肉(しゃぶしゃぶ用)500g、飛騨牛フィレ肉ステーキ2枚223g、国産若鶏もも肉2枚764g、岐阜県産豚バラスライス1,023g…これだけ買って10,000円しません。(帰ってから「フィレ肉じゃなくてサーロインでよかったのに」と妻に叱られましたが…。)他はまだこれからです。残り時間を考えると相当きつそうです。
さて工房の方は、長野市のお客様の「栃(トチ)拭き漆こたつ座卓」の拭き漆作業が佳境に入っています。暮れの納品をお楽しみにお待ちください。
また、北名古屋市のお客様の楢(ナラ)学習机のセットも、デスク下ワゴンの加工に取り掛かっています。
そんなわけで年内のスケジュールもきちきちです。
2016.12.14
「他力本願とはそういうことだったのか」
 先日、旦那寺(浄土真宗西本願寺派のお寺です)で報恩講があったので行ってきました。日頃はお寺にはご無礼ばかりしているので、今年は私が総代ということもあって真面目に行ってきました。
先日、旦那寺(浄土真宗西本願寺派のお寺です)で報恩講があったので行ってきました。日頃はお寺にはご無礼ばかりしているので、今年は私が総代ということもあって真面目に行ってきました。ところで、我が家は代々浄土真宗西本願寺派の檀家です。浄土真宗は言うまでもなく親鸞聖人を宗祖とし、阿弥陀如来をご本尊とした「他力本願」の仏教です。
無知をさらけ出すようですが、分かりやすくするためにさらにあえて乱暴な言い方をすると、(中学校の歴史で習って以来)私は実は「他力本願」を自分は何も努力しないで(修業をしないで)仏様(他力)の力に頼るというような理解をしていました。(日常でも、たとえば普段自分は何も努力しないで人に頼ってばかりいるような人のことを「お前は他力本願やな」といったりすることはあると思います。)
だから時折心の中に「禅宗のように修業をして自分を高める宗教の方が素晴らしい宗教なのではないか。浄土真宗のような宗教は『ぬるい』のではないか」と思ったりしていました。でもうちは先祖代々浄土真宗だから、仕方ない…などと思ったり、裏手にある禅宗のお寺に変わろうかなどと思ったり…不謹慎にもそういう浅はかな考えを持ったりしてきました。
 ところが、先日の報恩講で講話を聞いて、少し自分の考えを見直すことができました。講話をされたのは同じ宗派の福井県のお寺のご住職で、べらんめえ調でしたがユーモアがあって大変面白かったです。(話のしかた、話の組み立て方など大変参考になりました。)
ところが、先日の報恩講で講話を聞いて、少し自分の考えを見直すことができました。講話をされたのは同じ宗派の福井県のお寺のご住職で、べらんめえ調でしたがユーモアがあって大変面白かったです。(話のしかた、話の組み立て方など大変参考になりました。)実は親鸞聖人も9歳の時仏門に入り、その後に悟りを開こうと20数年間比叡山の山中に籠って修業をされたとか…。しかし、どれだけ厳しい修業を積んでも悟りは開けない。それどころか、自らの愚かさ足りなさに気づかされるだけで、結局失意のうちに山を下りたとのこと。その後、そんな自分をなんとか救ってくれる教えは無いかと探し続けるうちに出会ったのが今の教えだとか。(いわゆる「浄土三部経」…大無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経)
つまり仏様(阿弥陀様)は人間の愚かさ、足りなさなどすべてをお見通しの上で、それでも尚そういうすべての人を救ってくださる(他力本願)という。 親鸞は自分のことを「悪人」として、「そんな自分でさえ阿弥陀様は救ってくださる」と言います。私たちはそういう阿弥陀様(阿弥陀仏)にすべてをお任せして帰依する(南無)つまり「南無阿弥陀仏」というわけです。私たちはそれを知ったうえで阿弥陀様に心からありがとうという気持ちで「南無阿弥陀仏」というわけです。
ご住職は最後に「私もここではこんな偉そうな話をしているけど、これが終わったら車を運転しながら『やれやれやっと終わった!疲れた。早く帰って家で酒でも飲みたいな』という風に思っているに違いないです。でもそんな私のこともすべて阿弥陀様はお見通しになっておられ、それでも救いへと導いて下さる…」というようなことを話されました。簡単に言うとそんな話でした。
中学校の時に習った「自力本願=自分に厳しく自分を高める」「他力本願=自分は何も努力しないで仏様にすがっていればいい、のんきな教え」(あえて乱暴に言います)というのは全く私の間違った理解でした。(教える先生も大変ですね。なかなかそこまで理解して教えることはできないですから)今まで本当にご無礼ばかりしていましたが、私のような出来の悪い人間はやはりたまにはこういう講話を聞きに行くのがいいかもしれないと思ったのでした。
 さて、工房では北名古屋市のお客様の学習机の制作が進んでいます。本体の組み立てを終わり、天板の制作です。
さて、工房では北名古屋市のお客様の学習机の制作が進んでいます。本体の組み立てを終わり、天板の制作です。楢(ナラ)の3枚接ぎの加工です。雇い実を加工します。当工房ではたいていの場合、この「雇い実」とさらに「ビスケットジョイント」をダブルで使って接ぎ合わせをします。強度も2倍になる上、後で鉋掛けがしやすくなるからです。

 接ぎ合わせをしてボンドが完全に乾いたら鉋掛けをして平らにします。
接ぎ合わせをしてボンドが完全に乾いたら鉋掛けをして平らにします。こういう薄い板になればなるほど反りやすくなるので、板が反ると鉋を掛けるのが難しくなります。(とはいえこの天板で30mmの厚みはあります。学習机の天板としてはむしろ分厚い方だと思います。)
ですから接ぎ合わせた後できるだけ早く鉋掛けの作業までやってしまうようにしています。時間との勝負です。裏も表もやってしまいます。

 裏側をサンディングした後、「吸い付き桟」の加工を進めます。
裏側をサンディングした後、「吸い付き桟」の加工を進めます。
2016.12.06
「冬野菜」
白菜、ネギ、カブ、大根、キャベツ、レタス、ブロッコリー、しょうがなど、少しずついただいています。これから寒くなるとますますおいしくなります。
2016.11.30
「うれしい言葉」
 先日、千葉のお客様のお宅に「こたつ座卓」を納品して来ました。その際に、このところ「こたつ座卓」の問い合わせや注文が多いのを不思議に思っているので、どうして当工房にご注文をいただくことになったのかを聞いてみました。すると、次のようなことをおっしゃいました。
先日、千葉のお客様のお宅に「こたつ座卓」を納品して来ました。その際に、このところ「こたつ座卓」の問い合わせや注文が多いのを不思議に思っているので、どうして当工房にご注文をいただくことになったのかを聞いてみました。すると、次のようなことをおっしゃいました。「自分の父親が昔、歯科技工士をしていました。歯科技工士は普段は裏に隠れて見えない仕事です。それでも父は一人一人のお客さんのことを考えてどの仕事も一生懸命作っていました。佐藤さんのホームページをずっと見ているうちに私の父と同じようなことを感じました。だから佐藤さんにお願いすることにしたんです」
そしてはるばる千葉から当工房へお越しになり、ご相談をいただきました。私が「もしよかったら一緒に板を見に材木店へお連れしますよ」と言いますと、「板を選ぶところからすべて佐藤さんにお任せしたいのです」と言われました。そしてある程度ご希望を聞いて板を選定し、制作しました。
ホームページから私の仕事に向かう姿勢や思いを感じ取っていただき、ご注文をいただけたということですから、本当にうれしく思いました。

 さて、工房では長野市のお客様の栃(トチ)無垢一枚板こたつ座卓は拭き漆の工程に入っています。
さて、工房では長野市のお客様の栃(トチ)無垢一枚板こたつ座卓は拭き漆の工程に入っています。
同時に現在は岐阜市のお客様の欅(ケヤキ)無垢一枚板テーブルの制作中です。削った後裏側をサンディングし、反り止めの加工をします。
2016.11.11
「新車!?」
 畑には玉ねぎの苗を植え、エンドウの種を蒔きました。今年は玉ねぎの苗の育ちが悪く、自分で育てた苗はほとんど使い物になりませんでした。仕方なく苗屋さんに聞いたところ、どの苗屋さんも今年は苗が品不足とのこと。あわてて購入に走ったというわけです。前回も書きましたが今年の秋は野菜関係は厳しいようです。
畑には玉ねぎの苗を植え、エンドウの種を蒔きました。今年は玉ねぎの苗の育ちが悪く、自分で育てた苗はほとんど使い物になりませんでした。仕方なく苗屋さんに聞いたところ、どの苗屋さんも今年は苗が品不足とのこと。あわてて購入に走ったというわけです。前回も書きましたが今年の秋は野菜関係は厳しいようです。
 私はすでに畑で使う耕運機と管理機を1台づつ持っていました。しかし、使い勝手が悪いのにちょっと困っていたので、前から自走式の軽い管理機が欲しかったのです。
私はすでに畑で使う耕運機と管理機を1台づつ持っていました。しかし、使い勝手が悪いのにちょっと困っていたので、前から自走式の軽い管理機が欲しかったのです。ちょうど折も折、近くでJAの中古農機フェアをやっていたので見に行ってきて、即購入してしまいました。これでこれからはちょっと楽に畑仕事が出来そうです。
ところで…先月25日にアメリカに送ったこたつ座卓はまだ届いていないみたいです。アメリカってそんなに遠いところでしたっけ?無事届いてくれるか心配な毎日です。
2016.11.04
「野菜が高い」
 今回は近所の方から松茸をいただいたので松茸ピザも焼いてみました。贅沢!
今回は近所の方から松茸をいただいたので松茸ピザも焼いてみました。贅沢!また恒例のバーベキューでは牡蠣職人(?)による焼き牡蠣や、ワインソムリエ(?)の作るスパークリングワイン(?)なども相変わらずおいしかったです。ほかにも畑で取れたカブやサツマイモや玉ねぎやウインナーなどをダッチオーブンに入れて野菜スープを作ったり、同じく畑から取ってきたレタスやブロッコリー、などで野菜サラダを作ったりしました。どれもとてもおいしかったです。

 そんな中、自然と「最近野菜が高くて買えないよねえ」という話になりました。ニュースでも毎日のようにこの話題を流しています。
そんな中、自然と「最近野菜が高くて買えないよねえ」という話になりました。ニュースでも毎日のようにこの話題を流しています。しかし、おかしなもので、普段他の物(たとえばレジャーやら服やらお菓子やら車やら…)には結構平気でお金をかけるのに、野菜となると高々200円ぐらいでも「高い!買えない!」となるんですねえ。不思議なものです。
まあ我々が作る家具でも同様のことはあります。たとえば家を新築するとき、家自体には平気でどんどんお金をかけて建材を良いものにしたり、デザインを凝ったり、バスタブやら家電製品やらに惜しみなくお金をかけるような方でも「もうお金が無いから家具までお金が回らないんです。」などという話もよくうかがいます。(サビシイ!)

 話を戻して野菜のこと。我が家はおかげさまで野菜についてはかなり自給自足出来ています。
話を戻して野菜のこと。我が家はおかげさまで野菜についてはかなり自給自足出来ています。ジャガイモなどは買ったことがほとんどありません。それにいつでも新鮮で旬な無農薬野菜を食べられるのですから幸せなことだと思います。
 さて、工房では千葉県のお客様の栃(トチ)無垢一枚板こたつ座卓は塗装も終わって完成し、もうすぐ完成する額とともに納品を待つばかりです。
さて、工房では千葉県のお客様の栃(トチ)無垢一枚板こたつ座卓は塗装も終わって完成し、もうすぐ完成する額とともに納品を待つばかりです。そして現在は長野県のお客様の栃(トチ)無垢一枚板こたつ座卓(拭き漆仕上げ)の制作中です。前にも書きましたが、今年は異様に「こたつ座卓」のお問い合わせやご注文が多く、本当に不思議です。こたつを売る業者からも「取引させて欲しい」みたいなお問い合わせがあったくらいです。(もちろんそんなことは無理なので断りました。)
昨日テレビでニュースを見ていたら、最近急に寒くなってきたという話題の中で街頭インタビューがありました。するとある人が「寒くなったからこたつを出してきました」と言っていました。以前だったら「ストーブを出してきました」というところですが「こたつ」と言われたので、なるほどやっぱりこたつが見直されているのかなと感じました。時代はぐるぐる回っているのですね。
2016.10.24
「里の秋 その1」
カラスウリやザクロが生り、いかにも秋らしいです。キウイはもう収穫の時期を迎えています。
千葉県野田市のS様の栃(トチ)無垢一枚板こたつ座卓の方も、大分制作が進んでいます。天板の方はまず表裏ともに鉋掛けをします。幅1メートルを超える大きな一枚板ですし、しかも入り皮やら節やらが多いのでので結構大変でした。鉋屑もいっぱい出ました。
2016.10.13
「こたつブーム?」

 それは以前から度々はありましたが、今年の春ぐらいからでしょうか…メールにしろ電話にしろ、こたつ座卓の問い合わせが急に増えたように思います。
それは以前から度々はありましたが、今年の春ぐらいからでしょうか…メールにしろ電話にしろ、こたつ座卓の問い合わせが急に増えたように思います。今年も残り3ヶ月ですがその間に、4件のこたつ座卓を制作することになっています。(ヒーター付きの物もありますし、掘りごたつ用であったり、ホットカーペットと併用であったりしてヒーターは不要という物もあります。)うち一つは拭き漆仕上げのこたつです。
中には海外在住の方からもご注文があったりします。我が家も昔からずっと居間にはこたつが置かれ(子どもの頃、古い家の頃には掘りごたつがありましたが)、座って生活しています。
いつの間にかリビングはソファとローテーブルというのが主流になりました。しかし、居間にこたつ座卓がある風景はやはり日本独特の物だろうと思います。いろんな考え方、好き嫌いがあるのでどちらがいいとも言えませんが、この頃ちょっとこたつ座卓の生活が見直されているのかもしれません。
いつの間にかリビングはソファとローテーブルというのが主流になりました。しかし、居間にこたつ座卓がある風景はやはり日本独特の物だろうと思います。いろんな考え方、好き嫌いがあるのでどちらがいいとも言えませんが、この頃ちょっとこたつ座卓の生活が見直されているのかもしれません。
そんなわけで今工房では千葉県(アメリカ在住)のK様の栃無垢一枚板こたつ座卓がもうすぐ完成となります。続けて同じく千葉県のS様の栃無垢一枚板こたつ座卓の制作に入っています。
さて、話はがらりと変わりますが、私は日々仕事で赤鉛筆をよく使います。加工中の材料に印を付けたり、線を挽いたりするときに使うからです。荒材に印を付けるときなどは赤鉛筆はすぐにすり減ってしまいます。
ですから本当に結構な数を消費します。100均へ行ったり、安い物を見ると思わず買っておきます。それを知っている何人かの方からプレゼントで赤鉛筆をもらったこともあります。(笑)
 ところが削っていくと小さくなって、鉛筆削りには入らなくなってしまいます。(もちろん、ナイフで削ればいいのですが、なかなか…)
ところが削っていくと小さくなって、鉛筆削りには入らなくなってしまいます。(もちろん、ナイフで削ればいいのですが、なかなか…)
瞬間接着剤でくっつけたりしてみますが、うまくはいきません。ところが、ネットを見ていたらいいものを見つけました。「TUNAGO」という商品です。
ですから本当に結構な数を消費します。100均へ行ったり、安い物を見ると思わず買っておきます。それを知っている何人かの方からプレゼントで赤鉛筆をもらったこともあります。(笑)
 ところが削っていくと小さくなって、鉛筆削りには入らなくなってしまいます。(もちろん、ナイフで削ればいいのですが、なかなか…)
ところが削っていくと小さくなって、鉛筆削りには入らなくなってしまいます。(もちろん、ナイフで削ればいいのですが、なかなか…)瞬間接着剤でくっつけたりしてみますが、うまくはいきません。ところが、ネットを見ていたらいいものを見つけました。「TUNAGO」という商品です。
これで削ってからボンドを付けてつなげば、しっかりとくっつきます。いいものを見つけました。小さくなった赤鉛筆でも、捨てるのはもったいないですからね。
2016.10.07
「三代目」
 まず、イチゴの畝を作って苗を植えました。先月、仮植えをしておいた苗はちゃんと根を張ってしっかりした苗になっていました。
まず、イチゴの畝を作って苗を植えました。先月、仮植えをしておいた苗はちゃんと根を張ってしっかりした苗になっていました。それを仮植え床から掘ってきて、本植えをします。今年は3列、約45個ぐらいの苗を植えることができました。まだ苗は余っているのでまた鉢に植えておき、そのまま育てたり人にあげたりします。
 庭の方には先日買っておいたデルフィニウムの苗を植えました。今回はサカタのセルトップ苗を買いました。(タキイはピット苗と呼んでいます)
庭の方には先日買っておいたデルフィニウムの苗を植えました。今回はサカタのセルトップ苗を買いました。(タキイはピット苗と呼んでいます)全部で50本、庭のあちらとこちらに分けて植えました。元気で冬を越して欲しいです。
 話は変わり、仕事のことです。最近使い続けている鉋がだんだん薄くなってきたりいろいろで、使いにくくなってきました。そろそろ変え時かなと思い、早めに新しい鉋(カンナ)を注文しました。
話は変わり、仕事のことです。最近使い続けている鉋がだんだん薄くなってきたりいろいろで、使いにくくなってきました。そろそろ変え時かなと思い、早めに新しい鉋(カンナ)を注文しました。もちろん、新しい鉋を買ってもすぐに使えるようになるわけではありません。仕込みも必要ですし、その後も「調子が出る(いわば手に馴染むようになるということですが)」ようになるまで時間はかかります。ですから、当分は今の物も同時に使い続けていくことになるでしょう。
 私は工房を始めて以来、鉋やノミなど手工具はすべて新潟県燕市の道具屋さんから買っています。鉋はいつも同じ銘の物です。今回のもので三代目となります。
私は工房を始めて以来、鉋やノミなど手工具はすべて新潟県燕市の道具屋さんから買っています。鉋はいつも同じ銘の物です。今回のもので三代目となります。あっ、言い忘れましたがこれは寸八(すんぱち)と言って刃の幅が約70mmほどの鉋で、仕上げ用に使う、いわば一番よく使う鉋です。前に寸六(すんろく)という、ちょっと小さめの鉋も新しいのに変えました。そちらは二代目です。そちらは面を取ったり、仕上げ鉋の前段階に使ったりという物です。
一つの鉋で大体8〜10年ぐらいは使えるでしょうか…もちろん、上手に使えば10年と言わずそれ以上でも使えると思います。でも、私の場合はかなり鉋の使用頻度は高いと思いますから、それぐらいになるかなと思います。そう考えると、私がこの仕事を辞めるまで、あと1台ぐらいは買うことになるのかなと思います。(それぐらいまで元気で頑張りたいということですけど…。)
さて、工房ではアメリカ在住のお客様のこたつ座卓が着々と出来上がっています。脚部の部材を加工し、仕上げて組み立てをしました。
 天板の方ですが、割れがあるところは「千切り」を埋め、細かい割れも樹脂を入れて埋めました。
天板の方ですが、割れがあるところは「千切り」を埋め、細かい割れも樹脂を入れて埋めました。
2016.09.30
「違和感」
ここのところずっと雨が続いています。そのせいで畑の方は全然だめです。虫が多く、葉物野菜は虫に食われて思うように成長しません。皆さんそう言ってみえます。

 大根は一度全滅したので、最近もう一度種を蒔きなおしました。
大根は一度全滅したので、最近もう一度種を蒔きなおしました。
やむなく防虫網をかけたりしていますが、どれだけ効果があるか…大根に防虫網をかけるなんて長年畑を作っていて初めてのことです。

 大根は一度全滅したので、最近もう一度種を蒔きなおしました。
大根は一度全滅したので、最近もう一度種を蒔きなおしました。やむなく防虫網をかけたりしていますが、どれだけ効果があるか…大根に防虫網をかけるなんて長年畑を作っていて初めてのことです。
 ところで、先日町内の寄り合い(「お日待ち」と言います)がありました。その場である人から提案がありました。町内を通る道路に「防犯カメラ」を付けることと、「カラー舗装」をすることを町に対して要望するというものでした。
ところで、先日町内の寄り合い(「お日待ち」と言います)がありました。その場である人から提案がありました。町内を通る道路に「防犯カメラ」を付けることと、「カラー舗装」をすることを町に対して要望するというものでした。あまりに突然の提案で、正直言ってすぐに理解して考えるということが私には難しかったです。しかし、その間ずっと何か「違和感」を感じていました。その違和感の正体が何かも分からなかったので、発言もしませんでした。結局、町内として要望するということにあっという間に決まりました。
 その後、家に帰ってからもずっと考えていて、その違和感が何であるのか自分なりに少し見えてきました。ここでは詳しく書くことは出来ませんが、簡単に言えば「その前にやることがあるのでは」「もっと大事なことがあるのでは」というようなことかもしれません。
その後、家に帰ってからもずっと考えていて、その違和感が何であるのか自分なりに少し見えてきました。ここでは詳しく書くことは出来ませんが、簡単に言えば「その前にやることがあるのでは」「もっと大事なことがあるのでは」というようなことかもしれません。それは教育問題であったり、町としてのビジョンであったり、人としての生き方の問題であったりします。
2016.09.20
「誕生日」
 先日は私の5?回目の誕生日でした。前回の里山だよりには娘にもらった誕生日プレゼントのことを書きましたが、今回はまた息子からもビールとおつまみのプレゼントをもらいました。
先日は私の5?回目の誕生日でした。前回の里山だよりには娘にもらった誕生日プレゼントのことを書きましたが、今回はまた息子からもビールとおつまみのプレゼントをもらいました。また、最近は銀行やら生命保険会社などからも、プレゼントと言って何かを持ってきてくれます。まあ義理プレゼントというか営業プレゼントですけど…それでも、もらって嬉しくないことはありません。新妻聖子さんからはバースデーカードが…。
さて、仕事の方は栃(トチ)無垢一枚板ダイニングテーブルが大体完成に近づきました。

 まずは裏側を鉋で削って、その後一旦サンディングしてから吸い付き桟(反り止め)加工をします。
まずは裏側を鉋で削って、その後一旦サンディングしてから吸い付き桟(反り止め)加工をします。
多くのメーカーや工房ではこの作業を簡単にするために「サンダー」という工具で磨いて…というより、いわば削って取ってしまいます。そして、つるつるに仕上げて「どうですか、木の自然な表情ですよ。いいでしょう?」と言います。でもそれでは本当の木の表情は出てきません。だって人工的に作ってしまうのですからね。
 私の場合はそれが嫌なので、手間はかかりますが時間をかけて少しづつ木の皮をはがしていきます。彫刻刀やらブラシやらスポンジやらいろいろなものを使って…。
私の場合はそれが嫌なので、手間はかかりますが時間をかけて少しづつ木の皮をはがしていきます。彫刻刀やらブラシやらスポンジやらいろいろなものを使って…。
 私の場合はそれが嫌なので、手間はかかりますが時間をかけて少しづつ木の皮をはがしていきます。彫刻刀やらブラシやらスポンジやらいろいろなものを使って…。
私の場合はそれが嫌なので、手間はかかりますが時間をかけて少しづつ木の皮をはがしていきます。彫刻刀やらブラシやらスポンジやらいろいろなものを使って…。
先日お客様と一緒にある材木店に板を見に行きました。すると見ていた板は耳の部分がかなり汚い(削れていたり虫穴があったり、ささくれていたり…という意味です)板でした。そんな板はよくあります。というかむしろ耳の部分が完全にきれいに残っている板の方が珍しいと言えます。
その時、材木店の方が「こんなのは磨いて(実際は削って)作ってしまえば問題ないです」とお客様に向かって言いました。もちろんその通りです。そんなことは百も承知です。でも私は言いました。「ていうか、僕がそういうのが嫌いですから…」(と言ってその板に難色を示しました。) それを聞いた材木店の人は「なんだこいつ変わったやつだな」と言わんばかりの顔をして、私を見ていました。そのぐらい、私のようなこだわりを持って作っている人は少ないということなのです。
 みんなそうやって人工的な自然の表情を作るのを当たり前にしているのです、この業界は…。(もちろん、初めからガタガタになっているようなひどい状態の木の耳はそういうことができないので、私もやむをえずサンダーを使うこともあります。)
※木の耳については詳しくはこちらもご覧ください。
みんなそうやって人工的な自然の表情を作るのを当たり前にしているのです、この業界は…。(もちろん、初めからガタガタになっているようなひどい状態の木の耳はそういうことができないので、私もやむをえずサンダーを使うこともあります。)
※木の耳については詳しくはこちらもご覧ください。
その時、材木店の方が「こんなのは磨いて(実際は削って)作ってしまえば問題ないです」とお客様に向かって言いました。もちろんその通りです。そんなことは百も承知です。でも私は言いました。「ていうか、僕がそういうのが嫌いですから…」(と言ってその板に難色を示しました。) それを聞いた材木店の人は「なんだこいつ変わったやつだな」と言わんばかりの顔をして、私を見ていました。そのぐらい、私のようなこだわりを持って作っている人は少ないということなのです。
 みんなそうやって人工的な自然の表情を作るのを当たり前にしているのです、この業界は…。(もちろん、初めからガタガタになっているようなひどい状態の木の耳はそういうことができないので、私もやむをえずサンダーを使うこともあります。)
※木の耳については詳しくはこちらもご覧ください。
みんなそうやって人工的な自然の表情を作るのを当たり前にしているのです、この業界は…。(もちろん、初めからガタガタになっているようなひどい状態の木の耳はそういうことができないので、私もやむをえずサンダーを使うこともあります。)
※木の耳については詳しくはこちらもご覧ください。
2016.09.12
「誕生日」

 先日娘から「ちょっと早いけどもう9月になったから、ハイあげるわ…」と言って誕生日プレゼントをもらいました。
先日娘から「ちょっと早いけどもう9月になったから、ハイあげるわ…」と言って誕生日プレゼントをもらいました。最近小銭入れが壊れて、安っぽいものをホームセンターで買ってきて使っていたのを見て知っていたのでしょう。なかなかいいものをプレゼントしてくれました。
毎年一つづつ年を重ねて行くわけですが、昨日も納品したお客様の家で「佐藤さんはいいですね。いつまででも仕事が出来るから…」と言われ、「そうです。体が動く限り、それと注文がなくならない限りはいつまででも、まだまだ何十年もできます。は、は、は…」と言って笑っておりました。
ところでその納品ですが、このお客様は以前に地松無垢一枚板のダイニングテーブルと座卓、そしてタモの食器棚とケヤキ一枚板のちょっとした作業台などを作らせていただきました。そして今回はKOSI-KAKEを3脚とタモ無垢一枚板板脚ベンチ、おにぎりスツールなどをご注文いただきました。
地松一枚板のテーブルも年月を経ていい味を出していました。もちろんとても丁寧に使われているからだと言うことは言うまでもありません。ただし2m40cmという長いテーブルで、しかも板の厚みが3cmほどという薄さですので、(幅方向には反り止めが4本加工してありますが)長手方向にたわみが出ているということなので、途中に束を立てる加工をすることになりました。
お近くなのでご主人も度々工房に遊びに見えますし、ときどきお伺いすることもあります。いつ行っても上質な木の暮らしという気配を感じさせるお宅なので、うらやましくなるぐらいです。(ちなみにご主人も木に関わるお仕事をされています。) 奥様が言われました。「うれしいいわ。こうゆうものに囲まれているとずっとここにいたくなるわ。引きこもりになっちゃうぐらい。あ、は、は…それでまた何か欲しくなるの。また頼むわね」…ありがたいことです。

 ところで今回おにぎりスツールを1個ご注文いただいたので、ついでに何個か作りました。少し在庫あります。よかったらどうぞ。
ところで今回おにぎりスツールを1個ご注文いただいたので、ついでに何個か作りました。少し在庫あります。よかったらどうぞ。
お近くなのでご主人も度々工房に遊びに見えますし、ときどきお伺いすることもあります。いつ行っても上質な木の暮らしという気配を感じさせるお宅なので、うらやましくなるぐらいです。(ちなみにご主人も木に関わるお仕事をされています。) 奥様が言われました。「うれしいいわ。こうゆうものに囲まれているとずっとここにいたくなるわ。引きこもりになっちゃうぐらい。あ、は、は…それでまた何か欲しくなるの。また頼むわね」…ありがたいことです。

 ところで今回おにぎりスツールを1個ご注文いただいたので、ついでに何個か作りました。少し在庫あります。よかったらどうぞ。
ところで今回おにぎりスツールを1個ご注文いただいたので、ついでに何個か作りました。少し在庫あります。よかったらどうぞ。
そのおにぎりスツールの加工の様子の一部です。画像だけダイジェストで載せます。
2016.08.31
「秋支度」
 工房の窓の竹簾にツクツクホウシがとまって鳴いていました。ツクツクホウシを間近に見られるのは珍しいです。
工房の窓の竹簾にツクツクホウシがとまって鳴いていました。ツクツクホウシを間近に見られるのは珍しいです。アブラゼミ、クマゼミ、ニイニイゼミなどはこの辺には昔からよくいます。子どものころはこうしたセミを取るのに夢中になったものです。しかし、ツクツクホウシはなかなか捕まえられませんでした。
そもそもこの辺では珍しいですし、結構木の高いところにいたり、また結構敏感ですばしこい蝉なので捕まえるのが難しいのです。ですから私にとっては憧れの蝉でもありました。(アブラゼミなどは手でも簡単に捕まえられます。) 子どもの頃、父が単身赴任で少し北の地方の山奥(冷涼地)に住んでいた時、夏休みに連れて行ってくれて、そこでツクツクホウシを初めて捕まえた時のことは今でもよく覚えています。
ツクツクホウシはまた夏の終わりを感じさせる蝉でもあります。「ツクツクホーウシ、ツクツクホーウシ、ピーヨロロ、ピーヨロロ、ピ、ピ、ピ、ピ、ピ…」というあの独特の鳴き声がすると「そろそろ夏も終わりか」と一種の寂寥感を覚えます。
そんなわけで時は確実に過ぎて行き、秋に近づいています。関東、東北、北海道の方々には申し訳ありませんがこのたびの台風が一気に暑い空気を吹き飛ばしてくれたかのように、このところ涼しささえ感じるような気候になっています。夜は窓を開けて寝ると寒いぐらいです。昨夜は久しぶりに窓を閉めて寝ました。
 そんな中、畑の方も秋支度を始めています。白菜の種を買ってきてポットに植えました。
そんな中、畑の方も秋支度を始めています。白菜の種を買ってきてポットに植えました。
 先週、ネギの伏せ直しをしました。一旦掘り起こしたネギの皮を一皮むいてもう一度植えなおすのです。こうするとこれから冬にかけてやわらかくおいしいネギが大きく育ちます。
先週、ネギの伏せ直しをしました。一旦掘り起こしたネギの皮を一皮むいてもう一度植えなおすのです。こうするとこれから冬にかけてやわらかくおいしいネギが大きく育ちます。あ、そうそうこの時ネギは北向きに植えるということは常識です。誰かのブログに書いてありましたが、この時、植える間隔を広くすると太くて大きなネギになり、狭く詰めて植えると細いネギになるそうです。本当でしょうか?
 相変わらずナスがよく取れます。数日取らずにいるとこんなにたまってしまうほどです。「秋ナスは嫁に食わすな」と言いますが、うちだけでは食べきれません。
相変わらずナスがよく取れます。数日取らずにいるとこんなにたまってしまうほどです。「秋ナスは嫁に食わすな」と言いますが、うちだけでは食べきれません。
先日の日曜日には、はるばる千葉県からお客様に来ていただきました。ありがたいことです。このところまた問い合わせも多くなっています。とくに「こたつ座卓」の問い合わせもここ数ヶ月多くなっています。こたつ座卓や学習机などはある意味季節物の家具でもあります。(学習机もすでにセットで3件のご注文をいただいています。)
その時期に間に合うようにするためにはお早めにお問い合わせ、ご注文ををいただきたくお願いいたします。
その時期に間に合うようにするためにはお早めにお問い合わせ、ご注文ををいただきたくお願いいたします。
2016.08.25
「晩夏」

 そんな暑さの中、先日の土曜日(37度を記録した猛暑の日)いつものメンバーで「ピザ会」を決行しました。庭のピザ窯でピザやパンを焼き、バーベキューをしたりしていつものように賑やかでした。
そんな暑さの中、先日の土曜日(37度を記録した猛暑の日)いつものメンバーで「ピザ会」を決行しました。庭のピザ窯でピザやパンを焼き、バーベキューをしたりしていつものように賑やかでした。メンバーの中にワインソムリエ(?)もいるので毎回この方がおいしいワインやカクテルやシャンパンを作ってくれますが、それをいただけることが楽しみとなっています。
牡蠣職人(?)もいるので毎回おいしい牡蠣を焼いて食べますが、それも楽しみです。ただし、今回は夏ということもあって牡蠣はパスとなりました。あまりに暑いので工房から大型扇風機とスポットクーラーを庭に持ち出してきて涼を取りながらの活動でした。
毎回ピザ窯で、焼く係は私(なぜか「隊長」と呼ばれています)です。ただでさえ暑いのにピザ窯のそばは猛烈に熱いです。誰かに代わってほしいぐらいですが、まだ跡継ぎが育っていません。(みんなやりたくない?) でも今回は息子が時々火を焚くことだけはやってくれました。いずれピザを焼くワザを教え込もうかと考え中です。
2016.08.16
「残暑見舞い」
このあたりは田舎なので敷地だけは広いです。宅地だけでも何百坪にもなります。それに加えて広大な畑や田んぼがあります。その管理が大変です。田舎に住むとそういう点の苦労もあります。

 畑や庭はこのところ放ったらかしで、なかなか草引きが出来ないので伸び放題です。
畑や庭はこのところ放ったらかしで、なかなか草引きが出来ないので伸び放題です。

 畑や庭はこのところ放ったらかしで、なかなか草引きが出来ないので伸び放題です。
畑や庭はこのところ放ったらかしで、なかなか草引きが出来ないので伸び放題です。

 引き出しは、今回も天秤差しの加工をします。
引き出しは、今回も天秤差しの加工をします。
お盆の間はオリンピックや高校野球の熱戦を少しテレビで楽しみました。おかげで夜更かしになってしまい、生活のリズムがちょと崩れた感じになってしまいました。しかしお盆も終わり、また忙しい日常に戻ります。
2016.08.01
「ポケモンGO!」
「ポケモンGO」が大流行のようです。私は私なりに我が家の周りでポケモンGOをやってみました。かわいいポケモンがいっぱいいました。(私はゲームには興味が無いので、こうなっちゃいます…。)
2016.07.20
「暑さにも負けず」
工房では胡桃(クルミ)の座卓の制作が進んでいます。接ぎ合わせが終わった天板を所定の長さと幅に切り、その後は裏側をカンナ掛けします。毎日30度、いや35度を超える暑さが続きます。工房内は午後になるとその熱気がこもり、大変な暑さになります。外の方がよほど涼しいです。そんな中の天板の鉋掛け作業は結構きついです。
 毎回のことですが、この作業の前にはまず鉋の調整から始めます。主に使う長台ガンナや仕上げガンナ、そして小ガンナの台を台直しガンナを使って削って調整します。
毎回のことですが、この作業の前にはまず鉋の調整から始めます。主に使う長台ガンナや仕上げガンナ、そして小ガンナの台を台直しガンナを使って削って調整します。
鉋の台も木(樫の木)で出来てますから、常に反ったりして動きます。それではいくら刃をきれいに研いでも削れません。ですから、台直しガンナで削って平らにするのです。そしてさらに部分的に削って落としたりします。
 毎回のことですが、この作業の前にはまず鉋の調整から始めます。主に使う長台ガンナや仕上げガンナ、そして小ガンナの台を台直しガンナを使って削って調整します。
毎回のことですが、この作業の前にはまず鉋の調整から始めます。主に使う長台ガンナや仕上げガンナ、そして小ガンナの台を台直しガンナを使って削って調整します。鉋の台も木(樫の木)で出来てますから、常に反ったりして動きます。それではいくら刃をきれいに研いでも削れません。ですから、台直しガンナで削って平らにするのです。そしてさらに部分的に削って落としたりします。

 どのくらいすき取るかと言うと、光が透けて見える程度ですから相当微妙な量になります。(細かいことは難しいので書きません。)
どのくらいすき取るかと言うと、光が透けて見える程度ですから相当微妙な量になります。(細かいことは難しいので書きません。)自作の水平定規をあてて、お日様にすかして見ながら少しづつ削っていくのです。よく「鉋は台で削る」と言われますが、刃を研ぐこと以上にこの台の調整が大事なのです。
 そしてサンディングをします。それから吸い付き桟の加工をします。
そしてサンディングをします。それから吸い付き桟の加工をします。
いよいよ最終段階、天板の表側の加工に入ります。裏側と同様に鉋掛けをします。板の木端(こば)や木口(こぐち)も鉋掛けをします。今回は幅の広い天板ですので作業台に立てかけて削りました。
こんな風にしてもうすぐ完成と言うところまで来ています。T様お楽しみに…。
今週はこの後、壁面収納プロジェクト第3弾「テレビ台」の制作へと入っていきます。また同時に以前から頼まれている加茂郡のK様の小箱も制作していきます。それと、加茂郡のT様の椅子とベンチ、スツールの制作、その後に愛西市K様の栃無垢一枚板ダイニングテーブルとベンチのセット…と進めていきます。皆様お待たせしており、申し訳ありません。暑い夏ですが、頑張っていきます。
今週はこの後、壁面収納プロジェクト第3弾「テレビ台」の制作へと入っていきます。また同時に以前から頼まれている加茂郡のK様の小箱も制作していきます。それと、加茂郡のT様の椅子とベンチ、スツールの制作、その後に愛西市K様の栃無垢一枚板ダイニングテーブルとベンチのセット…と進めていきます。皆様お待たせしており、申し訳ありません。暑い夏ですが、頑張っていきます。
2016.07.15
「真夏」
 先日、壁面収納プロジェクト作品をお客様のところへ納品してきました。今回は相当大きいのと運び込みが難しいということもあり、引越し屋さんを頼みました。
先日、壁面収納プロジェクト作品をお客様のところへ納品してきました。今回は相当大きいのと運び込みが難しいということもあり、引越し屋さんを頼みました。当初は階段では運び込むのは無理だろうと考え、2階の窓を外して引き上げてもらおうと思っていました。しかし、やはりプロですね。あの難しそうな階段を難なく2階まで運び上げてしまいました。やはり何でも専門家に任せるのが一番ですね。
 実はこの壁面収納プロジェクトはまだ終わっていません。中央にはテレビ台を置くことになっています。この日実寸を測ってきましたので、ここにぴったり納まるサイズでこの後制作にかかる予定です。
実はこの壁面収納プロジェクトはまだ終わっていません。中央にはテレビ台を置くことになっています。この日実寸を測ってきましたので、ここにぴったり納まるサイズでこの後制作にかかる予定です。お客様にも「いいですねえ」と満足頂き、よかったです。手前に見えているテーブルやベンチ、椅子なども以前私が制作したものです。隣の部屋には書斎机セットも納めさせていただきました。お客様も「半布里工房のギャラリーのようですねぇ」と笑ってみえました。

 さて大物2つを無事納品終えて、ちょっと一息したいところですが、そうは問屋がおろしません。
さて大物2つを無事納品終えて、ちょっと一息したいところですが、そうは問屋がおろしません。息つく暇なく現在は一宮市のT様の座卓制作にかかっています。木取りの後、板の平面削りです。機械に入らない幅広の板なので、電動鉋を使って片面の平面を出します。板を載せてみて平行になっているかどうか目視して作業を進めていきます。

 「隠し雇い実接ぎ」という方法で板を接ぎ合わせます。私はいつも雇核(やといざね)とピスケットをダブルで使って接ぎ合わせることにしています。
「隠し雇い実接ぎ」という方法で板を接ぎ合わせます。私はいつも雇核(やといざね)とピスケットをダブルで使って接ぎ合わせることにしています。こうして天板を接ぎ合わせします。幅が広く4枚接ぎなので、まずは2枚ずつ2回(2日)に分けて接ぎ合わせをしました。そうしないと夏場は暑すぎて、ボンドが途中で乾いてしまう恐れがあるからです。
2016.07.05
「3重苦」
非常に暑い日が続きます。もう真夏のようです。この先どうなってしまうのでしょうか?それに加えて最近コバエが発生しています。3年前と比べると少しですし、本宅の中を毎日掃除しなければならないほどではないので、そう思うと大したことはありませんが…。
 それでも、工房で仕事中に、首やら耳の中やら腕やら体にまとわりつくのは本当にうっとおしいです。機械を使っている時には危険ですらあります。写真には小さすぎてうまく映りませんが、確かに発生しています。
それでも、工房で仕事中に、首やら耳の中やら腕やら体にまとわりつくのは本当にうっとおしいです。機械を使っている時には危険ですらあります。写真には小さすぎてうまく映りませんが、確かに発生しています。
 それでも、工房で仕事中に、首やら耳の中やら腕やら体にまとわりつくのは本当にうっとおしいです。機械を使っている時には危険ですらあります。写真には小さすぎてうまく映りませんが、確かに発生しています。
それでも、工房で仕事中に、首やら耳の中やら腕やら体にまとわりつくのは本当にうっとおしいです。機械を使っている時には危険ですらあります。写真には小さすぎてうまく映りませんが、確かに発生しています。
 すでにスイカは5個も取られました。せっかく楽しみにしている野菜なのに…腹が立ってどうしようもないです。昨日はすぐそばに仕掛けられた檻に1匹の猿がかかっていました。あまりに頭が来たのでこの猿にあたってしまいました。この猿だけが悪いのではないですが…。
すでにスイカは5個も取られました。せっかく楽しみにしている野菜なのに…腹が立ってどうしようもないです。昨日はすぐそばに仕掛けられた檻に1匹の猿がかかっていました。あまりに頭が来たのでこの猿にあたってしまいました。この猿だけが悪いのではないですが…。そんなわけで、うだるような暑さとコバエと猿という3重苦にあえぎながら過ごす毎日です。
そんなことを言ってばかりいても仕方がないので、きれいな花の画像で癒されてください。
そんなわけで第一弾食器棚、第2弾収納棚があと少しで完成となります。この2つを一旦納品後、続いて第3弾テレビ台は再来週以降に制作に入る予定です。その前に一宮市のT様の座卓を制作予定です。皆様、お待たせしていて申し訳ありません。よろしくお願いします。
2016.06.27
「夕ご飯」
工房で作業中に、首筋や耳の中がモゾッとするようになりました。ついにあの「コバエ」が出始めました。まだ本当に少しだけで、工房の中だけにしかも短時間で留まっているのでいいですが、本宅の中まで出るようになってはどうしようもありません。昨年、一昨年と大発生は無く何とか平和に暮らせましたが、今年はどうなることかとちょっと不安な毎日を過ごしています。
 話は変わりますが、毎日我が家の夕食には畑で取れた野菜が料理されて出ます。野菜だらけの食卓になってしまうので子どもたちはちょっとかわいそうですが、それでも旬の野菜ほどいいものはありません。無農薬だし。
話は変わりますが、毎日我が家の夕食には畑で取れた野菜が料理されて出ます。野菜だらけの食卓になってしまうので子どもたちはちょっとかわいそうですが、それでも旬の野菜ほどいいものはありません。無農薬だし。
きゅうりが取れすぎるので妻は困り顔ですが、なんとかきゅうりのキュウちゃんにしたり、三杯酢につけたりして料理してくれます。キュウちゃんは人にあげたりもしています。
 話は変わりますが、毎日我が家の夕食には畑で取れた野菜が料理されて出ます。野菜だらけの食卓になってしまうので子どもたちはちょっとかわいそうですが、それでも旬の野菜ほどいいものはありません。無農薬だし。
話は変わりますが、毎日我が家の夕食には畑で取れた野菜が料理されて出ます。野菜だらけの食卓になってしまうので子どもたちはちょっとかわいそうですが、それでも旬の野菜ほどいいものはありません。無農薬だし。きゅうりが取れすぎるので妻は困り顔ですが、なんとかきゅうりのキュウちゃんにしたり、三杯酢につけたりして料理してくれます。キュウちゃんは人にあげたりもしています。
 前々回の里山だよりに書いたジャガイモは、ほぼ毎日のように料理に出されます。これは一番手っ取り早く料理できる定番メニューです。ジャガイモを切ってレンジでチンして、マヨネーズとしょうゆにつけて食べます。ほくほくしておいしいです。
前々回の里山だよりに書いたジャガイモは、ほぼ毎日のように料理に出されます。これは一番手っ取り早く料理できる定番メニューです。ジャガイモを切ってレンジでチンして、マヨネーズとしょうゆにつけて食べます。ほくほくしておいしいです。
 これはポテトサラダです。うちのじゃがいもは本当においしいと思います。ほくほく感が全然違います。以前ジャガイモを差し上げた人もやはりポテトサラダを作ったと言って、写真を撮ってLINEで送ってくださいました。
これはポテトサラダです。うちのじゃがいもは本当においしいと思います。ほくほく感が全然違います。以前ジャガイモを差し上げた人もやはりポテトサラダを作ったと言って、写真を撮ってLINEで送ってくださいました。
 こちらはじゃがいもを掘って間もないころだけの限定料理と言ってもいいでしょう。すごく小さなジャガイモで普通なら捨てるような物ですが、それを皮が付いたまま揚げて、煮て料理したものです。掘ってすぐの頃は皮もやわらかく、こういう小さいジャガイモはそのままこうして料理して食べることができます。これがまたとってもおいしいのです。
こちらはじゃがいもを掘って間もないころだけの限定料理と言ってもいいでしょう。すごく小さなジャガイモで普通なら捨てるような物ですが、それを皮が付いたまま揚げて、煮て料理したものです。掘ってすぐの頃は皮もやわらかく、こういう小さいジャガイモはそのままこうして料理して食べることができます。これがまたとってもおいしいのです。ちなみにこの料理は妻の母が作ってくださいました。妻でも出来なくはないのですが、この味はやはりお母さんの味ですね。もちろん他にもいろんなジャガイモ料理を食べています。カレーだって、うちのじゃがいもが入っただけで味は全然違ってきます。
そういえば先日お出でいただいてご注文いただいたお客様(何度もリピートいただいているお客様ですが)にジャガイモときゅうりを少し差し上げましたら、LINEでご連絡くださいました。
「じゃがいもときゅうりも早速いただきました。ジャガイモを煮物にしたら子供達がおかわりにして食べて、月曜日のお弁当にもジャガイモを入れていきました。きゅうりも歯ごたえがしっかりしていてとってもおいしかったです」…喜んでいただけて私もとっても嬉しいです。以上、今日はうちのじゃがいもの大自慢大会となってしまいました。
2016.06.15
「あれこれ」
 少し前になりますが、「名古屋木工家ウィーク」というのが開催され、行ってきました。目的は人間国宝である「須田賢司」氏の講演を聞くことです。須田氏の名前は私がお世話になっている銘木店の社長さんからもよく聞いていたので、(須田氏もこの銘木店からよく材を購入されるそうです)ぜひ話を聞きたいと思ったのです。
少し前になりますが、「名古屋木工家ウィーク」というのが開催され、行ってきました。目的は人間国宝である「須田賢司」氏の講演を聞くことです。須田氏の名前は私がお世話になっている銘木店の社長さんからもよく聞いていたので、(須田氏もこの銘木店からよく材を購入されるそうです)ぜひ話を聞きたいと思ったのです。その銘木店の社長さんと息子さんもおみえになり、一緒に講演を聞いていました。須田氏も講演の中でこの銘木店を引き合いに出され、「私らはそういう銘木店が良い木を持っておいていただけるおかげで仕事が出来ています」とおっしゃっていました。あらためて貴重な材料を最大限に生かしてやることの使命のような物を感じさせられました。

 工房では食器棚は一応完成し、プロジェクト第2弾の収納棚の部材制作に取り掛かっています。
工房では食器棚は一応完成し、プロジェクト第2弾の収納棚の部材制作に取り掛かっています。(一応というのにはわけがあります。写真で見る通り側面の羽目板がはまっていません。これは第2弾の収納棚の側面の羽目板と共木で制作するため、後で一緒に作ることにしているからです。)

 第2農園ではほったらかしにしておいたネットメロンがいつの間にか実を付けていました。もう網目ができているものもあります。こちらも摘果をしなくては…。
第2農園ではほったらかしにしておいたネットメロンがいつの間にか実を付けていました。もう網目ができているものもあります。こちらも摘果をしなくては…。きゅうりはすでに毎日食卓に上がっています。あまりにも取れすぎるので、ちょっと肩身が狭いです。妻がキュウちゃん漬けにしてくれました。ビールのつまみにちょうどいい!
 キャベツは青虫に結構やられます。私は基本的に無農薬ですので、こうなるのはある程度仕方がないことです。(農薬を使うぐらいならたぶん野菜作りなどはしないと思います。無農薬というのに家庭菜園の意味があるのだと思ってますから。)
キャベツは青虫に結構やられます。私は基本的に無農薬ですので、こうなるのはある程度仕方がないことです。(農薬を使うぐらいならたぶん野菜作りなどはしないと思います。無農薬というのに家庭菜園の意味があるのだと思ってますから。)とにかく青虫を手で取るしかありません。しかし、すごい数です。小さいのも含めると、一つの株に100匹以上は絶対いると思います。見つけたら手でつぶすのですが、妻などに言わせるとそんなことは絶対無理のようです。相当野蛮な行為のようです。しかし、祖母もそんなふうでした。
田舎で暮らしていればそんなことは日常茶飯事なのではないでしょうか。田舎暮らしは生き物と人とがより近い関係になります。だからこそライバル関係(大げさに言うとどちらが勝つかということ)になるので、それは仕方がないことです。それでも結局青虫には勝てませんけど…よくキャベツを料理に使うときに妻が「ギャー!いた!」と声を出しているのを聞きます…面目ない…。
そのほか、ピーマン、ししとう、しょうが、ゴーヤ、サツマイモなども順調に大きくなっています。サツマイモは猿に何度かいたずらされて引っこ抜かれましたが、すぐにまた植えなおしたら、なんとか復活しています。
2016.06.07
「ジャガイモ収穫」
それは突然始まりました。ジャガイモの収穫です。昨日の朝、いつも通り畑を見に出ました。すると近所の人がジャガイモを掘ってみえるのに気が付きました。(そういえば天気予報で今週から来週にかけてあまり天気が良くないって言ってたなぁ。)
 そう思い、「よし今日やるぞ!」といきなり決めました。そもそもすでに少しづつ掘ってはジャガイモをいただいていました。十分大きくなっていたのです。茎もほとんど倒れ、葉も黄色く枯れかけてきていました。これは「もう掘ってもいいよ」という合図です。
そう思い、「よし今日やるぞ!」といきなり決めました。そもそもすでに少しづつ掘ってはジャガイモをいただいていました。十分大きくなっていたのです。茎もほとんど倒れ、葉も黄色く枯れかけてきていました。これは「もう掘ってもいいよ」という合図です。
この前の里山だよりにも書きましたが今年は大変成長が良く、他所よりも早く大きくなっているみたいです。ですから、通常よりも2週間近く早いですが、もう掘っても大丈夫です。
 そう思い、「よし今日やるぞ!」といきなり決めました。そもそもすでに少しづつ掘ってはジャガイモをいただいていました。十分大きくなっていたのです。茎もほとんど倒れ、葉も黄色く枯れかけてきていました。これは「もう掘ってもいいよ」という合図です。
そう思い、「よし今日やるぞ!」といきなり決めました。そもそもすでに少しづつ掘ってはジャガイモをいただいていました。十分大きくなっていたのです。茎もほとんど倒れ、葉も黄色く枯れかけてきていました。これは「もう掘ってもいいよ」という合図です。この前の里山だよりにも書きましたが今年は大変成長が良く、他所よりも早く大きくなっているみたいです。ですから、通常よりも2週間近く早いですが、もう掘っても大丈夫です。
 全部で9列作りましたが、1列分ぐらいはこれまでにすでに掘って食べたり、知り合いにあげたりしました。ですので、残り8列を一気に掘りました。結構な重労働です。
全部で9列作りましたが、1列分ぐらいはこれまでにすでに掘って食べたり、知り合いにあげたりしました。ですので、残り8列を一気に掘りました。結構な重労働です。こうして掘ったじゃがいもは少し畑に置いておき、乾かします。この間に猿やカラスに取られないようにだけ注意します。

 こうして収穫かごに5杯分収穫できました。一株に平均10個ついていたとすると、全部で1500個近く取れたことになります。
こうして収穫かごに5杯分収穫できました。一株に平均10個ついていたとすると、全部で1500個近く取れたことになります。数だけでなく今年は型(大きさ)も良く、Lサイズ、LLサイズ、Lに近いMサイズが多かったです。(2014年はこんな感じでした。)
 また、早く掘ったせいだと思いますが、肌がきれいでした。いつもは欲張って「もう少し大きくなるまで掘るのを待とう」と思い、掘ってみると確かに大きくなっていますが、肌にぶつぶつができていたり、大きい芋の中にす(割れ)が入っていたりすることもあるのです。
また、早く掘ったせいだと思いますが、肌がきれいでした。いつもは欲張って「もう少し大きくなるまで掘るのを待とう」と思い、掘ってみると確かに大きくなっていますが、肌にぶつぶつができていたり、大きい芋の中にす(割れ)が入っていたりすることもあるのです。収穫の時に一番大事なことは、十分乾かすことです。そうしないと保存している間に腐ってしまいます。そういう意味でもジャガイモを掘るのはよく晴れた日でないとだめです。
その他の野菜も、おおむね順調に育っています。ただトマトが例年に比べると(苗が悪かったんだと思いますが)少し元気が無いように見えます。ですので、様子を見ては水をやったり、追肥をしたりしています。私はトマトだけは水も肥料も一切やらないという育て方をしてきました。それはこれまで一応成功してきました。でも、やはりケースバイケースです。
私に植物を育てることを教えてくれた親戚のおじさん(すでに亡くなっていますが)がいつも言っていました。「正裕(私の名前)、花(野菜)はとにかくよく見てやることや。その顔を見とって、水が欲しそうな顔をしとったら水をやればいいし、肥え(肥料)が欲しそうな顔をしとったら肥えをやればいいんや。子育てと同じやぞ。子どももその顔を見とれば今何をしてやればいいか分かるでな。」
私に植物を育てることを教えてくれた親戚のおじさん(すでに亡くなっていますが)がいつも言っていました。「正裕(私の名前)、花(野菜)はとにかくよく見てやることや。その顔を見とって、水が欲しそうな顔をしとったら水をやればいいし、肥え(肥料)が欲しそうな顔をしとったら肥えをやればいいんや。子育てと同じやぞ。子どももその顔を見とれば今何をしてやればいいか分かるでな。」
2016.06.01
「憧れ」

 わが「jagar's garden」も4年目になります。絶えることなく次から次へと花が咲いて、そういう意味では思っていた通りの庭になってきました。しかし、残念なことに私が思い描く庭にはまだまだ遠いです。
わが「jagar's garden」も4年目になります。絶えることなく次から次へと花が咲いて、そういう意味では思っていた通りの庭になってきました。しかし、残念なことに私が思い描く庭にはまだまだ遠いです。
 その理由の一つは「バラ」が思うようにきれいに育ってくれないこと。バラをうまく咲かせてこそガーデナーと言えるのだと思いますが…あっ、私は家具作りが生業で、ガーデニングはただの趣味ですが…どうしてもバラがうまくいきません。でも、いつかきっとバラも美しく咲く庭にしたいと思っています。
その理由の一つは「バラ」が思うようにきれいに育ってくれないこと。バラをうまく咲かせてこそガーデナーと言えるのだと思いますが…あっ、私は家具作りが生業で、ガーデニングはただの趣味ですが…どうしてもバラがうまくいきません。でも、いつかきっとバラも美しく咲く庭にしたいと思っています。また理由の二つ目は私の好きなルピナスとラベンダーもうまく育たないということ。この2つの花がいっぱい咲く庭が夢なのですが、何回植えてもうまく育ちません。もちろん、気候のせいもあるでしょう。そもそもこのあたりの土地には向かない花なのかもしれません。
でも、やはり見果てぬ夢なのであります。私がかつて一時すごした飛騨の街道沿いには、ラベンダーがそれはそれは美しく咲いていたのであります。その光景を忘れられないのであります。秋にはブルーベリーをいっぱい植えようと計画中…楽しみは尽きません。
さて工房では、食器棚は引き出しの仕込まで終わりました。例によって手加工による「蟻組み(天秤差し)加工」を行い、仕込作業(引き出しの仕込みpart1、part2)も終わりました。
2016.05.24
「年代物」
「年代物」と言ってもお宝の話ではありません。工房内を見渡すと結構古いものがあって、ずっと使い続けているという話です。
 例えば、工房においてあるこの事務机…実はこれは亡き父の形見の学習机です。父が若かりし学生の頃使っていたという学習机…戦中か戦後間もないころのものと思われます。
例えば、工房においてあるこの事務机…実はこれは亡き父の形見の学習机です。父が若かりし学生の頃使っていたという学習机…戦中か戦後間もないころのものと思われます。
決して良い材料が使われているわけでもなく、またすごく凝ったつくりをしているわけでもありません。材料も安いものでしょう。引き出しなどの組み立てには釘も使われていて、底板などはラワン合板です。
そんな机ですが、私はこれがなぜか気に入っていて、大学生になったときぐらいだと思いますが父から譲ってもらい、下宿先でも使っていました。思えばそのころからすでに木の家具というものに惹かれていたのかもしれません。当時は全く分かりませんでしたが…。
 例えば、工房においてあるこの事務机…実はこれは亡き父の形見の学習机です。父が若かりし学生の頃使っていたという学習机…戦中か戦後間もないころのものと思われます。
例えば、工房においてあるこの事務机…実はこれは亡き父の形見の学習机です。父が若かりし学生の頃使っていたという学習机…戦中か戦後間もないころのものと思われます。決して良い材料が使われているわけでもなく、またすごく凝ったつくりをしているわけでもありません。材料も安いものでしょう。引き出しなどの組み立てには釘も使われていて、底板などはラワン合板です。
そんな机ですが、私はこれがなぜか気に入っていて、大学生になったときぐらいだと思いますが父から譲ってもらい、下宿先でも使っていました。思えばそのころからすでに木の家具というものに惹かれていたのかもしれません。当時は全く分かりませんでしたが…。
 このちょっとしたスツールはもう20年以上前に、縁あって廃校になるという小学校の図工室(理科室?)の机とスツールのセットを分けていただいたものです。ですから、これも相当古いものでおそらくすでに50年ぐらいは経っているものと思います。
このちょっとしたスツールはもう20年以上前に、縁あって廃校になるという小学校の図工室(理科室?)の机とスツールのセットを分けていただいたものです。ですから、これも相当古いものでおそらくすでに50年ぐらいは経っているものと思います。もちろん接着剤の効果は切れて、ほぞも少し緩んで多少はガタつくものの、使用に際して困るようなことは全然ありません。しっかりしています。昔の無名の大工さんが作ったであろうと思われますが、「四方ころび」という技術で足を差し込んであります。なかなか大したものです。
 このきったない(汚い)ハンガーは果たしていつごろのものかもわかりません。祖父母が使っていたものです。いずれにせよ昭和の高度経済成長時代のころのものでしょう。ぼろぼろに見えますが、全然壊れないのでそのまま使い続けています。
このきったない(汚い)ハンガーは果たしていつごろのものかもわかりません。祖父母が使っていたものです。いずれにせよ昭和の高度経済成長時代のころのものでしょう。ぼろぼろに見えますが、全然壊れないのでそのまま使い続けています。
 この棚と先に書いた机の横に写っている白い整理ダンスは、私が工房を始めた時にとりあえず収納が欲しくて、家で使っていてもう使用しなくなっていたものを工房に持ってきて使ったものです。いずれもフラッシュ家具の安い物で、センスも何もありませんが、捨てられずに使い続けています。
この棚と先に書いた机の横に写っている白い整理ダンスは、私が工房を始めた時にとりあえず収納が欲しくて、家で使っていてもう使用しなくなっていたものを工房に持ってきて使ったものです。いずれもフラッシュ家具の安い物で、センスも何もありませんが、捨てられずに使い続けています。
 数年前に庭にピザ窯を作った時に、窯の中を濡れ拭きするモップが欲しくてホームセンターなどを回って探しました。しかし、どこへ行っても布巾を挟む部分がプラスティックでできたものしか売ってありません。それでは300度以上にもなる窯に入れたら溶けてしまうので使い物になりません。
数年前に庭にピザ窯を作った時に、窯の中を濡れ拭きするモップが欲しくてホームセンターなどを回って探しました。しかし、どこへ行っても布巾を挟む部分がプラスティックでできたものしか売ってありません。それでは300度以上にもなる窯に入れたら溶けてしまうので使い物になりません。ある時、近くの古い金物屋さんが廃業のため在庫処分をするということを聞きつけて、行ってみたところ、これを見つけたのです。ですから結構古いもので、昔はこういうものを売っていたのですね。これは重宝しています。
あと、写真のカウンターチェアと収納棚は、工房を開設して間もないころ試作したりしてみたものです。もうすぐ20年近くなりますが、(当たり前ですが)結構乱暴に扱っていてもまったく問題なく現在も使用しています。
ポリシーでセンスの悪いものは使わないとか、着用しないとかいう人から見ると「そんなものをよく使っているなぁ」と笑われるかもしれません。(最近はオサレな人が増えましたからね)でも私は物を大事に使うことが大切だと思うので、何を言われようが関係ありません。これらのものは壊れるまで使い続けると思います。
さて、工房では食器棚の扉などの制作最中です。この作業はいわば化粧のようなもので、表に見える部分です。もちろん表に見えないここまでの段階が相当大事なのですが、表に見える部分ですから…言うまでもありません。

 扉、引き戸の羽目板の接ぎ合わせです。今回は中央にあえてスリットを入れて(ブックマッチで)接ぎ合わせてみました。そして組み立てる前に塗装もしておきます。
扉、引き戸の羽目板の接ぎ合わせです。今回は中央にあえてスリットを入れて(ブックマッチで)接ぎ合わせてみました。そして組み立てる前に塗装もしておきます。
さて、工房では食器棚の扉などの制作最中です。この作業はいわば化粧のようなもので、表に見える部分です。もちろん表に見えないここまでの段階が相当大事なのですが、表に見える部分ですから…言うまでもありません。

 扉、引き戸の羽目板の接ぎ合わせです。今回は中央にあえてスリットを入れて(ブックマッチで)接ぎ合わせてみました。そして組み立てる前に塗装もしておきます。
扉、引き戸の羽目板の接ぎ合わせです。今回は中央にあえてスリットを入れて(ブックマッチで)接ぎ合わせてみました。そして組み立てる前に塗装もしておきます。
引き戸の下には戸車を入れる穴も加工します。真鍮のVレールと溝に合わせて段欠き加工を施します。0.5mm違うとうまくいきませんので、慎重に加工します。
この後、蝶番の取り付け加工、引き出し加工(天秤差し)、棚板加工、底板加工と進んでいきます。
2016.05.19
「じわじわ制作中」
一昨日の火曜日、工房裏手のお寺でまた「お寺マルシェ」が開催されました。
 今年は「バンドネオン」の生演奏もあるというので、ちょっと見に行ってきました。プロのバンドネオン奏者の方とパーカッショニストの方とのコラボでしたが、なかなか良かったです。お寺の雰囲気にも妙に合っている気がしました。
今年は「バンドネオン」の生演奏もあるというので、ちょっと見に行ってきました。プロのバンドネオン奏者の方とパーカッショニストの方とのコラボでしたが、なかなか良かったです。お寺の雰囲気にも妙に合っている気がしました。
 今年は「バンドネオン」の生演奏もあるというので、ちょっと見に行ってきました。プロのバンドネオン奏者の方とパーカッショニストの方とのコラボでしたが、なかなか良かったです。お寺の雰囲気にも妙に合っている気がしました。
今年は「バンドネオン」の生演奏もあるというので、ちょっと見に行ってきました。プロのバンドネオン奏者の方とパーカッショニストの方とのコラボでしたが、なかなか良かったです。お寺の雰囲気にも妙に合っている気がしました。
2016.05.10
「GWも終わり…」
ゴールデンウィークは、みなさんはどのように過ごされたのでしょうか?我が家は毎年のことですが、基本的に出かけることはないです。もちろん大半は工房で仕事となりますが、それ以外は相変わらず庭をいじったり、畑で作業をしたり、いつものメンバーでピザパーティーをしました。
 ただし、今年は初日(29日)に劇団四季のミュージカルを見に行くことができました。「オペラ座の怪人」です。私はミュージカルは大好きで、劇団四季も昔はよく見に行きました。(以前の里山だよりにも少し書いています。)
ただし、今年は初日(29日)に劇団四季のミュージカルを見に行くことができました。「オペラ座の怪人」です。私はミュージカルは大好きで、劇団四季も昔はよく見に行きました。(以前の里山だよりにも少し書いています。)
今回はずいぶん久しぶりのことでした。この「オペラ座の怪人」は25周年記念公演の様子がテレビ(WOWOW)でも放映されて、それを録画して時々見ていました。世界最高のキャストの圧倒的なパフォーマンスに、見るたびに感動しています。それだけに今回はあまり期待はしていなかったのですが、実際見てみるとそんなことはなく、素晴らしかったです。想像以上で感動しました。
今年はなんだかコンサートづいていて、夏にはあのサラブライトマンの公演を見に行く予定ですし、冬には新妻聖子のコンサートも見に行きます。(この間銀行へ行ったら、「大相撲のチケットの応募ができますけど、しますか?」と言われたので応募しておきました。そちらも当たったりして…)
 ただし、今年は初日(29日)に劇団四季のミュージカルを見に行くことができました。「オペラ座の怪人」です。私はミュージカルは大好きで、劇団四季も昔はよく見に行きました。(以前の里山だよりにも少し書いています。)
ただし、今年は初日(29日)に劇団四季のミュージカルを見に行くことができました。「オペラ座の怪人」です。私はミュージカルは大好きで、劇団四季も昔はよく見に行きました。(以前の里山だよりにも少し書いています。)今回はずいぶん久しぶりのことでした。この「オペラ座の怪人」は25周年記念公演の様子がテレビ(WOWOW)でも放映されて、それを録画して時々見ていました。世界最高のキャストの圧倒的なパフォーマンスに、見るたびに感動しています。それだけに今回はあまり期待はしていなかったのですが、実際見てみるとそんなことはなく、素晴らしかったです。想像以上で感動しました。
今年はなんだかコンサートづいていて、夏にはあのサラブライトマンの公演を見に行く予定ですし、冬には新妻聖子のコンサートも見に行きます。(この間銀行へ行ったら、「大相撲のチケットの応募ができますけど、しますか?」と言われたので応募しておきました。そちらも当たったりして…)
 ところで畑のほうは今イチゴが旬を迎えています。うちのは「おおきみ」という大型の種類です。大きくて甘くておいしいイチゴです。ただし、いつもと比べると今年はちょっと小さい気がします。
ところで畑のほうは今イチゴが旬を迎えています。うちのは「おおきみ」という大型の種類です。大きくて甘くておいしいイチゴです。ただし、いつもと比べると今年はちょっと小さい気がします。でも、味はイチゴの味がしっかりしておいしいです。先日ピザ会の時に出したら、「イチゴ狩りのイチゴより断然おいしい」と言ってくれる人もいました。
 「jagar's garden」はモッコウバラの季節は終わり、これからバラ、クレマチス、そしてアジサイなどの初夏の庭へと移っていきます。
「jagar's garden」はモッコウバラの季節は終わり、これからバラ、クレマチス、そしてアジサイなどの初夏の庭へと移っていきます。現在はと言えば、昨年の冬にピット苗で購入してたくさん植えつけたデルフィニウムがとてもきれいです。クレマチスも花を咲かせ始めました。
 以前鉢植えにした「栃」の木が結構大きくなってきました。地面に植えてしまうと将来(と言っても100年も先のことですが)大木になって、どうしようもなくなるので鉢に植えて観葉植物として育てているのですが、どうやら鉢の下へ根が貫通して地面まで根を張ってしまっているようです。
以前鉢植えにした「栃」の木が結構大きくなってきました。地面に植えてしまうと将来(と言っても100年も先のことですが)大木になって、どうしようもなくなるので鉢に植えて観葉植物として育てているのですが、どうやら鉢の下へ根が貫通して地面まで根を張ってしまっているようです。そのおかげでここ1年ほどの間にぐんぐん成長しています。さてどうしたものか…。

 さて工房では、食器棚の制作の方がようやく組み立てまで来ました。部材制作の段階で後々のことまで見通して加工をしなければならないので、ここまで来るのには結構手間がかかりました。
さて工房では、食器棚の制作の方がようやく組み立てまで来ました。部材制作の段階で後々のことまで見通して加工をしなければならないので、ここまで来るのには結構手間がかかりました。例えば引き戸の溝加工も部材のうちにしておくわけですが、今回は(この後で制作する収納棚の引き戸も含めて)大きな(少し重量もありそうな)引き戸になるので戸車をつけるということにして、まずはサンプルを作って検討しました。そのあとで溝加工を行いました。
 そしていよいよ組み立てですが、框組み構造の今回の食器棚のように複雑なものは一度で組み立てはできません。少しづつ何度にも分けて組み立てていきます。
そしていよいよ組み立てですが、框組み構造の今回の食器棚のように複雑なものは一度で組み立てはできません。少しづつ何度にも分けて組み立てていきます。しかも、組み立てに使うハタガネ(締め具)の数にも限りがあって、一度で全部の組み立てができません。結果、組み立てだけでも何日もかかってしまいます。
2016.05.02
「久しぶりの」
お客様からメールをいただきました。「最近(HPが)全然更新されませんが体調が良くないのですか?心配しています。杞憂ならば良いのですが…」
どっこい大丈夫です。ご心配をおかけしてすみません。

 仕事の方はここの所ずっと(相変わらず)地味な作業の繰り返しであります。複雑な箱物制作なので目ざましい進展はありませんが、少しづつ前に進んでいます。
仕事の方はここの所ずっと(相変わらず)地味な作業の繰り返しであります。複雑な箱物制作なので目ざましい進展はありませんが、少しづつ前に進んでいます。

 仕事の方はここの所ずっと(相変わらず)地味な作業の繰り返しであります。複雑な箱物制作なので目ざましい進展はありませんが、少しづつ前に進んでいます。
仕事の方はここの所ずっと(相変わらず)地味な作業の繰り返しであります。複雑な箱物制作なので目ざましい進展はありませんが、少しづつ前に進んでいます。

 部材の数が多く、しかも複雑な組み合わせになるので、間違えないようにすべての部材に印や名前、表とか裏とか前とか後とか…たくさんの覚書を書いては作っているのですが、あまりに多いので頭がこんがらがっちゃいそうです。それでも何とかもうすぐ組み立てに入れそうです。
部材の数が多く、しかも複雑な組み合わせになるので、間違えないようにすべての部材に印や名前、表とか裏とか前とか後とか…たくさんの覚書を書いては作っているのですが、あまりに多いので頭がこんがらがっちゃいそうです。それでも何とかもうすぐ組み立てに入れそうです。

 さて、里山だよりも1か月近く空いたので、周りの景色もずいぶん変わっています。連休初日には畑に夏野菜の苗を植えました。毎年恒例ですが、たくさんの苗を植えています。
さて、里山だよりも1か月近く空いたので、周りの景色もずいぶん変わっています。連休初日には畑に夏野菜の苗を植えました。毎年恒例ですが、たくさんの苗を植えています。コロたん(ミニメロン)2株、ピーマン2株、ナス2種類6株、おひさまコーン40個(種まき)、トマト(ホーム桃太郎)6株、ミニトマト4株、大玉スイカ4株、ゴーヤー6株と種まき、安納いも20本、べにはるか(さつまいも)50本、きゅうり(夏さんご)4株と種まき、ししとう2株、万願寺とうがらし2株、大しょうが20個、ネットメロン3株、その他キャベツやレタス、ブロッコリーなどです。今月の終わりごろには玉ねぎも収穫できそうです。
一方、「jagar's garden」も次から次へと花が咲き、主役が交代していきました。チューリップなどがきれいだったころはこんな感じ。
2016.04.06
「時は過ぎ」
このホームページを管理していただいている人に聞くと、毎日純粋に(一人の人が一日のうちに何回見たとしても、あるいは何ページ見たとしてもそれは一人としてカウントすると)約130人ぐらいの人にこのホームページを見ていただいているようです。
よく「うちはアクセス数が1000あります」とか「カウント数が1500くらいあります」とか言う人がいますが、あれは正確な訪問者数を表した数ではありません。一人の人が一日のうちに3回見れば3と数えますし、さらにその人が1回見た時に10ページ見れば10とカウントします。ですから一人の人で30〜40なんていうカウント数にもなってしまうこともあるのです。(いわゆるページビューと呼ばれるものです。)
話は脱線しましたが、純粋な訪問者のうち10〜20人ぐらいは当工房のお客様だとして(もっとかも?)、100人以上の未知のお客様にも毎日このホームページを見ていただいていることになります。いずれのお客様も大変ありがたいことです。中にはこの里山だよりを楽しみにしておられる方もいるかも(いないかも?)しれません。できるだけ更新をしようと思っていますが、なかなか…前回の更新から10日以上過ぎてしまいました。

 10日も間を空けると季節はどんどん移り変わってしまいます。
10日も間を空けると季節はどんどん移り変わってしまいます。
「jagar's garden」はずいぶん花が咲いて華やかになって来ました。チューリップもあちらこちらに咲きはじめました。
よく「うちはアクセス数が1000あります」とか「カウント数が1500くらいあります」とか言う人がいますが、あれは正確な訪問者数を表した数ではありません。一人の人が一日のうちに3回見れば3と数えますし、さらにその人が1回見た時に10ページ見れば10とカウントします。ですから一人の人で30〜40なんていうカウント数にもなってしまうこともあるのです。(いわゆるページビューと呼ばれるものです。)
話は脱線しましたが、純粋な訪問者のうち10〜20人ぐらいは当工房のお客様だとして(もっとかも?)、100人以上の未知のお客様にも毎日このホームページを見ていただいていることになります。いずれのお客様も大変ありがたいことです。中にはこの里山だよりを楽しみにしておられる方もいるかも(いないかも?)しれません。できるだけ更新をしようと思っていますが、なかなか…前回の更新から10日以上過ぎてしまいました。

 10日も間を空けると季節はどんどん移り変わってしまいます。
10日も間を空けると季節はどんどん移り変わってしまいます。「jagar's garden」はずいぶん花が咲いて華やかになって来ました。チューリップもあちらこちらに咲きはじめました。

 アネモネはまっすぐに天を向いて咲きますので、真上から写真を撮らなくてはなりませんが、クリスマスローズは逆に下を向いて咲きますので、「どうぞ上を向いてください」とお願いして地面に寝そべって写真を撮らなければなりません。
アネモネはまっすぐに天を向いて咲きますので、真上から写真を撮らなくてはなりませんが、クリスマスローズは逆に下を向いて咲きますので、「どうぞ上を向いてください」とお願いして地面に寝そべって写真を撮らなければなりません。
 畑ではジャガイモの芽が出揃い、少し大きくなって来ました。このタイミングでまず芽かきをします。余分な芽を抜き取って一株に2本ぐらいにします。もったいないように見えますが、こうすることで元気な株が育ち、良質で型の良いジャガイモが出来るのです。
畑ではジャガイモの芽が出揃い、少し大きくなって来ました。このタイミングでまず芽かきをします。余分な芽を抜き取って一株に2本ぐらいにします。もったいないように見えますが、こうすることで元気な株が育ち、良質で型の良いジャガイモが出来るのです。
2016.03.24
「見るたび変わる」
2016.03.18
「暖かくなりました」

 一昨日、久しぶりに畑仕事をしました。冬野菜をお終いにしてきれいに耕しておきました。
一昨日、久しぶりに畑仕事をしました。冬野菜をお終いにしてきれいに耕しておきました。来るべき時のために堆肥と石灰をまいて、土に混ぜておきます。少し動いただけで汗が出るほどの暖かさでした。
 今はナバナが旬です。これがすごく甘くておいしいです。しかし、あまりに多すぎて食べ切れません。放っておくとすぐに菜の花になってしまいます。
今はナバナが旬です。これがすごく甘くておいしいです。しかし、あまりに多すぎて食べ切れません。放っておくとすぐに菜の花になってしまいます。

 さて、工房ではM様の胡桃(クルミ)のダイニングセットのベンチ2脚が完成となります。今日から塗装に入ります。
さて、工房ではM様の胡桃(クルミ)のダイニングセットのベンチ2脚が完成となります。今日から塗装に入ります。そしてまた今日から一宮市のT様の栃(トチ)のベンチの制作に入ります。
それが終わると浜松市のT様のご注文…壁面全体を埋める家具の制作に入ります。幅4m、天井高2m40cmという壁全体を覆うように食器棚、収納棚、テレビ台を制作していきます。すべて楢(ナラ)材で制作します。楢(ナラ)材は重いので大変です。しかも超大型家具ですし、一人なので大変です。気合を入れてがんばらないといけません。
その後、一宮市のT様の座卓、加茂郡のT様の椅子5脚とスツール、そして愛西市のK様の栃(トチ)無垢一枚板ダイニングテーブル…と続いていきます。相変わらず仕事、仕事の日々が続きます。ですから、唯一の息抜きはやはり庭仕事、畑仕事と言うわけです。
2016.03.11
「てくてくめぐりでの嬉しい出来事」
今日は3月11日です。この日の事については以前の里山だよりにも書いてあります。それから5年、こうして日々忙しく仕事をさせていただいていることに感謝したいと思います。

 庭のあちこちに球根植物の芽がずくずくと(にょきにょきと?)出ています。エゴノキの根元に植えたクリスマスローズにも花が咲きました。やったね!
庭のあちこちに球根植物の芽がずくずくと(にょきにょきと?)出ています。エゴノキの根元に植えたクリスマスローズにも花が咲きました。やったね!

 庭のあちこちに球根植物の芽がずくずくと(にょきにょきと?)出ています。エゴノキの根元に植えたクリスマスローズにも花が咲きました。やったね!
庭のあちこちに球根植物の芽がずくずくと(にょきにょきと?)出ています。エゴノキの根元に植えたクリスマスローズにも花が咲きました。やったね!
さて、明日、明後日も「いなか舎てくてくめぐり」が行われます。先週の土、日も大勢の方がいらっしゃいました。その中で特にうれしかったのが2組のお客様です。一組は岐阜市からみえたと言う小学生の女の子とそのおばあちゃんです。きっとお母さん(お父さん?)の実家に来たついでに、おばあちゃんとこの「てくてくめぐり」にいらっしゃったのだと思います。
その女の子が興味深く木で作られた小物を見てくれていました。その様子を見ておばあちゃんが「欲しい?」と聞かれると、その女の子は「一輪挿しが欲しいの」と答えました。それで私は「まだあるよ」と奥にしまってあった一輪挿しの残りもすべて出してあげました。結局山桜でできた一輪挿しを買って行ってくれました。その時のいとおしそうに一輪挿しをなでなでしていた様子が心に残りました。なんだかとてもうれしかったです。
もう一組は町内の小学生の女の子3人組です。私は初めは「たいていスタンプラリーが目的だろうな」と思っていたのですが、スタンプを押すのではなく、本当に興味深く展示してある家具や小物を見てくれていました。子どもたちがそんな風に見てくれるのは珍しく、とてもうれしくて思わずいろいろ細かく説明していました。(こどもには難しいことだったかも知れませんが、ついつい説明してしまいました。)
この催しにいらっしゃる方々は、いろんなギャラリーめぐりのついでにみえる方がほとんどです。ですから無垢の木の家具、木工品が好きで見に来たという方ばかりではありません。いやむしろそういう人は少ないです。皆さん「木はいいね」「暖かい感じだね」などおっしゃっていただきますが、普段当工房にお出でになるお客様とは明らかに違いはあります。
ですが、子どもは違います。子供はおべんちゃら、お上手は言いません。(語弊があったらごめんなさい。もちろん中には本当に心から「いいなぁ」と思ってくださった方もいらっしゃることは重々承知の上です。)子どもを見ていると純粋な感情が伝わってきます。あの2組のお客様の子供さんたちからは言葉では無いうれしいメッセージが私に伝わって来ました。

 さて、工房で制作していた「極上杢マカバ無垢一枚板テーブル」は塗装も終わり、完成しました。
さて、工房で制作していた「極上杢マカバ無垢一枚板テーブル」は塗装も終わり、完成しました。
ひとまず組み立てて、納品のときを待っています。私も納品でお客様に見てもらうのを楽しみにしています。
その女の子が興味深く木で作られた小物を見てくれていました。その様子を見ておばあちゃんが「欲しい?」と聞かれると、その女の子は「一輪挿しが欲しいの」と答えました。それで私は「まだあるよ」と奥にしまってあった一輪挿しの残りもすべて出してあげました。結局山桜でできた一輪挿しを買って行ってくれました。その時のいとおしそうに一輪挿しをなでなでしていた様子が心に残りました。なんだかとてもうれしかったです。
もう一組は町内の小学生の女の子3人組です。私は初めは「たいていスタンプラリーが目的だろうな」と思っていたのですが、スタンプを押すのではなく、本当に興味深く展示してある家具や小物を見てくれていました。子どもたちがそんな風に見てくれるのは珍しく、とてもうれしくて思わずいろいろ細かく説明していました。(こどもには難しいことだったかも知れませんが、ついつい説明してしまいました。)
この催しにいらっしゃる方々は、いろんなギャラリーめぐりのついでにみえる方がほとんどです。ですから無垢の木の家具、木工品が好きで見に来たという方ばかりではありません。いやむしろそういう人は少ないです。皆さん「木はいいね」「暖かい感じだね」などおっしゃっていただきますが、普段当工房にお出でになるお客様とは明らかに違いはあります。
ですが、子どもは違います。子供はおべんちゃら、お上手は言いません。(語弊があったらごめんなさい。もちろん中には本当に心から「いいなぁ」と思ってくださった方もいらっしゃることは重々承知の上です。)子どもを見ていると純粋な感情が伝わってきます。あの2組のお客様の子供さんたちからは言葉では無いうれしいメッセージが私に伝わって来ました。

 さて、工房で制作していた「極上杢マカバ無垢一枚板テーブル」は塗装も終わり、完成しました。
さて、工房で制作していた「極上杢マカバ無垢一枚板テーブル」は塗装も終わり、完成しました。ひとまず組み立てて、納品のときを待っています。私も納品でお客様に見てもらうのを楽しみにしています。
残りのアイテムである「無垢一枚板板脚ベンチ」2脚を制作中です。これが完成したら一緒に納品となります。こちらもいい感じに出来上がったので、お客様にお見せするのが楽しみです。
2016.03.07
「いなか舎てくてくめぐり」

 当工房は、5、6日と12、13日の4日間のみ参加します。展示はもちろん「無垢の木の家具、木工品」です。
当工房は、5、6日と12、13日の4日間のみ参加します。展示はもちろん「無垢の木の家具、木工品」です。即売用として作った一輪挿し、箸置き、iPhoneスタンド(スピーカ)なども並んでいます。春の日の一日、のんびりと里山をめぐって回ってみてはいかがでしょうか。

 さて、工房では「マカバ一枚板テーブル」の方が塗装に入りました。
さて、工房では「マカバ一枚板テーブル」の方が塗装に入りました。オイル、ワックスを何度も塗り重ねていきます。素晴らしい極上の杢が浮かび上がっています。この瞬間を楽しめるのは制作者だけですから、役得ですね。
 よく「自分でオイルを塗りませんか?」と言って、お客様に体験をしてもらうことをやっているところもあります。体験自体はいいことだと思いますし、やってみたいと思うのですが、オイル塗装もやはりきれいに仕上げようと思えばそれなりに技術や経験を要するものです。コツというものもありますから。
よく「自分でオイルを塗りませんか?」と言って、お客様に体験をしてもらうことをやっているところもあります。体験自体はいいことだと思いますし、やってみたいと思うのですが、オイル塗装もやはりきれいに仕上げようと思えばそれなりに技術や経験を要するものです。コツというものもありますから。お客様にも是非この感動を味わってもらいたいと思いつつも、そういうこともあるのでなかなか出来ないわけです。

 「胡桃(クルミ)3枚接ぎダイニングテーブル」の方は吸い付き桟加工をし、天板裏側の加工を終わりました。
「胡桃(クルミ)3枚接ぎダイニングテーブル」の方は吸い付き桟加工をし、天板裏側の加工を終わりました。
2016.02.29
「労働」
 先週の火曜日、ジャガイモの植え付けをしました。今年も男爵芋の種芋を約160個植え、一列余分に列が余ったのでキタアカリという種類を20個ほど植えてみました。毎年恒例の一大仕事です。さあ、いよいよ畑の季節が始まります。
先週の火曜日、ジャガイモの植え付けをしました。今年も男爵芋の種芋を約160個植え、一列余分に列が余ったのでキタアカリという種類を20個ほど植えてみました。毎年恒例の一大仕事です。さあ、いよいよ畑の季節が始まります。

 「マカバ一枚板テーブル」のほうは順調に着々と出来上がっています。寄せ蟻加工を施した蟻桟のほうもこんな感じに出来上がりました。
「マカバ一枚板テーブル」のほうは順調に着々と出来上がっています。寄せ蟻加工を施した蟻桟のほうもこんな感じに出来上がりました。
 試しに叩き込んでみました。嵌め合いも完璧!緩くなく、ちょっときついぐらいのちょうどいい感じに仕上がりました。
試しに叩き込んでみました。嵌め合いも完璧!緩くなく、ちょっときついぐらいのちょうどいい感じに仕上がりました。今回は都会のおしゃれなマンションに置かれるので、脚は非常にシンプルにしかもごつくないように少し細めの4本脚です。幕板は目立たないようにデザインもしてあります。しかし、マカバの一枚板はすごく重く(二人で持っても相当重い!)、それに耐えられるようにするにはこの嵌め合いは大変重要です。上手くいって良かったです。
そしていよいよ表側の仕上げです。大、中、小様々な鉋を使ってきれいに削り上げます。こういう杢が出た板は「交錯木理」と言って木目が互い違いに入り組んでいるので下手に削ると逆目(さかめ)を起こしてしまい、ざらざらした感じが残ってしまいます。何度も鉋の刃を研いで丁寧に削っていきます。

 「隠し雇い実接ぎ」の加工をし、接ぎ合わせをしました。
「隠し雇い実接ぎ」の加工をし、接ぎ合わせをしました。
 その後、所定の長さにカットしてから裏面を一度仕上げます。この後で「吸い付き桟」加工に入って行きます。
その後、所定の長さにカットしてから裏面を一度仕上げます。この後で「吸い付き桟」加工に入って行きます。
2016.02.23
「もうすぐ春」
「jagar's garden」のあちらこちらにチューリップの芽が顔を出し始めました。アネモネもシャクヤクも芽を出しています。
 昨年の11月ごろに大量にピット苗を買って、あちらこちらに植えておいたデルフィニウムですが、いつの間にか寒さにやられて融けて無くなっていたように見えていました。今年のガーデンのメインになるはずだったのに…とショックを受けていました。
昨年の11月ごろに大量にピット苗を買って、あちらこちらに植えておいたデルフィニウムですが、いつの間にか寒さにやられて融けて無くなっていたように見えていました。今年のガーデンのメインになるはずだったのに…とショックを受けていました。ところがなんと新しい芽を出しているではありませんか。植物はすごい!これでまた楽しみに待つことが出来ます。
2016.02.15
「その後の顛末」

 一昨日の土曜日、小雨が降る中でしたがピザ会の解禁ということで、いつものメンバーが集まり本年度初めてのピザ会を敢行しました。久しぶりだったのでピザもパンも、バーベキューもおいしかったです。
一昨日の土曜日、小雨が降る中でしたがピザ会の解禁ということで、いつものメンバーが集まり本年度初めてのピザ会を敢行しました。久しぶりだったのでピザもパンも、バーベキューもおいしかったです。その後はみんなですぐ近くにある造り酒屋「松井屋酒造場」へ行き、蔵開きのお酒を頂いて来ました。この時にしか飲めない貴重なお酒です。おいしいと評判でした。みなさんたくさんお土産のお酒を買って行かれました。
ところで前にも書きましたが、このイベントに合わせて小物を作りました。スマートフォンスタンド(スピーカー)です。このイベントで来られるお客様は木の家具、木工品に興味がある方ばかりじゃないので(むしろ大半がそういう人)、初めの頃は基本的には即売は無しということにしていました。しかし毎年大勢の方に来ていただくので、お土産になるものを用意しなければいけないなと思い、昨年から即売用の小物を作って置く事にしたのです。ですから、安いことが絶対条件。さすがにワンコインというわけにはいきませんが…。

 で、前に書いたように家族の意見で、このスマホスタンド(スピーカー)に消しゴムはんこで花やら猫の脚やらのはんこを作って押してみました。
で、前に書いたように家族の意見で、このスマホスタンド(スピーカー)に消しゴムはんこで花やら猫の脚やらのはんこを作って押してみました。まあ、こういうのもいいんじゃないでしょうか?何より、家族でああだこうだ言いながら楽しんで作れるのがいいですね。
ところで、作ってみた後で気になったので、「実際に市販されているものはどんなものだろう?」「どんな音がするのだろう?」と、大きな雑貨屋さんに行って見て来ました。(そもそもこういうものを売っている所があまり無いということも分かりました。)
例えば、竹を切って作ったものもありました。でも、結構高い値段がついているわりにそれほどいい音が出るわけでもありませんでした。内部に電子機器を付けたものもありました。こちらは確かに音量は大きくなりますが、音質は今一と感じました。価格は高いし…そう思うと、私の作ったこのスマホスタンドは安い割りに良いんじゃないでしょうか?(自画自賛)
例えば、竹を切って作ったものもありました。でも、結構高い値段がついているわりにそれほどいい音が出るわけでもありませんでした。内部に電子機器を付けたものもありました。こちらは確かに音量は大きくなりますが、音質は今一と感じました。価格は高いし…そう思うと、私の作ったこのスマホスタンドは安い割りに良いんじゃないでしょうか?(自画自賛)
さて、胡桃(クルミ)のサイドボードはいよいよ最終局面に入りました。扉の制作です。京都の布問屋から仕入れた布を板に止め、組み立てていきます。
2016.02.09
「感覚」
 工房の中は薪ストーブで暖を取れますが、最近よく活躍しているのはオガクズストーブのほうです。最近薪ストーブが人気ですが、燃料となる薪の調達は意外と大変ではないでしょうか。買うと高いし、丸太で仕入れて切って割るのも大変です。それに比べると我が工房は、日ごろ出る端材をストックしてあるので結構な量があります。
工房の中は薪ストーブで暖を取れますが、最近よく活躍しているのはオガクズストーブのほうです。最近薪ストーブが人気ですが、燃料となる薪の調達は意外と大変ではないでしょうか。買うと高いし、丸太で仕入れて切って割るのも大変です。それに比べると我が工房は、日ごろ出る端材をストックしてあるので結構な量があります。
 しかしそれでも、一冬毎日薪ストーブを焚き続けるにはちょっと足りません。ピザパーティーに使う分もとっておかなければなりませんし…そこでオガクズストーブが重宝するというわけです。オガクズは1〜2ヶ月に一度軽トラ一杯に積んで産廃に出すほどあるわけですから、無くなる事はありません。
しかしそれでも、一冬毎日薪ストーブを焚き続けるにはちょっと足りません。ピザパーティーに使う分もとっておかなければなりませんし…そこでオガクズストーブが重宝するというわけです。オガクズは1〜2ヶ月に一度軽トラ一杯に積んで産廃に出すほどあるわけですから、無くなる事はありません。
ところで制作中のサイドボードの方ですが、扉の裏板や棚板など板を接ぎ合わせる仕事があります。この板接ぎは少しコツが要ります。かつて木工所での修行中に大失敗をした経験があるので、その失敗から学び上手にはなりました。
簡単に言うと…接ぎ合わせる面をただまっすぐに削るのではなく、中凹になるように削るのです。手押し鉋という機械でまっすぐに削っておいてから、手鉋で中央を少しだけ削るというやり方もあります(よく木工雑誌などを見るとどこかの木工家がいかにもという感じでそう教えています)が、薄い板になればなるほどそれは難しくなります。
簡単に言うと…接ぎ合わせる面をただまっすぐに削るのではなく、中凹になるように削るのです。手押し鉋という機械でまっすぐに削っておいてから、手鉋で中央を少しだけ削るというやり方もあります(よく木工雑誌などを見るとどこかの木工家がいかにもという感じでそう教えています)が、薄い板になればなるほどそれは難しくなります。
 で、どうするかというと、実は手押し鉋盤を微妙に調整すればそんな風に削れるのです。これは木工所にいる時に工場長が教えてくれました。正確に言うとやり方を教えてくれたのではなく、そういうやり方があるよと言ってくれただけです。(現場というものは往々にしてそういうものです。丁寧に教えてくれたりなどしません。「盗め」「自分で見つけろ」ということでしょうか。)
で、どうするかというと、実は手押し鉋盤を微妙に調整すればそんな風に削れるのです。これは木工所にいる時に工場長が教えてくれました。正確に言うとやり方を教えてくれたのではなく、そういうやり方があるよと言ってくれただけです。(現場というものは往々にしてそういうものです。丁寧に教えてくれたりなどしません。「盗め」「自分で見つけろ」ということでしょうか。)それから独学で試行錯誤の末に身に付けました。
2016.02.02
「どツボにはまった!」

 来月(3月)の5日から毎年恒例の「いなか舎てくてくめぐり」(町内ギャラリーめぐり)というイベントが始まります。
来月(3月)の5日から毎年恒例の「いなか舎てくてくめぐり」(町内ギャラリーめぐり)というイベントが始まります。当工房も毎年参加していますが、昨年から小物を即売することにし、即売用の小物をこれに合わせて作っています。昨年は「箸置き」と「一輪挿し」を作りました。今年も何か新しいものを作らなくてはと思っていましたので、急遽作ることにしました。
この仕事は私にとってはある意味で良い機会になります。

 一つは、工房の中にも外にもたまりにたまった端材を利用できるという意味で良いチャンスです。元来「もったいない」性分で捨てることが出来ず、薪にしてしまうのももったいない気がして、たまる一方でしたからちょうど良い機会です。
一つは、工房の中にも外にもたまりにたまった端材を利用できるという意味で良いチャンスです。元来「もったいない」性分で捨てることが出来ず、薪にしてしまうのももったいない気がして、たまる一方でしたからちょうど良い機会です。もう一つは、普段は大物家具を制作するのがほとんどで、小物についてはどうしても商品開発が出来ずにいるわけですが、この機会に小物のラインアップが一つずつ増えていくということで、これもちょうど良いというわけです。
そういうわけで、今制作中の胡桃(クルミ)のサイドボードはしばし作業を停止し、小物の制作にかかりました。しばし停止といっても2、3日で出来るだろうと思っていました。ところが…考えが甘かったです。やりはじめたら、「もうちょっとここをこうしよう」と次々と修正点が出てきて、何度もやり直しを繰り返す羽目になりました。結局、今日で4日かかっています。
2016.01.29
「久しぶりのご対面」
本日は座卓をご注文頂いたお客様の家に行き、現場を見ながらのお打ち合わせをして来ました。このお客様は7年ほど前にダイニングテーブルをご注文いただき、この春またベンチのご注文を頂いており、そしてまた座卓のご注文というリピートのお客様です。

 そのダイニングテーブルと7年ぶりの対面をしましたが、すごくきれいに使っていただいており、全く汚れていないのにびっくりするとともに感動致しました。
そのダイニングテーブルと7年ぶりの対面をしましたが、すごくきれいに使っていただいており、全く汚れていないのにびっくりするとともに感動致しました。
そして何よりも7年という時がその風合いを素晴らしく深く変化させていたことにも感動しました。聞くとやはりこまめにメンテナンスオイルを使ってメンテナンスしているとのことでした。こうして愛着を持って使っていただけることが私どもにとっては何よりの喜びとなります。
ちなみ最近お納めした息子様宅のダイニングセットを含めると、今度の座卓までたくさんの再注文を頂くことになります。奥様いわく「正直言っていろんな家具屋さんを見てまわりましたが、佐藤さんの家具の何とも言えない温かみは他のものとは全然違います。他の家具屋さんで欲しいなあと思えるものはなかったです」というありがたいお言葉を頂き、すごくうれしく励みになりました。
さて工房で制作中の「胡桃(クルミ)のサイドボード」は引き出しまで完成し、扉の制作に入っています。

 そのダイニングテーブルと7年ぶりの対面をしましたが、すごくきれいに使っていただいており、全く汚れていないのにびっくりするとともに感動致しました。
そのダイニングテーブルと7年ぶりの対面をしましたが、すごくきれいに使っていただいており、全く汚れていないのにびっくりするとともに感動致しました。そして何よりも7年という時がその風合いを素晴らしく深く変化させていたことにも感動しました。聞くとやはりこまめにメンテナンスオイルを使ってメンテナンスしているとのことでした。こうして愛着を持って使っていただけることが私どもにとっては何よりの喜びとなります。
ちなみ最近お納めした息子様宅のダイニングセットを含めると、今度の座卓までたくさんの再注文を頂くことになります。奥様いわく「正直言っていろんな家具屋さんを見てまわりましたが、佐藤さんの家具の何とも言えない温かみは他のものとは全然違います。他の家具屋さんで欲しいなあと思えるものはなかったです」というありがたいお言葉を頂き、すごくうれしく励みになりました。
さて工房で制作中の「胡桃(クルミ)のサイドボード」は引き出しまで完成し、扉の制作に入っています。
鉋を掛けて仕上げ、ぴたっと納まるまで仕込みを繰り返します。
 つまみを取り付け、裏側にストッパーを取り付けて引き出し部分の完成です。(※詳しいことは「木になる話」にも書いてありますのでご覧ください。)
つまみを取り付け、裏側にストッパーを取り付けて引き出し部分の完成です。(※詳しいことは「木になる話」にも書いてありますのでご覧ください。)このサイドボードには見せ場がいくつもありますが、この引き出し部もその一つです。また、これから作っていく扉も見せ所の一つです。いくつもの峠を越えて完成に少しづつ近づいていくのです。
2016.01.25
「サイドボード、引き続き本体組み立てまで」
 今年初めて作った「べにはるか」という種類のサツマイモは大正解でした。すごく甘くて収量も多く、形もいいです。サツマイモは普通の場合、採ってからすぐはあまり甘くなく、少しおいておくと甘くなるものですが、このべにはるかは比較的すぐに食べても甘いのがいいところでもあります。
今年初めて作った「べにはるか」という種類のサツマイモは大正解でした。すごく甘くて収量も多く、形もいいです。サツマイモは普通の場合、採ってからすぐはあまり甘くなく、少しおいておくと甘くなるものですが、このべにはるかは比較的すぐに食べても甘いのがいいところでもあります。
 さて、工房では胡桃(クルミ)のサイドボードの制作が順調に続いています。本体内部の部材制作になります。
さて、工房では胡桃(クルミ)のサイドボードの制作が順調に続いています。本体内部の部材制作になります。方立(ほうたて)に蟻加工をしたり、裏板の溝や扉の溝(我々は溝とは言わず「小穴」と言いますが)をついたり、引き出しの桟の部材を作ったりします。
 ここから内部の造作に入って行きます。引き出しは小さいけど6杯あります。またまた蟻組み(天秤差し)の作業が待っています。すでにその作業に入っていますが、それはまたこの次…。
ここから内部の造作に入って行きます。引き出しは小さいけど6杯あります。またまた蟻組み(天秤差し)の作業が待っています。すでにその作業に入っていますが、それはまたこの次…。箱物はとにかく工程が多く複雑です。根気あるのみです。その点だけは私は自信があります。少しづつですがパズルが組みあがるように形になっていく箱物制作は結構楽しいものですよ。
2016.01.14
「留形隠し蟻組み接ぎ」

 そして天板と側板、地板の加工に入ります。手押し鉋という機械に入らない広い板の場合は、電動鉋を使って平面出しをします。
そして天板と側板、地板の加工に入ります。手押し鉋という機械に入らない広い板の場合は、電動鉋を使って平面出しをします。水平に削れているかどうか、まっすぐに削った木を当てて見ます。目視で水平かどうか判断するので、ここは勘に頼って作業します。
さて、いよいよここからこのサイドボードの目玉の一つである「留形隠し蟻組み接ぎ」の加工に入って行きます。長さが165cm、幅が45cmという大きな板をこの仕口で組みます。もちろんここから完全な手加工です。
 まずは墨付けです。こういった加工は墨付けの精度が非常に重要です。いくら切ったり彫ったりの技術があったとしても墨自体が違っていてはどうしようもないですから。
まずは墨付けです。こういった加工は墨付けの精度が非常に重要です。いくら切ったり彫ったりの技術があったとしても墨自体が違っていてはどうしようもないですから。
 まずは墨付けです。こういった加工は墨付けの精度が非常に重要です。いくら切ったり彫ったりの技術があったとしても墨自体が違っていてはどうしようもないですから。
まずは墨付けです。こういった加工は墨付けの精度が非常に重要です。いくら切ったり彫ったりの技術があったとしても墨自体が違っていてはどうしようもないですから。
 次はノミ作業です。いろんな大きさ、形のノミを使って慎重に彫っていきます。
次はノミ作業です。いろんな大きさ、形のノミを使って慎重に彫っていきます。この作業がここから延々と何時間も続きます。板の上に座り込んで腰をかがめ、ひねったような姿勢でずっと続けるので、かなり腰も首も痛くなります。
次に留の部分をノミや際鉋(きわがんな)という道具で削ります。ときどき45度になっているかを確認しながら進めます。
2016.01.06
「年末から新年にかけて」
2016年も始まりました。昨年12月からずっとそうですが、毎日1月とは思えない陽気が続いています。
工房周りの様子もまるで春先のようです。木々は芽を膨らませ、スイセンの花も咲いていたり、畑のイチゴは花をつけたり、実をならせていたり…エンドウもすっかり大きくなっていたりして、これはもう3月ぐらいの風景です。この先冬らしい寒さはやってくるのでしょうか?やはり冬は寒くないといけないんですがね…。
工房周りの様子もまるで春先のようです。木々は芽を膨らませ、スイセンの花も咲いていたり、畑のイチゴは花をつけたり、実をならせていたり…エンドウもすっかり大きくなっていたりして、これはもう3月ぐらいの風景です。この先冬らしい寒さはやってくるのでしょうか?やはり冬は寒くないといけないんですがね…。
さて、我が家の年末年始は毎年やることは同じです。以前の里山だより(2010年1月4日と2015年1月5日)にも書いたのでそちらもご覧ください。
まずは年賀状。お客様・仕事用と友人・親戚用の2パターンを作ります。次に、お墓へ行ってお墓掃除をし、花などをお供えしてきます。田舎の墓は大きいので結構大変です。うちの場合は墓石が5つと地蔵様があります。花筒も11個あるのでお花を用意するのも大変です。
そして、28日はお餅つきと決まっています。二升を2杯分ついて、鏡餅7飾り分を作り、あんころ餅・黄な粉餅、そして残りは伸し餅にして次の日に包丁で四角く切ります。

 29日には本年最後の納品に行って来ました。想像以上だと喜んでいただいてほっとしました。
29日には本年最後の納品に行って来ました。想像以上だと喜んでいただいてほっとしました。
まずは年賀状。お客様・仕事用と友人・親戚用の2パターンを作ります。次に、お墓へ行ってお墓掃除をし、花などをお供えしてきます。田舎の墓は大きいので結構大変です。うちの場合は墓石が5つと地蔵様があります。花筒も11個あるのでお花を用意するのも大変です。
そして、28日はお餅つきと決まっています。二升を2杯分ついて、鏡餅7飾り分を作り、あんころ餅・黄な粉餅、そして残りは伸し餅にして次の日に包丁で四角く切ります。

 29日には本年最後の納品に行って来ました。想像以上だと喜んでいただいてほっとしました。
29日には本年最後の納品に行って来ました。想像以上だと喜んでいただいてほっとしました。
 今年は30日、31日の2日間に大掃除をしました。母屋と離れ、そして工房と3軒分あり、それを妻と2人だけでやるのですから大変です。娘は海外旅行に行ってしまい、息子は相変わらずインドネシアで年越しをしているので…。
今年は30日、31日の2日間に大掃除をしました。母屋と離れ、そして工房と3軒分あり、それを妻と2人だけでやるのですから大変です。娘は海外旅行に行ってしまい、息子は相変わらずインドネシアで年越しをしているので…。ガラス拭きだけでも、数えてみたら46枚ほどありました。(工房のガラス拭きまではできませんでした。)最後は力尽きて、工房は大掃除ならぬ小掃除とお茶を濁した感じになってしまいました。
31日には山へ松の葉を取りに行き、鏡餅を添えてお飾りを作ります。そして愛車の洗車もします。そんなこんなで年末は忙しく過ぎていきました。
大晦日の夜は、夕ご飯前に仏壇前にてお経をあげてお参りします。そして妻が作ってくれた年越しのご馳走を食べて、紅白歌合戦を楽しみます。紅白歌合戦が終わると近くの神社へ初詣に行き、年越しをします。真夜中の静寂の初詣はなかなか厳かでいいものです。
新年1日はゆっくり寝ているわけには行きません。朝一でお寺へあいさつに伺います。お米と「お年玉(おねんぎょく)」を持って行きます。我が町内の人は皆、自分の檀那寺と町内にあるお寺(龍福寺)の2寺にあいさつに行くのが恒例となっています。
 帰ってきてからお雑煮の朝ごはんを食べて、年賀状を見て楽しみます。今年は2日に初詣で名古屋にある熱田神宮へ行きました。これも恒例です。ここで毎年買って帰るのが「生年月日占い」です。これ、結構あっているんです。自分の性格とか向いた職業とか…「その通り!」と思うようなことが多いんです。
帰ってきてからお雑煮の朝ごはんを食べて、年賀状を見て楽しみます。今年は2日に初詣で名古屋にある熱田神宮へ行きました。これも恒例です。ここで毎年買って帰るのが「生年月日占い」です。これ、結構あっているんです。自分の性格とか向いた職業とか…「その通り!」と思うようなことが多いんです。
仕事始めは3日でした。結局昨年のうちに完成できなかった加茂郡のお客様の玄関衝立の続きです。オブジェのようなものなので、一応図面は作りますが途中で様子を見ながらあれこれ変更も加えつつ進めていきます。大体先が見えてきたので、あと少しで完成です。
2016.01.01
「年始のあいさつ」
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
昨年納品で奈良を訪れた時、法隆寺にも参ることができました。そしてまじまじとその建築物を見て思ったことがあります。古の人の建築技術の高さは言うまでもないことですが、そこかしこに職人としての矜持を感じさせるものがあったのです。今、当工房には親鸞聖人のご入滅のお寺と言われているお寺で使われていた建具が数点あります。(それを再生させるという仕事をしなければならないのですが。) それを見ても同じように職人の矜持を感じます。
ものづくりの職人の端くれとして、大事にしなければいけないと感じています。今年の仕事の中に少しでも反映させなければと思っています。

 さて今年の仕事始めはいきなり大きな山です。もう一度作ってみたくてなかなかその機会が無かった「胡桃サイドボード」と極上杢マカバ一枚板のダイニングテーブルです。
さて今年の仕事始めはいきなり大きな山です。もう一度作ってみたくてなかなかその機会が無かった「胡桃サイドボード」と極上杢マカバ一枚板のダイニングテーブルです。
良い一年の始まりになるようにがんばりたいと思います。
昨年納品で奈良を訪れた時、法隆寺にも参ることができました。そしてまじまじとその建築物を見て思ったことがあります。古の人の建築技術の高さは言うまでもないことですが、そこかしこに職人としての矜持を感じさせるものがあったのです。今、当工房には親鸞聖人のご入滅のお寺と言われているお寺で使われていた建具が数点あります。(それを再生させるという仕事をしなければならないのですが。) それを見ても同じように職人の矜持を感じます。
ものづくりの職人の端くれとして、大事にしなければいけないと感じています。今年の仕事の中に少しでも反映させなければと思っています。

 さて今年の仕事始めはいきなり大きな山です。もう一度作ってみたくてなかなかその機会が無かった「胡桃サイドボード」と極上杢マカバ一枚板のダイニングテーブルです。
さて今年の仕事始めはいきなり大きな山です。もう一度作ってみたくてなかなかその機会が無かった「胡桃サイドボード」と極上杢マカバ一枚板のダイニングテーブルです。良い一年の始まりになるようにがんばりたいと思います。