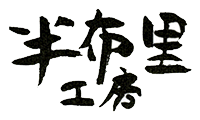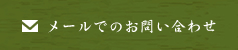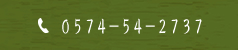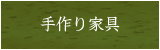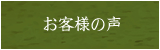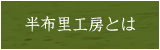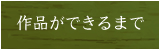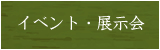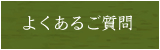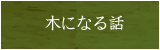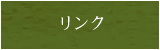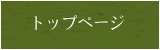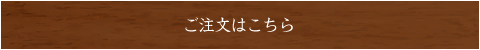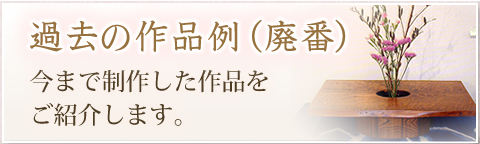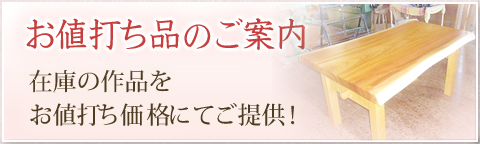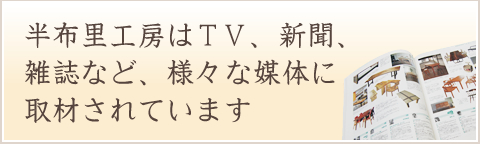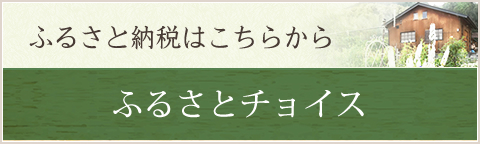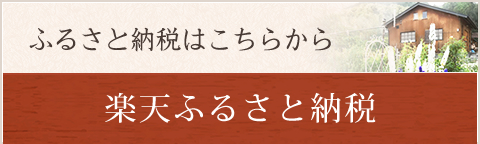- トップページ
- 里山便り2017
2017.12.26
「年末のあいさつ」
2017.12.22
「専門家に聞け」
なんだか最近スツールとちゃぶ台ばかり作っているような気がします。(うれしいことですけど。) でも一度にたくさん作ると言ってもそんなに多く作ることも大変なので、3個ぐらいづつになります。
 ところで、完成したものを運送屋さんを頼んで配送する場合、こういった小物は自分で段ボールで箱を作ります。大きな板段ボールを買ってきて、サイズを測ってカットします。
ところで、完成したものを運送屋さんを頼んで配送する場合、こういった小物は自分で段ボールで箱を作ります。大きな板段ボールを買ってきて、サイズを測ってカットします。それを折り曲げて箱にするのですが、段ボールというのは曲げやすい方向(筋が付いている方向)と曲げにくい方向とがあるのはご存じのとおりです。
この仕事に就く前は知らなかったのですが、こういうことをやるようになってから、ある日必要に迫られて段ボール屋さんに聞いたところいいことを教えてくれました。

 「10円玉で筋を付けてから曲げるといいよ。10円でなくても1円でも100円でもいいよ。(笑)」ということでした。
「10円玉で筋を付けてから曲げるといいよ。10円でなくても1円でも100円でもいいよ。(笑)」ということでした。それでやってみると、確かにきれいに曲がりました。やはり専門家に聞くのが一番ですね。知り合いの保育士や学校の先生にも教えてあげました。(学校なんかではよく段ボールで工作をしたりしますから。)
ふるさと納税の方は出来る限り今年中に発送したいと思っていますが、年が明けてからの制作・発送になるものもありますので、よろしくお願いいたします。
2017.12.14
「霜の花」
最近お気に入りの番組は「プレバト」です。必ずビデオに撮っておいて見ます。その中でも特に俳句が好きなのですが、本当にいつもあの先生には感心します。見るたびに日本語って本当に素晴らしい言葉だなと思い、その美しい日本語がだんだん廃れていくことを残念に思っています。あの先生には日本中の小中学校を回って、子どもたちに日本語の素晴らしさを教えて回ってほしいといつも思ったりします。
 ところでその俳句の季語に「霜の花」というのがありますが、今朝いつものように畑を見に行くと、野菜がすっかり霜に覆われて真っ白になっていました。
ところでその俳句の季語に「霜の花」というのがありますが、今朝いつものように畑を見に行くと、野菜がすっかり霜に覆われて真っ白になっていました。
しかし、その様があまりに美しかったので何枚も写真に撮っていました。白菜に付く霜の様子などはまさに花のようです。
 ところでその俳句の季語に「霜の花」というのがありますが、今朝いつものように畑を見に行くと、野菜がすっかり霜に覆われて真っ白になっていました。
ところでその俳句の季語に「霜の花」というのがありますが、今朝いつものように畑を見に行くと、野菜がすっかり霜に覆われて真っ白になっていました。しかし、その様があまりに美しかったので何枚も写真に撮っていました。白菜に付く霜の様子などはまさに花のようです。

 白菜も大根もカブも、またネギもすべてこうして霜が降りて凍みれば凍みるほどおいしく甘くなっていきます。
白菜も大根もカブも、またネギもすべてこうして霜が降りて凍みれば凍みるほどおいしく甘くなっていきます。そして、イチゴも玉ねぎもエンドウもこういう霜に耐えて強くしっかりとした苗になり、春になると一気に大きく育つのです。

 花も同じです。デルフィニウムなどは一度すっかり霜にやられてしまったかのように(枯れたように)なってしまいますが、そんなことは無く地面の下でしっかりと根を張り、強くなって春に復活してくれます。
花も同じです。デルフィニウムなどは一度すっかり霜にやられてしまったかのように(枯れたように)なってしまいますが、そんなことは無く地面の下でしっかりと根を張り、強くなって春に復活してくれます。ビオラもまた同じ。私たち人間もまたこうでありたいです。
ベニマツのペン立ては前回の里山だよりにもちょっと書きましたが、ナイフ1本での彫刻が見せ所です。その様子を今流行の「タイムラプス」動画で撮りましたのでご覧ください。決して難しいものではなく誰でもできますが、こういうやり方をしている人は私の知る限りでは意外にいません。
2017.12.05
「ふるさと納税」
 我が町富加町の「ふるさと納税」の返礼品として11月から「ちゃぶ台」「木馬」「おにぎりスツール」の3点を載せさせていただいていますが、おかげさまでぼつぼつとご注文をいただき、発送をさせて頂いています。現在も徐々に在庫がなくなってきているので、急いで制作に取り掛かっています。
我が町富加町の「ふるさと納税」の返礼品として11月から「ちゃぶ台」「木馬」「おにぎりスツール」の3点を載せさせていただいていますが、おかげさまでぼつぼつとご注文をいただき、発送をさせて頂いています。現在も徐々に在庫がなくなってきているので、急いで制作に取り掛かっています。ところで、このふるさと納税の商品は通常のご注文と違って私が直接お客様とやりとりをするものではなく、あくまでも町が窓口となって、町の方から私どもに発送の依頼を頂くということになっています。ですので私の方からは発送をするだけで、いつも「どんな人が買ってくださったんだろうなぁ」と想像しているだけです。
ところが先日次のようなメールが来ました。
福岡県在住の○○と申します。
本日、ふるさと納税の返礼品としておにぎりスツールを受け取りました。一言お礼を申し上げたく、メッセージを送らせていただきました。
写真以上に素敵なスツールで、座り心地も良く、とても気に入りました。長く大事に使って、愛用させていただきます。この度はありがとうございました。
本日、ふるさと納税の返礼品としておにぎりスツールを受け取りました。一言お礼を申し上げたく、メッセージを送らせていただきました。
写真以上に素敵なスツールで、座り心地も良く、とても気に入りました。長く大事に使って、愛用させていただきます。この度はありがとうございました。
感想を送って下さるとは思ってもいなかったことなので、とてもうれしかったです。そんなわけで、一品一品心を籠めて作ることの大切さを再確認させていただきました。
話は変わりますが、このところ友人、知人にプレゼントするものを作る必要があり、小物を作りました。

 一つは息子がタイでお世話になったホストファミリーにプレゼントするお盆です。我が家でも使っていますが、使いやすくて愛用しています。
一つは息子がタイでお世話になったホストファミリーにプレゼントするお盆です。我が家でも使っていますが、使いやすくて愛用しています。
 もう一つは、先日のピザ会の時に還暦祝いのポロシャツをプレゼントしていただいたメンバーの方々へのお礼です。いつも使えるものがいいだろうということで、ベニマツでペン立てを作りました。
もう一つは、先日のピザ会の時に還暦祝いのポロシャツをプレゼントしていただいたメンバーの方々へのお礼です。いつも使えるものがいいだろうということで、ベニマツでペン立てを作りました。なぜベニマツで作ったかというと、(もちろんベニマツという木がなかなか無い貴重な木だということもありますが)彫刻をしたかったからです。楽しみながら久しぶりにナイフ1本で彫刻をしました。側面にはしっかり「jagar's garden」と入れておきました。(底の裏側には半布里工房の焼き印も押しておきました。)
2017.11.07
「連休は…」
 10月下旬に雨や台風が続いたのでイチゴの苗の定植がなかなか出来ずやきもきいていましたが、先々週の間になんとか晴れ間をついてやってしまいました。
10月下旬に雨や台風が続いたのでイチゴの苗の定植がなかなか出来ずやきもきいていましたが、先々週の間になんとか晴れ間をついてやってしまいました。今年は苗が少ないかなと思っていましたが意外と良い苗がたくさん出来、結局は80本ほどの苗を植え付けすることができました。さらに余ったので10本ほどは鉢にも植えました。また知り合いで欲しい人にあげようかなと思っています。
 そんなに植えましたが、まだ苗が残っています。もったいないです。もう大きい苗は少ないですが、欲しい人があれば差し上げます。(うちのイチゴは「おおきみ」という種類で、大型の実がなります。その辺ではあまり売ってない種類です。)
そんなに植えましたが、まだ苗が残っています。もったいないです。もう大きい苗は少ないですが、欲しい人があれば差し上げます。(うちのイチゴは「おおきみ」という種類で、大型の実がなります。その辺ではあまり売ってない種類です。)
 気になっていたサツマイモの収穫も終わらせました。うちのは「べにはるか」という種類です。
気になっていたサツマイモの収穫も終わらせました。うちのは「べにはるか」という種類です。先日娘が言っていたのですが…どこかの幼稚園で園児にサツマイモ掘りをさせることにして家庭に連絡をしたところ(掘った芋を持ち帰るということらしいのですが)、ある親が「うちの子が掘った芋が小さかった場合どうしてくれるのですか?!」と電話をかけてきたとのこと…。
そこで、その幼稚園ではあらかじめ先生たちが芋を掘って、大きさを均等にしてビニール袋に入れたうえでもう一度土の中に埋めておいて、それを園児に掘らせたということでした。
あきれて言葉も出ません。子どもは「サツマイモって土の中にビニールに入って出来ているんだ!」って思うかも?親も親なら幼稚園も幼稚園…世も末です。どうしてそうなるのか?もしどうしても公平にしたかったら、園児に掘らせた後で一度みんな一所に集めて「こんなにたくさん取れたね!」などと言ってみんなで喜び、それから公平に分ければ済むことじゃないですか。それに仮に自分が掘った芋が小さくてそれを持ち帰ることになったとしても、別に悪いことじゃありません。そういう経験も必要です。
脱線しましたが、芋ほりって言うとなんか簡単そうに思われるかもしれませんがそうでもないのです。もちろんサツマイモ専門で作っている農家の土はそれ用にサラサラの土だから、もしかすると手で掘れてしまうかもしれませんが、この辺の土は(前にも書きましたが)石畑で土も硬いです。しかもサツマイモは結構あちこちに広がってできるので(思わぬところに出来ていたりする)、鍬などで掘った時に傷つけることも多いです。鍬とスコップで慎重に掘らないといけません。結構難しいです。
 さて今回は収穫かごに3箱分取れました。ビニールハウスの中に掘った保存用の穴に入れてモミガラをかぶせ、さらに要らなくなった毛布を掛けて保存しておくと、ずっと長い間とっておくことができます。
さて今回は収穫かごに3箱分取れました。ビニールハウスの中に掘った保存用の穴に入れてモミガラをかぶせ、さらに要らなくなった毛布を掛けて保存しておくと、ずっと長い間とっておくことができます。

 一方ほったらかしにしておいた庭も、この連休中に草を引いたりしてきれいにしました。
一方ほったらかしにしておいた庭も、この連休中に草を引いたりしてきれいにしました。そのあとで妻が作っていたビオラ、パンジーの苗を植えました。全部で300本ほどの苗が出来てしまったので、そこらじゅうにいっぱい植えました。庭中ビオラだらけです。
 さらにさらに…隣の第二農園の一部まで庭を拡張することにし、工事を始めてしまいました。ここは基本的には「バラ園」にするつもりです。(今のところはとりあえずほかの花の苗を植えてありますが…。)
さらにさらに…隣の第二農園の一部まで庭を拡張することにし、工事を始めてしまいました。ここは基本的には「バラ園」にするつもりです。(今のところはとりあえずほかの花の苗を植えてありますが…。)どんどん庭(jagar's garden)は広がっていきます。楽しみです。そんなわけで連休はほぼ庭と畑仕事で終わっていったのでした。
 さて仕事の方ですが、わが町「富加町」のふるさと納税の返礼品にいくつか商品を登録することになりました。登録されているのは「胡桃(クルミ)ちゃぶ台」「タモちゃぶ台」「木馬」「おにぎりスツール」の4点です。
さて仕事の方ですが、わが町「富加町」のふるさと納税の返礼品にいくつか商品を登録することになりました。登録されているのは「胡桃(クルミ)ちゃぶ台」「タモちゃぶ台」「木馬」「おにぎりスツール」の4点です。
2017.10.19
「私が畑や庭を作るのは…」
 そろそろイチゴの苗を本植えするために畝づくりをしたいのですが、ずっと雨続きなのでできません。台風が行ってしまってからになりそうです。
そろそろイチゴの苗を本植えするために畝づくりをしたいのですが、ずっと雨続きなのでできません。台風が行ってしまってからになりそうです。仮植え床では苗がしっかり根を張って今か今かと待っています。100本以上の苗を植えてありますが、そのうち大きく元気なものを選んで60本ほど植えることになりそうです。
ところで、私が庭や畑を作る理由は(ずっと以前にも書いたような気がしますが)次のようなわけです。
第1は何と言ってもやはり(野菜の場合)すごくおいしいということ。スーパーで買ってくるものとは全然味が違います。そりゃあ畑直送ですから新鮮でおいしいに決まってます。それにうちは無農薬ですから体にいい物ばかりです。いつでも旬のもの、すごくおいしい野菜を食べられる。これほどの幸せはありません。
第2に畑や庭からいろいろなことが学べるということ。畑も庭もどちらも同じく自然が相手ですから毎年同じではありません。いい年もあれば悪い年もあります。今までやってきた同じことが通用しないことだってあります。日々勉強です。それに結果が出るのに時間がかかります。何と言っても1年にチャンスは1回しかありません。今年だめならまた来年。気長な仕事です。
 庭もまた同じ。今年植えてみた花がその場所に合わなかったなんて言うことはしょっちゅうです。場所を変えてみたらうまくいったとか、逆にだめだったはずなのにどういうわけか4年目に成功したとか…本当にいろいろあるのです。結果が出るのに3年も4年もかかるのです。結果を急がないということもまた学ぶことができます。
庭もまた同じ。今年植えてみた花がその場所に合わなかったなんて言うことはしょっちゅうです。場所を変えてみたらうまくいったとか、逆にだめだったはずなのにどういうわけか4年目に成功したとか…本当にいろいろあるのです。結果が出るのに3年も4年もかかるのです。結果を急がないということもまた学ぶことができます。
また、あまりにも過保護に育ててもいけません。時には厳しく育てるとすごくおいしい野菜が出来たりもします。しかし、ものによってはすごく大事に育てないと死んでしまうという植物もあります。相手によって対応も様々に変えなければいけないのだということも学びます。ほかにもいろいろ、あげればきりがないです。
第3は教育の面から。この頃はよく「食育」なんて言う言葉でテレビでも本でもよく言われるようになりましたが、そんな大げさな言い方でなくても食は人間形成にとってとても大事なものに決まってます。よく子どもが野菜ぎらいだとか「トマトを食べない」「きゅうりを食べない」「ジャガイモを残す」…などと言います。それは簡単なことです。おいしいトマトなら、おいしいキュウリなら、おいしいジャガイモならそれは子どもも食べます。それに(ここが大事なポイント)「お父ちゃん」が作った野菜なら食べてみようかという気になりますって。
 私が畑を趣味にし始めて20数年。子どもたちは本当に小さい時から私の作った野菜を食べてきました。おかげさまでうちでは子どもたちもよく野菜を食べてきました。
私が畑を趣味にし始めて20数年。子どもたちは本当に小さい時から私の作った野菜を食べてきました。おかげさまでうちでは子どもたちもよく野菜を食べてきました。
第1は何と言ってもやはり(野菜の場合)すごくおいしいということ。スーパーで買ってくるものとは全然味が違います。そりゃあ畑直送ですから新鮮でおいしいに決まってます。それにうちは無農薬ですから体にいい物ばかりです。いつでも旬のもの、すごくおいしい野菜を食べられる。これほどの幸せはありません。
第2に畑や庭からいろいろなことが学べるということ。畑も庭もどちらも同じく自然が相手ですから毎年同じではありません。いい年もあれば悪い年もあります。今までやってきた同じことが通用しないことだってあります。日々勉強です。それに結果が出るのに時間がかかります。何と言っても1年にチャンスは1回しかありません。今年だめならまた来年。気長な仕事です。
 庭もまた同じ。今年植えてみた花がその場所に合わなかったなんて言うことはしょっちゅうです。場所を変えてみたらうまくいったとか、逆にだめだったはずなのにどういうわけか4年目に成功したとか…本当にいろいろあるのです。結果が出るのに3年も4年もかかるのです。結果を急がないということもまた学ぶことができます。
庭もまた同じ。今年植えてみた花がその場所に合わなかったなんて言うことはしょっちゅうです。場所を変えてみたらうまくいったとか、逆にだめだったはずなのにどういうわけか4年目に成功したとか…本当にいろいろあるのです。結果が出るのに3年も4年もかかるのです。結果を急がないということもまた学ぶことができます。また、あまりにも過保護に育ててもいけません。時には厳しく育てるとすごくおいしい野菜が出来たりもします。しかし、ものによってはすごく大事に育てないと死んでしまうという植物もあります。相手によって対応も様々に変えなければいけないのだということも学びます。ほかにもいろいろ、あげればきりがないです。
第3は教育の面から。この頃はよく「食育」なんて言う言葉でテレビでも本でもよく言われるようになりましたが、そんな大げさな言い方でなくても食は人間形成にとってとても大事なものに決まってます。よく子どもが野菜ぎらいだとか「トマトを食べない」「きゅうりを食べない」「ジャガイモを残す」…などと言います。それは簡単なことです。おいしいトマトなら、おいしいキュウリなら、おいしいジャガイモならそれは子どもも食べます。それに(ここが大事なポイント)「お父ちゃん」が作った野菜なら食べてみようかという気になりますって。
 私が畑を趣味にし始めて20数年。子どもたちは本当に小さい時から私の作った野菜を食べてきました。おかげさまでうちでは子どもたちもよく野菜を食べてきました。
私が畑を趣味にし始めて20数年。子どもたちは本当に小さい時から私の作った野菜を食べてきました。おかげさまでうちでは子どもたちもよく野菜を食べてきました。
第4は「気分転換」です。ちょっと畑に出ると、またちょっと庭を眺めに行くと気分がすうーっとします。朝7時ごろから畑や庭に行き、植物の成長を眺めたり、また30分から1時間ぐらい草引きなどの軽い農作業をすることで体が徐々に目覚めて行きます。それから工房に入り、仕事にかかります。
ずっと一人で工房にこもって仕事をしていると息が詰まってきます。そんな時またちょっと畑や庭を見に行きます。またすうーっとします。英気が戻ってきます。そういうわけで本当に良い気分転換になるのです。そんなわけで畑も庭も私の生活には無くてはならないものとなっています。
さて、話を変えて工房では小物作りの試作中です。小物分野は普段の家具作りとは全く違うので、これはこれで相当悩みます。皆さんは不思議に思うかもしれませんが、小物作りって結構機械加工に頼る部分が大きいです。何と言っても一品が高価な家具と違って小物は一品が安価ですから、これで「稼ぐ」には大量に作る必要があります。つまりスピードも重要…結果、機械が重要ということになってしまうのです。
 例えばこの画像…こういう穴掘りの作業をする場合は通常「ルーターマシーン」という大きな木工機械を使います。(当工房は持っていません。「木になる話」の「どんな機械を使うか」をご覧ください。)
例えばこの画像…こういう穴掘りの作業をする場合は通常「ルーターマシーン」という大きな木工機械を使います。(当工房は持っていません。「木になる話」の「どんな機械を使うか」をご覧ください。)
あるいは大きな工場ではNCというコンピューター制御の大型機械を使うでしょう。当工房では仕方がないので写真のようにハンドルーターという電動工具を使って、治具を作ってやるしかありません。ルーターマシーンがあればどれだけ楽に、早くできることか…。
ずっと一人で工房にこもって仕事をしていると息が詰まってきます。そんな時またちょっと畑や庭を見に行きます。またすうーっとします。英気が戻ってきます。そういうわけで本当に良い気分転換になるのです。そんなわけで畑も庭も私の生活には無くてはならないものとなっています。
さて、話を変えて工房では小物作りの試作中です。小物分野は普段の家具作りとは全く違うので、これはこれで相当悩みます。皆さんは不思議に思うかもしれませんが、小物作りって結構機械加工に頼る部分が大きいです。何と言っても一品が高価な家具と違って小物は一品が安価ですから、これで「稼ぐ」には大量に作る必要があります。つまりスピードも重要…結果、機械が重要ということになってしまうのです。
 例えばこの画像…こういう穴掘りの作業をする場合は通常「ルーターマシーン」という大きな木工機械を使います。(当工房は持っていません。「木になる話」の「どんな機械を使うか」をご覧ください。)
例えばこの画像…こういう穴掘りの作業をする場合は通常「ルーターマシーン」という大きな木工機械を使います。(当工房は持っていません。「木になる話」の「どんな機械を使うか」をご覧ください。)あるいは大きな工場ではNCというコンピューター制御の大型機械を使うでしょう。当工房では仕方がないので写真のようにハンドルーターという電動工具を使って、治具を作ってやるしかありません。ルーターマシーンがあればどれだけ楽に、早くできることか…。
2017.10.16
「とっておきの…」
工房では3種の円卓が完成(一つは円卓で二つは円座卓です)し、塗装に入っています。正確に言うと桜(サクラ)の円卓と栃(トチ)の円座卓は塗装も終わり完成。欅(ケヤキ)の円座卓は塗装の最中です。
 こちらは栃(トチ)無垢一枚板の円座卓です。天板の鉋掛けをすると、きらきらしたきれいな模様が浮かび上がります。
こちらは栃(トチ)無垢一枚板の円座卓です。天板の鉋掛けをすると、きらきらしたきれいな模様が浮かび上がります。
 こちらは栃(トチ)無垢一枚板の円座卓です。天板の鉋掛けをすると、きらきらしたきれいな模様が浮かび上がります。
こちらは栃(トチ)無垢一枚板の円座卓です。天板の鉋掛けをすると、きらきらしたきれいな模様が浮かび上がります。
 天板のサイドの面は「蛇腹面」にしました。
天板のサイドの面は「蛇腹面」にしました。
 こちらは桜(サクラ)の円卓です。(前回の里山だよりにも書きました。)
オイルとワックスで塗装をしたら、きれいな模様が浮き出てきました。
こちらは桜(サクラ)の円卓です。(前回の里山だよりにも書きました。)
オイルとワックスで塗装をしたら、きれいな模様が浮き出てきました。実はこの板…とある木工家から格安で分けてもらったものです。(その方が仕事をお辞めになるというので処分されたのです。)
その方は「水目桜だ」と言ってみえましたが、私はどう見ても「アメリカンブラックチェリー」じゃないかと思ったわけです。結局わからずじまいでしたが、こうやって仕上げてみるとひょっとして本当に「水目桜」かもしれません。木って本当に分からないものです。
脚部はシンプルな1本脚です。天板の厚み、面の取り方(サイドの面はシンプルな面です)、脚部の模様など、スマート(スタイリッシュ)になりすぎないように あえて無骨な(素朴な)感じに仕上げてみました。

 脚柱のほうも鉋の削り跡がそのまま残っています。
脚柱のほうも鉋の削り跡がそのまま残っています。
 こちらは欅(ケヤキ)無垢一枚板の円座卓です。天板の裏側に「寄せ蟻」の加工をします。幅の広い大きな板脚に寄せ蟻の加工をしましたので、これ以上の反り止めはありません。強度は抜群です。
こちらは欅(ケヤキ)無垢一枚板の円座卓です。天板の裏側に「寄せ蟻」の加工をします。幅の広い大きな板脚に寄せ蟻の加工をしましたので、これ以上の反り止めはありません。強度は抜群です。

 こうして最後の塗装に入りました。珍しい杢をした欅(ケヤキ)の無垢一枚板円座卓です。
こうして最後の塗装に入りました。珍しい杢をした欅(ケヤキ)の無垢一枚板円座卓です。これら3つの作品も、以前から持っていた「とっておきの材料」を形にしたものです。今年初めの里山だよりに書きましたが、工房の中にはずっとしまってある「とっておきの材料」があります。それらに日の目を見させてやるというのが、今年の私の目標の一つでもありました。
先日ご紹介しました「クラロウォールナットのパーソナルデスク」や「シベリヤ産ベニマツのダイニングテーブル」、同じくシベリヤ産ベニマツで作った「SBチェア」などもそういうとっておきの材料を形にしたものです。こうして着々と目標がクリアできているのはうれしいことです。いずれお披露目の場を作ろうと思っています。まだまだ他にも作らなければなりません。
山桜の共木(ブックマッチのテーブルにするつもり)、由緒ある古刹の建具(テーブルまたは座卓に変身させるつもり)、存在感のある欅(ケヤキ)の無垢一枚板(座卓にするつもり)、杢のきれいな栃(トチ)の根株などなど…書き出せばきりがありません。
はたして全部形にすることができるのだろうか??…頑張ろうっと。
2017.10.10
「進みゆく季節」
畑では白菜、大根、カブ、キャベツ、ブロッコリー、レタス、正月菜や玉ねぎとネギの苗などが順調に育っています。数日前に種を蒔いたばかりのナバナもすでに芽を出しました。
サツマイモはすでに大きくなっており、何回か掘って食べたり、人にあげたりしています。イチゴの苗も仮植え床で順調に育っています。今月の終わりには本植えをするので、とりあえず起こして石灰を振っておきました。
工房では三種の円卓(座卓)の制作中です。まずは桜(サクラ)の円卓が完成しました。シンプルな一本脚のデザインにしてみました。今回もあまりスタイリッシュにならないようにどちらかというと無骨な(素朴な)感じにしてみました。(板や部材の厚みと「面」の処理の仕方、そして細部のデザインなどです。)
前にも書きましたが最近は「スタイリッシュな」「軽い」家具が流行ですが、私はそんな時代だからこそあえてそういう流行に乗らないようにしたいと思っています。あくまでも木の良さを素朴に伝えたいと思っています。
前にも書きましたが最近は「スタイリッシュな」「軽い」家具が流行ですが、私はそんな時代だからこそあえてそういう流行に乗らないようにしたいと思っています。あくまでも木の良さを素朴に伝えたいと思っています。
もう一つの栃(トチ)無垢一枚板の円座卓の方も制作中です。脚を円柱に加工します。円柱の加工はもちろん「木工ろくろ」でもできます。今回はそうではなく手鉋で作ります。
8角柱(ここまでは自動鉋盤という機械で削ります。)の角を削って16角柱にし、さらに角を削って32角柱、さらにさらに64角柱…といった感じで、限りなく円柱にしていくのです。鉋仕事は慣れれば苦ではありません。
8角柱(ここまでは自動鉋盤という機械で削ります。)の角を削って16角柱にし、さらに角を削って32角柱、さらにさらに64角柱…といった感じで、限りなく円柱にしていくのです。鉋仕事は慣れれば苦ではありません。
2017.10.02
「この頃のこと」
当工房の看板猫ジャガーが、大変なことになってしまいました。目を怪我して医者から外出禁止令が出てしまったのです。「このまま放っておくと目を縫わなきゃなりませんし、最悪目を取り出すことになってしまいますよ」と、(脅すつもりでもないでしょうが)言われてしまいました。
 ですので、言われた通り目薬をできるだけつけて(医者には一日10回はつけてくださいと言われましたが…)、カラーをして家の中に閉じ込めておくことになりました。
ですので、言われた通り目薬をできるだけつけて(医者には一日10回はつけてくださいと言われましたが…)、カラーをして家の中に閉じ込めておくことになりました。
 ですので、言われた通り目薬をできるだけつけて(医者には一日10回はつけてくださいと言われましたが…)、カラーをして家の中に閉じ込めておくことになりました。
ですので、言われた通り目薬をできるだけつけて(医者には一日10回はつけてくださいと言われましたが…)、カラーをして家の中に閉じ込めておくことになりました。
 しかし、ずっと家の中に置いておくのもかわいそうなので、猫用のハーネスを買ってきて外へ散歩に連れ出すことにしました。ところが、せっかく連れ出してもじっとしているだけであったり、狭いところをくぐって行こうとするのです。猫の散歩というのはどうやら無理みたいですね。
しかし、ずっと家の中に置いておくのもかわいそうなので、猫用のハーネスを買ってきて外へ散歩に連れ出すことにしました。ところが、せっかく連れ出してもじっとしているだけであったり、狭いところをくぐって行こうとするのです。猫の散歩というのはどうやら無理みたいですね。
 先日お寺の若院(次期住職)が結婚式をされました。家の前の道を花嫁行列が通りました。久しぶりに見た光景です。かく言う私も30年前に結婚した時同じように行列をしたものです。(その時は妻の実家のほうの祝い唄「めでた」という歌を歌いながらの行列でした。)
先日お寺の若院(次期住職)が結婚式をされました。家の前の道を花嫁行列が通りました。久しぶりに見た光景です。かく言う私も30年前に結婚した時同じように行列をしたものです。(その時は妻の実家のほうの祝い唄「めでた」という歌を歌いながらの行列でした。)見物客にはお菓子が配られました。こういう習わしが廃れていくのは少し淋しいですね。
一昨日の土曜日、いつものメンバーでまたまたピザ会をしました。パンはちょっと失敗。少し焦げてしまいました。でも中身はおいしかったです。ジャガーも一緒に参加しました。

 すると、「今日は隊長(私、そんなふうに呼ばれています)の還暦祝いです」と言ってプレゼントまでいただきました。サプライズだったので本当にうれしかったです。
すると、「今日は隊長(私、そんなふうに呼ばれています)の還暦祝いです」と言ってプレゼントまでいただきました。サプライズだったので本当にうれしかったです。来ていただけるだけで十分うれしいのに、こんなことまでしてもらって…みなさん、どうもありがとうございました。
 赤いポロシャツでした(還暦だから?)。普段は地味な色の服しか着ないので少し恥ずかしかったですが、「似合う、似合う」とおだてられ、悪い気分はしなかったです。
赤いポロシャツでした(還暦だから?)。普段は地味な色の服しか着ないので少し恥ずかしかったですが、「似合う、似合う」とおだてられ、悪い気分はしなかったです。「これからもずっとピザを焼いてください」と言われました。当分焼き場担当は離れられそうもありません。
2017.09.22
「秋、創造の秋」
 秋めいてきました。過ごしやすくなってうれしいです。これから仕事の方もはかどることでしょう。先日完成した「クラロウォールナット パーソナルデスク」はやっぱりすごくいいです。自分の机にしたいぐらいです。でもそんなことは言ってられません。現物在庫あります。どなたかご購入ください。
秋めいてきました。過ごしやすくなってうれしいです。これから仕事の方もはかどることでしょう。先日完成した「クラロウォールナット パーソナルデスク」はやっぱりすごくいいです。自分の机にしたいぐらいです。でもそんなことは言ってられません。現物在庫あります。どなたかご購入ください。
 工房では新作椅子の制作にかかっています。「KOSI-KAKE」をベースに改良したものですが、似て非なるものになりそうです。イメージは「よりシンプルに」「より手作り感を感じられるように」「より軽く」「KOSI-KAKEのすわり心地をそのままに」ていう感じですか…。
工房では新作椅子の制作にかかっています。「KOSI-KAKE」をベースに改良したものですが、似て非なるものになりそうです。イメージは「よりシンプルに」「より手作り感を感じられるように」「より軽く」「KOSI-KAKEのすわり心地をそのままに」ていう感じですか…。シンプルにするっていうことはその分仕口もより強度が保てるものにする必要がありますし、加工の精度も必要となってきます。
実際の作業は以下の動画でご覧ください。
2017.09.04
「夏が終わった」
朝晩はだいぶん涼しくなり、日中も風がさわやかに感じるようになりました。今年はことのほか暑くジメジメした夏でしたが、ようやく終わりだなと感じて嬉しく思っています。妻や娘は「夏が終わってさみしい」と言ってますが、私は全然そんなことはありません。暑いのが大嫌いです。寒いのは我慢できます。
8月終わりにいつものメンバーで夏の終わりのピザ会もやりました。もうこのメンバーでは数え切れないほどやっているので、本当に気が楽で楽しいです。準備から後片付けまで本当によくやっていただけるのも助かります。
8月終わりにいつものメンバーで夏の終わりのピザ会もやりました。もうこのメンバーでは数え切れないほどやっているので、本当に気が楽で楽しいです。準備から後片付けまで本当によくやっていただけるのも助かります。
先日の還暦祝いの家族旅行を除けば、今年唯一のレジャーでした。
 畑や庭の方もすでに秋仕様へと変わっています。畑ではイチゴの苗の仮植えをしておきました。今年は猛暑続きだったので苗があまり育たず、いい苗が少ないみたいですが、それでも100本以上の苗を仮植え床に移植しておきました。ここで1ヶ月ほど育てて今月末~10月はじめに本植えをします。
畑や庭の方もすでに秋仕様へと変わっています。畑ではイチゴの苗の仮植えをしておきました。今年は猛暑続きだったので苗があまり育たず、いい苗が少ないみたいですが、それでも100本以上の苗を仮植え床に移植しておきました。ここで1ヶ月ほど育てて今月末~10月はじめに本植えをします。
 組み立てをします。大きく重い一枚板なので一人で組み立てるのは大変です。ボンドが乾いてしまうといけないのでスピードも必要です。段取りをしっかりし、頭の中でシミュレーションをしてから、「いざっ!」という感じで組み立てにかかります。
組み立てをします。大きく重い一枚板なので一人で組み立てるのは大変です。ボンドが乾いてしまうといけないのでスピードも必要です。段取りをしっかりし、頭の中でシミュレーションをしてから、「いざっ!」という感じで組み立てにかかります。
 次は表面の仕上げにかかります。まずは穴に樹脂を充填して埋めます。裏側まで貫通しているようなので(いきなり表から入れると裏側にボトボトと垂れてくるので)まずは裏側に入れて固めます。(蓋をする感じです。)
数時間おいて固まったら今度は表側から入れます。
次は表面の仕上げにかかります。まずは穴に樹脂を充填して埋めます。裏側まで貫通しているようなので(いきなり表から入れると裏側にボトボトと垂れてくるので)まずは裏側に入れて固めます。(蓋をする感じです。)
数時間おいて固まったら今度は表側から入れます。大きな穴、深い穴の場合は一度にできませんので、何回にも分けて樹脂を入れて固めていきます。ですからこの作業でも結構な時間を要します。
黄色っぽくなっているところもまた時間とともに褐色に変化していくと思います。ユニークな表情が現れた、また厚みもしっかりある大きな一枚板の机が出来ました。
2017.08.22
「ウォールナット一枚板との格闘」

 先日完成したヒノキのベンチを、我が家のダイニングテーブルに合わせて置いてみました。
先日完成したヒノキのベンチを、我が家のダイニングテーブルに合わせて置いてみました。テーブルと椅子はシベリア産ベニマツですが、ヒノキもなかなか合います。
さて工房では、只今ウォールナットの一枚板を使って「パーソナルデスク」を制作中です。なかなかの大きな無垢一枚板なので、一人親方の私としてはまさに格闘中といったところです。
削ってみて確信に変わったのですが、このウォールナットは貴重なクラロウォールナットという種類の材です。(その証拠を見つけました。クラロウォールナットの証である接ぎ木の跡です。) この種類の木はなかなか乾燥が難しくてなかなか乾かないと、材木店の社長が言っていました。この板も天然乾燥の後人工乾燥に入れ、さらに工房にて2年ほど置いてあったにも関わらず、削ってみたら未乾燥の状態でした。ただし様子を見ていると反ることもなく、心配していたような部分的に痩せていくことも無さそうなので大丈夫のようです。
 とりあえず削って所定の厚みに仕上げた後、どこでカットするか(どういう形にするか、長さをどれだけにするか)しばし悩みます。
とりあえず削って所定の厚みに仕上げた後、どこでカットするか(どういう形にするか、長さをどれだけにするか)しばし悩みます。
決まったらカットに入ります。片方をまっすぐにするのも大きく重い板なので、一人でやるのは一苦労です。
 ここから、いよいよ「留形隠し蟻組み接ぎ」の加工に入ります。可能な限り精密に墨線を引き、のこぎりを入れます。この作業の正確さが命です。ウォールナットは色が黒いので鉛筆の線が見えにくくて大変です。(以前白い芯のシャープペンを購入してやってみましたが、結局普通の鉛筆が一番だということに落ち着きました。)
ここから、いよいよ「留形隠し蟻組み接ぎ」の加工に入ります。可能な限り精密に墨線を引き、のこぎりを入れます。この作業の正確さが命です。ウォールナットは色が黒いので鉛筆の線が見えにくくて大変です。(以前白い芯のシャープペンを購入してやってみましたが、結局普通の鉛筆が一番だということに落ち着きました。)
電動工具も使って大まかに落とします。

 際鉋やノミを使って留(45度)の部分を削って作っていきます。
際鉋やノミを使って留(45度)の部分を削って作っていきます。
こうして「留形隠し蟻組み接ぎ」の加工を終えました。これだけの大きさの一枚板にこの加工をしようと思うと、「微調整」などというまどろっこしいことはむしろ大変です。墨付け、のこぎりの切り込み、ノミ仕事など、各段階を出来る限り精密に行うことが全てです。
2017.08.17
「シークレット」
8月11日に1泊2日で家族旅行に行ってきました。実は私、今年で還暦を迎えます。そこで我が子どもたちが、その祝いということでこの旅行を計画して連れて行ってくれたのです。行先も何もわからない「シークレット旅行」でした。
行く前から「お父さん汚れてもいい靴を持って行ってよ」というので「どこへ連れて行くんだ?」と不安になったり、車がだんだん山の中へ入って行くので…
…という具合。
着いたところは美しい渓谷でした。きれいな滝がいっぱいありました。とても涼しく気持ちが良かったです。久しぶりにそんな気持ちのいい空間で過ごしました。
行く前から「お父さん汚れてもいい靴を持って行ってよ」というので「どこへ連れて行くんだ?」と不安になったり、車がだんだん山の中へ入って行くので…
私「おいキャンプをさせる気じゃないの?」
私「食事をするところはあるの?」
娘「わからん(笑)」
私「食事をするところはあるの?」
娘「わからん(笑)」
…という具合。
着いたところは美しい渓谷でした。きれいな滝がいっぱいありました。とても涼しく気持ちが良かったです。久しぶりにそんな気持ちのいい空間で過ごしました。
その後すぐ近くの温泉に入り、少し行ったところで昼食をいただきました。私は車を運転しなくていいので安心して昼間から酔っぱらうことが出来ました。
 そして旅館へ行きました。温泉旅館でした。還暦の記念写真を撮りました。(旅館が用意してくれた赤いちゃんちゃんこを着た写真も撮りましたが、恥ずかしいので載せません(笑))
そして旅館へ行きました。温泉旅館でした。還暦の記念写真を撮りました。(旅館が用意してくれた赤いちゃんちゃんこを着た写真も撮りましたが、恥ずかしいので載せません(笑))
妻からはプレゼントももらいました。私にとってはこれ以上も無いうれしい還暦祝いとなりました。子どもたちに感謝です。ありがとう。
さて工房ではヒノキのベンチが完成しました。シンプルなベンチです。
 そして旅館へ行きました。温泉旅館でした。還暦の記念写真を撮りました。(旅館が用意してくれた赤いちゃんちゃんこを着た写真も撮りましたが、恥ずかしいので載せません(笑))
そして旅館へ行きました。温泉旅館でした。還暦の記念写真を撮りました。(旅館が用意してくれた赤いちゃんちゃんこを着た写真も撮りましたが、恥ずかしいので載せません(笑))妻からはプレゼントももらいました。私にとってはこれ以上も無いうれしい還暦祝いとなりました。子どもたちに感謝です。ありがとう。
さて工房ではヒノキのベンチが完成しました。シンプルなベンチです。
 そしてこれから、ウォールナット無垢一枚板を使って「パーソナルデスク」を制作します。
そしてこれから、ウォールナット無垢一枚板を使って「パーソナルデスク」を制作します。
2017.08.08
「暑い!」
2017.08.01
「素朴、遊び心」
うだるような暑さが続きます。お昼過ぎともなると、工房の中はスポットクーラーに当たっていないと5分で気分が悪くなるぐらいの暑さです。暑くて庭も畑も放ったらかしで、ネタにするような写真はありません。そんなわけで木工ネタになります。
 我が家のダイニングテーブルセットを設置してみました。妻曰く「うちの家具を作ったのは初めてじゃないの?」…いいえ!そんなことはありません!カップボード、ベンチソファ、2人の子どもの学習机、本立て、ベッド…結構作ってますよ。(子どものが多いな!嫁さんのリクエストにはあまり応えて来てなかったな。)
我が家のダイニングテーブルセットを設置してみました。妻曰く「うちの家具を作ったのは初めてじゃないの?」…いいえ!そんなことはありません!カップボード、ベンチソファ、2人の子どもの学習机、本立て、ベッド…結構作ってますよ。(子どものが多いな!嫁さんのリクエストにはあまり応えて来てなかったな。)
 我が家のダイニングテーブルセットを設置してみました。妻曰く「うちの家具を作ったのは初めてじゃないの?」…いいえ!そんなことはありません!カップボード、ベンチソファ、2人の子どもの学習机、本立て、ベッド…結構作ってますよ。(子どものが多いな!嫁さんのリクエストにはあまり応えて来てなかったな。)
我が家のダイニングテーブルセットを設置してみました。妻曰く「うちの家具を作ったのは初めてじゃないの?」…いいえ!そんなことはありません!カップボード、ベンチソファ、2人の子どもの学習机、本立て、ベッド…結構作ってますよ。(子どものが多いな!嫁さんのリクエストにはあまり応えて来てなかったな。)
 それにしてもやはりベニマツの家具はいいですねえ。暖かく、優しく、明るく、そして軽いけれど見た目は重厚な感じです。(部材の厚みは通常使う広葉樹よりも分厚いです。松なので強度を考えるとそうなります。)
それにしてもやはりベニマツの家具はいいですねえ。暖かく、優しく、明るく、そして軽いけれど見た目は重厚な感じです。(部材の厚みは通常使う広葉樹よりも分厚いです。松なので強度を考えるとそうなります。)画像の奥に見えるのは10数年前に(練習で)作った同じくベニマツのカップボードとサイドテーブルですが、いい感じに色が濃く変化しています。このテーブルと椅子もいずれはそんな感じに味わいを増すことでしょう。
 ところで、工房では円卓が完成しています。天板の側面を鉋掛けしてきれいに整えます。
ところで、工房では円卓が完成しています。天板の側面を鉋掛けしてきれいに整えます。
 完成した脚部を天板に組み込みます。「寄せ蟻」の加工がしてあるので、叩き込んで組み付けます。
完成した脚部を天板に組み込みます。「寄せ蟻」の加工がしてあるので、叩き込んで組み付けます。
ところで、ここからが今日のメインテーマ。今年になって、私はもう一度自分を見直す良い機会に恵まれました。今のままの仕事ぶりで良いのか、さらに言うと本当に作りたいものが何であったのか…いろいろ考えました。ある意味「原点回帰」です。
昔よく眺めた家具の写真集(外国の家具)を、何冊ももう一度引っ張り出してきて見直したりもしました。(多くは外国の田舎の風景や室内、家具の写真です。) 忘れていたことをたくさん思い出しました。その時の気持ちを思い出し、今の仕事を見つめなおそうと思いました。同時にまた「あれも作りたい、これも作りたい!」という初心も蘇ってきました。
話はそれますが、家具業界にも「流行(はやり)」があります。今は「軽い家具」「コラボ(たとえば鉄と木、皮と木、ファブリック(布)と木など…)」「シンプル・モダン」「カトラリー(皿やスプーンなどといったキッチングッズなど)」「編み座の椅子(有名なウェグナーのYチェアのようなペーパーコードで編んだ椅子のようなもの)」などがそうだと思います。でも、私自身はそういうのにはあまり興味がありません。
p.s. 私自身は現状の流行の中には(私たち「木工家」と言われる人たちにとっては)、自分たちで自分たちの首を絞めるようなこともあると思っています。
私が木工を始めたころは、どちらかというと「木の味わいを前面に出す」「木の良さを伝えたい」というのが主流だったと思います。私自身はこの点はこれからも変わることが無いと思っています。
そこでですが、最近私が思っているのは「素朴さ」を味わえること、そして近代になって日本人が忘れている「遊び心」を思い出すことです。これまでに納品のついでにいろんな歴史的な建物も見学することが出来ました。会津城、法隆寺、高野山金剛峰寺、長野善光寺、円覚寺・建長寺など鎌倉の諸寺、宇治平等院鳳凰堂、厳島神社…昔の建築物や建具、家具などを見るとそこかしこに作った人の遊び心が見られます。(もちろん上述の外国の田舎の家具の写真集にもそれが見られます。)
 現代の建築物や家具、建具などはそれとはまったく反対です。圧倒的に現代の方が技術(機械、工具など)は進歩しているのに、昔の人の方がよほどモノづくりに対する心の豊かさが感じられます。粋でおしゃれです。私も家具作りにそういうことを少し入れていかなきゃなと思いました。
現代の建築物や家具、建具などはそれとはまったく反対です。圧倒的に現代の方が技術(機械、工具など)は進歩しているのに、昔の人の方がよほどモノづくりに対する心の豊かさが感じられます。粋でおしゃれです。私も家具作りにそういうことを少し入れていかなきゃなと思いました。
もちろんこれまでに作ってきたものと路線が大きく変わるわけではなく、デザインががらっと変わるわけではないと思いますが、どこか「素朴」な感じがしたり、「おっ!」と気づかれるようなところがある家具を作っていければなと思っています。
昔よく眺めた家具の写真集(外国の家具)を、何冊ももう一度引っ張り出してきて見直したりもしました。(多くは外国の田舎の風景や室内、家具の写真です。) 忘れていたことをたくさん思い出しました。その時の気持ちを思い出し、今の仕事を見つめなおそうと思いました。同時にまた「あれも作りたい、これも作りたい!」という初心も蘇ってきました。
話はそれますが、家具業界にも「流行(はやり)」があります。今は「軽い家具」「コラボ(たとえば鉄と木、皮と木、ファブリック(布)と木など…)」「シンプル・モダン」「カトラリー(皿やスプーンなどといったキッチングッズなど)」「編み座の椅子(有名なウェグナーのYチェアのようなペーパーコードで編んだ椅子のようなもの)」などがそうだと思います。でも、私自身はそういうのにはあまり興味がありません。
p.s. 私自身は現状の流行の中には(私たち「木工家」と言われる人たちにとっては)、自分たちで自分たちの首を絞めるようなこともあると思っています。
私が木工を始めたころは、どちらかというと「木の味わいを前面に出す」「木の良さを伝えたい」というのが主流だったと思います。私自身はこの点はこれからも変わることが無いと思っています。
そこでですが、最近私が思っているのは「素朴さ」を味わえること、そして近代になって日本人が忘れている「遊び心」を思い出すことです。これまでに納品のついでにいろんな歴史的な建物も見学することが出来ました。会津城、法隆寺、高野山金剛峰寺、長野善光寺、円覚寺・建長寺など鎌倉の諸寺、宇治平等院鳳凰堂、厳島神社…昔の建築物や建具、家具などを見るとそこかしこに作った人の遊び心が見られます。(もちろん上述の外国の田舎の家具の写真集にもそれが見られます。)
 現代の建築物や家具、建具などはそれとはまったく反対です。圧倒的に現代の方が技術(機械、工具など)は進歩しているのに、昔の人の方がよほどモノづくりに対する心の豊かさが感じられます。粋でおしゃれです。私も家具作りにそういうことを少し入れていかなきゃなと思いました。
現代の建築物や家具、建具などはそれとはまったく反対です。圧倒的に現代の方が技術(機械、工具など)は進歩しているのに、昔の人の方がよほどモノづくりに対する心の豊かさが感じられます。粋でおしゃれです。私も家具作りにそういうことを少し入れていかなきゃなと思いました。もちろんこれまでに作ってきたものと路線が大きく変わるわけではなく、デザインががらっと変わるわけではないと思いますが、どこか「素朴」な感じがしたり、「おっ!」と気づかれるようなところがある家具を作っていければなと思っています。
2017.07.28
「相変わらず」

 大雨(ゲリラ豪雨)でジメジメむしむしとした日か、猛暑かどっちかしかないという日々が続きます。本当に嫌です。
大雨(ゲリラ豪雨)でジメジメむしむしとした日か、猛暑かどっちかしかないという日々が続きます。本当に嫌です。おかげで畑も庭も構う気になれず、相当荒れています。そんな中でも野菜はたくさん取れています。取れすぎで食べられず腐っていくことが多いです。もったいないですが…。

 さて工房の方は、スピンドルバックの椅子3脚が完成しました。3脚合わせると、脚やスピンドル合わせて約70本ほどの丸棒を木工ろくろで挽くことになります。
さて工房の方は、スピンドルバックの椅子3脚が完成しました。3脚合わせると、脚やスピンドル合わせて約70本ほどの丸棒を木工ろくろで挽くことになります。それを、その後でまたすべて鉋掛けします。鉋の削り跡を残します。その方がいい感じになります。
 今回こんなものを買いました。携帯を固定して自撮りするアームです。これで座ぐりをしているところの動画を撮りました。それはInstagramの方に載せています。よかったら見てください。
今回こんなものを買いました。携帯を固定して自撮りするアームです。これで座ぐりをしているところの動画を撮りました。それはInstagramの方に載せています。よかったら見てください。

 組み立てをして仕上げをします。この椅子は1脚に10ヶ所も「通しほぞ」を使っています。組み立ててからそれらを切り取って削り、仕上げます。
組み立てをして仕上げをします。この椅子は1脚に10ヶ所も「通しほぞ」を使っています。組み立ててからそれらを切り取って削り、仕上げます。
2017.07.06
「試作終了、そしてinstagram」
 工房にコバエが出始めました。と言っても4年前と比べるとごくごくわずかですけど。体にまとわりつくとうっとおしいですが、扇風機を回して吹き飛ばしています。
工房にコバエが出始めました。と言っても4年前と比べるとごくごくわずかですけど。体にまとわりつくとうっとおしいですが、扇風機を回して吹き飛ばしています。台風や大雨の被害もほとんど無いことを考えると、猿やコバエに苦しむことぐらいは我慢しなければいけないのかもしれません。

 「jagar's garden」はいよいよ夏の庭になってきました。アジサイやギボウシなどの夏のコーナーもボリュームが出てきました。ハーブコーナーにはベルガモットの花が咲き始めました。また、エキノプスも特徴的な花を咲かせ始めました。
「jagar's garden」はいよいよ夏の庭になってきました。アジサイやギボウシなどの夏のコーナーもボリュームが出てきました。ハーブコーナーにはベルガモットの花が咲き始めました。また、エキノプスも特徴的な花を咲かせ始めました。
 この椅子は通しほぞを多用する椅子です。組み立ててから切り取って、きれいに削り取ります。
この椅子は通しほぞを多用する椅子です。組み立ててから切り取って、きれいに削り取ります。
ところで話は変わりますが、実は一昨日からこっそり「instagram(インスタグラム)」を始めました。この「instagram(インスタグラム)」は普段の仕事の様子を切り取って載せていくつもりです。よかったら見てやってください。
「半布里工房のInstagram(インスタグラム)」
「半布里工房のInstagram(インスタグラム)」
2017.06.30
「盛夏近し」
 工房で制作中の新作椅子もだんだん形になってきました。脚や背・肘のスピンドルを木工ろくろで挽きました。大分慣れてきたので早くなってきました。削れるときに出る「シャーッ」という音が心地よく感じられるようになりました。
工房で制作中の新作椅子もだんだん形になってきました。脚や背・肘のスピンドルを木工ろくろで挽きました。大分慣れてきたので早くなってきました。削れるときに出る「シャーッ」という音が心地よく感じられるようになりました。
ろくろで挽いた丸棒は、さらに鉋を掛けて仕上げます。鉋の跡はそのまま残します。その方がいい感じになります。当工房の他の作品の多くもこんな風に手鉋の跡を残すようにしています。
 もちろん腰掛けてみて、すわり心地も確かめます。まだ接着剤はつけていませんが、すでにしっかり組み合わされてびくともしません。すわり心地は合格点です。肘や背板、座板を整形し、座板に座刳りを施せばさらにすわり心地は良くなるはずです。
もちろん腰掛けてみて、すわり心地も確かめます。まだ接着剤はつけていませんが、すでにしっかり組み合わされてびくともしません。すわり心地は合格点です。肘や背板、座板を整形し、座板に座刳りを施せばさらにすわり心地は良くなるはずです。
さて畑の方ではいろんな野菜が収穫間近となっています。トマト、スイカ、ネットメロン、トウモロコシなどなど…こういう野菜が取れ始めるといよいよ夏だなあと感じます。
 トマト、ミニトマトが取れ始めました。今年初めて食べたミニトマトに妻が「すごく甘い!今までで一番甘かった時と同じぐらい!」と言っていました。
トマト、ミニトマトが取れ始めました。今年初めて食べたミニトマトに妻が「すごく甘い!今までで一番甘かった時と同じぐらい!」と言っていました。
その年、取れたトマトを差し上げたある人が(うちにいらっしゃってその場で食べなさったのですが)今だに「あのミニトマトの味が忘れられない」と言っているそうです。そんなにおいしかったかな?(でも野菜を作っているとそういう時があります。私もかつて作ったスイカの味がいまだに忘れられません。その味を再び味わいたくて毎年スイカを作っているのです。) 今年はおいしいトマトが食べれそうです。
 そのスイカも大きくなってきました。一つだけは結構大きそうです。
そのスイカも大きくなってきました。一つだけは結構大きそうです。
 トマト、ミニトマトが取れ始めました。今年初めて食べたミニトマトに妻が「すごく甘い!今までで一番甘かった時と同じぐらい!」と言っていました。
トマト、ミニトマトが取れ始めました。今年初めて食べたミニトマトに妻が「すごく甘い!今までで一番甘かった時と同じぐらい!」と言っていました。その年、取れたトマトを差し上げたある人が(うちにいらっしゃってその場で食べなさったのですが)今だに「あのミニトマトの味が忘れられない」と言っているそうです。そんなにおいしかったかな?(でも野菜を作っているとそういう時があります。私もかつて作ったスイカの味がいまだに忘れられません。その味を再び味わいたくて毎年スイカを作っているのです。) 今年はおいしいトマトが食べれそうです。
 そのスイカも大きくなってきました。一つだけは結構大きそうです。
そのスイカも大きくなってきました。一つだけは結構大きそうです。

 畝が余ったので一株だけ植えておいたマクワウリです。実ができ始めました。
畝が余ったので一株だけ植えておいたマクワウリです。実ができ始めました。最近はやりのさまざまなメロンと比べるともちろん味は淡白で甘みが少ないですが、何と言っても懐かしい味です。
私の子どもの頃にはこれぐらいしかありませんでした。でもおばあさんが畑から取ってきてくれたマクワウリを皮をむいて切ってもらって、少し塩を付けて食べたあのおいしさは今でも覚えています。何もなかったころはそんなものでも本当においしく感じられたのですね。幸せとは…幸せな時代とは…。
実はひそかに楽しみにしているのが、工房のすぐ下のところに作っているこの枝豆です。上手に出来たらビールのつまみにして食べます。ところが、枝豆というのは意外と作るのが難しいのです。いい感じに育っているなあと思っていたら葉や茎だけ大きく育って実が全然出来ていなかったり、夏の暑さにやられて枯れてしまったり…今まで失敗の連続です。
 ですから、たいていの人はこの時期には枝豆(大豆)は作っていません。大体7月の終わりごろに種を蒔いて秋に(大豆として)収穫という感じです。でもそれではビールのおいしい時期に食べたい枝豆としては間に合わないので私はあえて今作っているのです。
ですから、たいていの人はこの時期には枝豆(大豆)は作っていません。大体7月の終わりごろに種を蒔いて秋に(大豆として)収穫という感じです。でもそれではビールのおいしい時期に食べたい枝豆としては間に合わないので私はあえて今作っているのです。枝豆(大豆。以前テレビでやっていましたが枝豆が大豆と同じものだということを知らない人が大変多いのですね)は、肥沃な土壌は好まないみたいです。それに結構灌水も必要みたいです。工房の下の一番痩せた土のところであまり肥料はやらずに今年は育ててみました。さてうまく行くでしょうか…。
2017.06.27
「こぼれ種」
 前回の里山だよりで、きゅうりが取れすぎて困るということを書きました。
前回の里山だよりで、きゅうりが取れすぎて困るということを書きました。
やはり理想は、苗や種をできるだけ買ってこなくても自家栽培で済むようにすることです。できるだけ宿根草をたくさん植えるのもそのためだし、種を取っておいてその種で増やすようにしていこうと思っています。
 こちらのコーナーは、いろんな花がこぼれ種から芽を出すワイルドフラワーコーナーです。毎年シーズンが終わり、花の種が落ちてしまったころに、管理機でだーっと混ぜてしまいます。
こちらのコーナーは、いろんな花がこぼれ種から芽を出すワイルドフラワーコーナーです。毎年シーズンが終わり、花の種が落ちてしまったころに、管理機でだーっと混ぜてしまいます。
すると春になるとまたいろんな花の芽が出てきます。「何が出るかな?」と楽しみです。草もいっぱい生えてきますので、間違えて引いてしまわないようにしなければいけません。
ジャーマンカモミールはこちらから苗を移植して植えています。ほかにもポピー、百日草、トラノオ、ダイアンサスやその他名も知らない花がいっぱい咲いてきます。ヒマワリもいっぱい芽を出しています。こちらから掘り起こしてジャガーズガーデンのほうに移植してやったりします。
 千日紅も掘り起こして移植してやります。
千日紅も掘り起こして移植してやります。
 こちらのコーナーは、いろんな花がこぼれ種から芽を出すワイルドフラワーコーナーです。毎年シーズンが終わり、花の種が落ちてしまったころに、管理機でだーっと混ぜてしまいます。
こちらのコーナーは、いろんな花がこぼれ種から芽を出すワイルドフラワーコーナーです。毎年シーズンが終わり、花の種が落ちてしまったころに、管理機でだーっと混ぜてしまいます。すると春になるとまたいろんな花の芽が出てきます。「何が出るかな?」と楽しみです。草もいっぱい生えてきますので、間違えて引いてしまわないようにしなければいけません。
ジャーマンカモミールはこちらから苗を移植して植えています。ほかにもポピー、百日草、トラノオ、ダイアンサスやその他名も知らない花がいっぱい咲いてきます。ヒマワリもいっぱい芽を出しています。こちらから掘り起こしてジャガーズガーデンのほうに移植してやったりします。
 千日紅も掘り起こして移植してやります。
千日紅も掘り起こして移植してやります。
現在のジャガーズガーデンはタチアオイやハーブやアジサイがきれいです。ダリアも咲き始めました。
2017.06.22
「肝要なのは風通しの良さ」
 工房の壁にこんなものが取り付けてあります。何に使うのでしょう?
工房の壁にこんなものが取り付けてあります。何に使うのでしょう?…正解は角材や丸棒などの中心を見つける道具です。昔小中学校で「対角線と対角線の交点が中心」とか「直径は円の中心を通る直線」などと習ったものですが、それです。小中学校の算数(数学)が日常的に使われるのが木工の仕事です。
ところで、只今ひたすら木工ろくろの仕事をしています。丸棒を作って脚やスピンドルにした椅子作りです。
 新作の椅子は同じく丸棒を使った「ウインザーチェア風」の椅子です。この後も当分ろくろ師としての生活が続きそうです。
新作の椅子は同じく丸棒を使った「ウインザーチェア風」の椅子です。この後も当分ろくろ師としての生活が続きそうです。大抵の家具は普通は十分の一(または五分の一)ぐらいの縮小図面でいけるのですが、今回は難しそうなので実寸図面を書いてみました。作る前からすでにわくわくしています。
 畑の方ですが野菜は順調です。トマトは6段~7段ぐらいまで花が咲いて実がたくさんついてきました。
畑の方ですが野菜は順調です。トマトは6段~7段ぐらいまで花が咲いて実がたくさんついてきました。トマトは結構手をかけて育てます。毎日様子を見て、脇芽を取ってやることはもちろん、混み合っている葉っぱを取って風通しを良くしてやります。トマトの下には千切った葉っぱがいっぱい落ちています。花でも何でもそうですがやはり風通しを良くしてやることがすごく大事だと思っています。風通しを良くして日もよく当たるようにしてやります。
 ナスも同じです。混み合っていると中にまで日が当たらないので良いナスができません。下の方の葉は早めに取り去り、混んでいるところは切ってしまっても構いません。私はナスを収穫したら、その上の葉一枚を残してその上からばっさり切ってしまいます。(その葉の脇にはすでに新しい芽が出来ています。それがまた伸びてきます。)
ナスも同じです。混み合っていると中にまで日が当たらないので良いナスができません。下の方の葉は早めに取り去り、混んでいるところは切ってしまっても構いません。私はナスを収穫したら、その上の葉一枚を残してその上からばっさり切ってしまいます。(その葉の脇にはすでに新しい芽が出来ています。それがまた伸びてきます。)その上にも実がついていることが多いのでもったいないようにも思えますが、構うことはありません。昨年このやり方をしたら、秋まで何もしなくてもたくさんのナスが取れました。
とにかくさっきも書きましたが、植物は花でも野菜でも風通しを良くしてやることが本当に大事です。そうしないと蒸れて弱ったり病気になったり、いろいろ弊害が出てきます。(我々の社会でも風通しの良い社会であることが大切ですね。)
 言い忘れましたが、唯一ミニトマトは私の場合は「放ったらかし」農法です。ジャングルのようになっています。でも毎年このやり方で、すごくおいしいミニトマトがたくさん取れています。もちろん風通しを良くするために葉っぱを切って取ったり、あまりにも混み合っているところは切って取ったりぐらいはしますけど。
言い忘れましたが、唯一ミニトマトは私の場合は「放ったらかし」農法です。ジャングルのようになっています。でも毎年このやり方で、すごくおいしいミニトマトがたくさん取れています。もちろん風通しを良くするために葉っぱを切って取ったり、あまりにも混み合っているところは切って取ったりぐらいはしますけど。
 ネットメロンのほうも、実がたくさんついています。
ネットメロンのほうも、実がたくさんついています。本などを読むと「小蔓を3本ぐらい伸ばし、主蔓の何節目で切り、さらに孫蔓の何節目で切り取る…」等々いろいろ書いてありますが、それは大変難しいです。出たとこ勝負の佐藤農法ではまず適当に放っておきます。そのうち実がついてきますので、様子を見ていいものだけを一株に8個ほど残すようにして、あとは取ってしまいます。
 きゅうりの方は毎日取れすぎで困っています。今日もこんなに…毎回言いますがこれを処理するのは妻です。この間もやむなく大量に「きゅうりのキュウちゃん」にしてくれました。「また!」という声が聞こえてきそうです。
きゅうりの方は毎日取れすぎで困っています。今日もこんなに…毎回言いますがこれを処理するのは妻です。この間もやむなく大量に「きゅうりのキュウちゃん」にしてくれました。「また!」という声が聞こえてきそうです。そんなわけで畑では夏野菜が続々と収穫の時を迎えています。

 それに伴って、猿の大襲来も予想されます。(すでに毎日のように猿が来ています。ロケット花火で対抗する毎日が続いています。)
それに伴って、猿の大襲来も予想されます。(すでに毎日のように猿が来ています。ロケット花火で対抗する毎日が続いています。) それでトウモロコシ、トマト、スイカ、メロンなど主だったものは網で囲っておきました。
我が家では「野菜の摂取が足りない」ということだけはありません。
2017.06.16
「ジャガイモ収穫」
 前回の里山だよりにに書きましたが、ジューンベリーの実がなっていたので収穫してジャムを作りました。今年はジューンベリーの実が豊作です。ボールにいっぱい取れました。測ってみたら650gほどでした。
前回の里山だよりにに書きましたが、ジューンベリーの実がなっていたので収穫してジャムを作りました。今年はジューンベリーの実が豊作です。ボールにいっぱい取れました。測ってみたら650gほどでした。
 こちらは今年取れたイチゴでちょっと前に(妻が)作ったイチゴジャムです。もうだいぶん食べましたが…。自分で言うのもナンデスガ、今まで食べたイチゴジャムの中で一番おいしいです。今年はイチゴが豊作ですごく甘かったです。
こちらは今年取れたイチゴでちょっと前に(妻が)作ったイチゴジャムです。もうだいぶん食べましたが…。自分で言うのもナンデスガ、今まで食べたイチゴジャムの中で一番おいしいです。今年はイチゴが豊作ですごく甘かったです。ところで、昨日、今日と2日間に分けてジャガイモの収穫をしました。2日間もかかったのは、このところの日照り続きで土がカチカチになっていて掘るのが大変だったからで、無理せず半分づつ収穫することにしました。カチカチの土である上に畝間に草も生えていて、それを抜いたりしながら掘るので余分な手間でした。
生育の良い年は茎葉も大きく育つので、その陰になって草はあまり生えません。(誰かが「茎があまり大きくなると栄養が茎の方に行ってしまうから良くない」と言っていましたが、そんなことは絶対ありません。やはり茎葉もある程度大きくしっかり育った方がいいです。私の経験上そう思います。) そういう意味でも今年はあまり良くないと思います。
 そんなわけで、結果を言うと今年は不作です。(昨年は大豊作で、一昨年は不作でした。なんだか一年おきみたいになってます。)
全体に小ぶりのようです。LLサイズはあまり無く、Lサイズ、Mサイズが多いようです。(このことは過去の里山だよりにも書いています。)
そんなわけで、結果を言うと今年は不作です。(昨年は大豊作で、一昨年は不作でした。なんだか一年おきみたいになってます。)
全体に小ぶりのようです。LLサイズはあまり無く、Lサイズ、Mサイズが多いようです。(このことは過去の里山だよりにも書いています。)
 不作の原因はおそらく雨が少なかったことでしょう。葉っぱに病気も出てしまいました。(食べるのには何も影響はありません。)
不作の原因はおそらく雨が少なかったことでしょう。葉っぱに病気も出てしまいました。(食べるのには何も影響はありません。)前から「今年はあまり良くないぞ」と思っていましたので、粘って収穫を待ちました。でも、あまり遅くなると芋の表面が汚くなったりします(ぶつぶつができる)し、それに妻が「あまり大きいのよりも小さい方がいいよ。大きいのは中にすが入っていたりするし…」と言ったので収穫することにしました。
それでも収穫かごに4杯分しっかり取れたので、収量は十分です。実はこのジャガイモの収穫が畑づくりの中では一年で一番の楽しみの時であります。すでに何回も掘って食べていますが、味は例年通り、大変おいしいです。先日ピザ会をやりましたが、その時にも芋を掘って(玉ねぎも一緒に)お持ち帰りいただきました。また親戚にあげたり、知人にあげたりもします。皆さんが喜んで下さるのでうれしいです。

 さてそのピザ会ですがこの間の土曜日に行いました。このメンバーでは今年になってから3回目のピザ会です。今までにこのメンバーで何回のピザ会をやったでしょうか。おそらく、20回以上になるのではないでしょうか。
さてそのピザ会ですがこの間の土曜日に行いました。このメンバーでは今年になってから3回目のピザ会です。今までにこのメンバーで何回のピザ会をやったでしょうか。おそらく、20回以上になるのではないでしょうか。もう皆さん慣れたもので、準備から片づけまでさっさとやってくれます。大いに助かります。それにピザを作る人、焼く人(私)、バーベキュー担当の人(牡蠣職人)、ワインソムリエ(バーテンダー)などなど役割が決まっていますので、そういう点でもスムーズです。
毎回わが農園から直送の野菜が料理に並びます。おいしいです。(言うまでもないですが…。)
2017.06.14
「6月」
早いものでもう6月も半ば。あと少しで今年も半分を過ぎようとしています。庭の花も移り変わり、初夏の庭の様相を呈しています。
たまに早めに仕事を終えて、薄暮時にこの庭の東屋(あずまや)の下で一人でビールを飲むことがあります。夕方の気持ち良い時間、車の音も人の声もほとんど聞こえず、聞こえる音と言えば、風が木々を揺らす音と鳥の声ぐらいしかありません。そんな中で丹精した庭と猫を眺めながら飲むビール…これほど美味しいものはありません。
 アジサイのアナベルが咲き始めました。このアジサイはボリュームがあります。昨年剪定をしておいたのですが、それでもこんなに大きくなってしまいました。
アジサイのアナベルが咲き始めました。このアジサイはボリュームがあります。昨年剪定をしておいたのですが、それでもこんなに大きくなってしまいました。
たまに早めに仕事を終えて、薄暮時にこの庭の東屋(あずまや)の下で一人でビールを飲むことがあります。夕方の気持ち良い時間、車の音も人の声もほとんど聞こえず、聞こえる音と言えば、風が木々を揺らす音と鳥の声ぐらいしかありません。そんな中で丹精した庭と猫を眺めながら飲むビール…これほど美味しいものはありません。
 アジサイのアナベルが咲き始めました。このアジサイはボリュームがあります。昨年剪定をしておいたのですが、それでもこんなに大きくなってしまいました。
アジサイのアナベルが咲き始めました。このアジサイはボリュームがあります。昨年剪定をしておいたのですが、それでもこんなに大きくなってしまいました。
 ハーブコーナーも、うっそうと茂ってきています。いろんな種類のミントやレモンバーム、カモミール、ローズマリーなどがびっしり育っています。
ハーブコーナーも、うっそうと茂ってきています。いろんな種類のミントやレモンバーム、カモミール、ローズマリーなどがびっしり育っています。ハーブティーにして飲んだりします。これはベルガモットです。この花が結構好きです。2種類のベルガモットが植えてあります。
 5月の華々しい時期を過ぎて(デルフィニウム、バラ、クレマチス、オルレア、ジギタリス、アヤメやショウブなどの花が終わってしまい)、少しの間庭がさみしい時にがんばってにぎわせてくれたのが、このペンステモンやホタルブクロです。ありがたい花です。丈夫でよく株が増えます。もう終わりに近づいています。ご苦労様。
5月の華々しい時期を過ぎて(デルフィニウム、バラ、クレマチス、オルレア、ジギタリス、アヤメやショウブなどの花が終わってしまい)、少しの間庭がさみしい時にがんばってにぎわせてくれたのが、このペンステモンやホタルブクロです。ありがたい花です。丈夫でよく株が増えます。もう終わりに近づいています。ご苦労様。
 庭の中央に植えてあるシンボルツリーのジューンベリーは、いっぱい実をならせて今まさに取頃です。食べてみるとすごく甘いです(種がありますが)。昨年はほとんど鳥に食べられましたが、今年は鳥も気が付いていない(?)ようです。早くとらなきゃ。
庭の中央に植えてあるシンボルツリーのジューンベリーは、いっぱい実をならせて今まさに取頃です。食べてみるとすごく甘いです(種がありますが)。昨年はほとんど鳥に食べられましたが、今年は鳥も気が付いていない(?)ようです。早くとらなきゃ。
ところで、庭の手入れについて書きます。私は毎朝、毎夕必ず庭を散策(?それほど大げさなものではありませんが…)し、ついでにほとんど必ずやることが2つあります。一つは散水です。1日に1回でいいです。散水(水やり)と簡単に言いますが、誰かが言いました「散水7年」…そのくらい結構散水はコツがいるものらしいです。やりすぎてもいけないし、足りないといけないし…やらなければいけない植物もあればあまりやってはいけない植物もあるし…。今年で5年目の庭です。まだまだです。

 もう一つは枯れた花を(切って)摘むことです。これは大切です。花をたくさん咲かせようと思ったら、とにかくこまめに終わった花を(しかも早めに)摘み取ることです。
もう一つは枯れた花を(切って)摘むことです。これは大切です。花をたくさん咲かせようと思ったら、とにかくこまめに終わった花を(しかも早めに)摘み取ることです。
花は(特にバラなどは)花を切られると防衛本能が働くのか、より一層花を咲かせようと頑張るらしいです。「花は切れ!」これがコツみたいです。

 もう一つは枯れた花を(切って)摘むことです。これは大切です。花をたくさん咲かせようと思ったら、とにかくこまめに終わった花を(しかも早めに)摘み取ることです。
もう一つは枯れた花を(切って)摘むことです。これは大切です。花をたくさん咲かせようと思ったら、とにかくこまめに終わった花を(しかも早めに)摘み取ることです。花は(特にバラなどは)花を切られると防衛本能が働くのか、より一層花を咲かせようと頑張るらしいです。「花は切れ!」これがコツみたいです。
さて工房では「ベニマツのテーブル」も塗装を終わり完成です。「憧れのベニマツの大テーブル」です。天板のサイズは奥行90cm×長さ190cm×天板の厚み45mmぐらい。シンプルな中央脚にカントリーチックな脚の模様!「素敵だな!」と一人悦に入っております。
実は何を隠そうこのテーブル、我が家の住人からのずいぶん以前からの(十数年も前からの)リクエストに応えて作ったものでした。我が家で今使っているテーブルは私がかつて木工所で働いていた時に作ったもので、あまり手作り家具っぽくないものです。天板はある程度数を作ったものの残り物が出たので、それを社長に頼んでいただきましたが、脚部は完全に自分で作ったので愛着があってずっと使ってきたものです。
でも、「いつかはベニマツのテーブルを作る」と言い続けて、ようやく実現したのです。今やこれだけのクオリティーのベニマツのテーブルは、日本広しと言えどもそうそう無いと思います。感無量…。
 今回はさらに特別仕様で、天板の下に物が置けるように簡易的な棚を付けました。着脱可能です。
今回はさらに特別仕様で、天板の下に物が置けるように簡易的な棚を付けました。着脱可能です。
さて、このあとご注文の仕事をこなしながら、我が家のダイニングチェアも作って行きます。新作の椅子になります。2種類考えています。こちらも楽しみです。
でも、「いつかはベニマツのテーブルを作る」と言い続けて、ようやく実現したのです。今やこれだけのクオリティーのベニマツのテーブルは、日本広しと言えどもそうそう無いと思います。感無量…。
 今回はさらに特別仕様で、天板の下に物が置けるように簡易的な棚を付けました。着脱可能です。
今回はさらに特別仕様で、天板の下に物が置けるように簡易的な棚を付けました。着脱可能です。さて、このあとご注文の仕事をこなしながら、我が家のダイニングチェアも作って行きます。新作の椅子になります。2種類考えています。こちらも楽しみです。
2017.06.09
「ベニマツテーブル」
 工房で制作中のベニマツ2枚接ぎのテーブルがほぼ出来上がりました。脚下の部分に飾りを刻みます。ベニマツのような木にはこういう飾り(デザイン)が似合います。際鉋や彫刻刀を使って整形します。
工房で制作中のベニマツ2枚接ぎのテーブルがほぼ出来上がりました。脚下の部分に飾りを刻みます。ベニマツのような木にはこういう飾り(デザイン)が似合います。際鉋や彫刻刀を使って整形します。
 上下のほぞはこんな感じで組み込まれます。シンプルな中央脚と反り止めのみで大きな天板を支える構造ですので、強度の出るほぞ組みを使います。
上下のほぞはこんな感じで組み込まれます。シンプルな中央脚と反り止めのみで大きな天板を支える構造ですので、強度の出るほぞ組みを使います。
 前回の里山だよりの中に「鉋掛けをした後は傷がつかないように、汚れないように大変神経を使って扱うことになります。(やわらかい木ですので、ちょっとのことで傷がついてしまいます。)」と書きましたが、やっぱりやってしまいました。
前回の里山だよりの中に「鉋掛けをした後は傷がつかないように、汚れないように大変神経を使って扱うことになります。(やわらかい木ですので、ちょっとのことで傷がついてしまいます。)」と書きましたが、やっぱりやってしまいました。
さて、いよいよ天板と脚部を合体させます。嵌め合いもきつきつに作ってありますので、少しづつ少しづつ両側を交互に叩き込んでいきます。最後にあり溝の端っこを埋めて仕上げます。
通常テーブルを作る場合、搬入のことを考えて天板と脚部とが分解できるように(現場で組み立てられるように)「ノックダウン式」で作ることがほとんどですが、今回は初めから一体型で作っています。(搬入の心配がないので。)
通常テーブルを作る場合、搬入のことを考えて天板と脚部とが分解できるように(現場で組み立てられるように)「ノックダウン式」で作ることがほとんどですが、今回は初めから一体型で作っています。(搬入の心配がないので。)
久しぶりのベニマツの家具作りでした。なんだかとても楽しかったです。工房を始めたころの気持ちを少し思い出しました。私の家具作りの原点に立ち返ることが出来て、なんだか忘れていたものを思い出したような気持になりました。この気持ち、大切にしたいと思いました。
 話は変わりますが、畑では夏野菜が育っています。ジャガイモはすっかり茎が倒れていて、通常であればもう掘っても良いという合図です。
話は変わりますが、畑では夏野菜が育っています。ジャガイモはすっかり茎が倒れていて、通常であればもう掘っても良いという合図です。
でも、先日来2、3株掘ってみましたがまだ少し早いような感じです。今年はちょっと調子が悪いかも…。でも食べたら、甘くてすごくおいしかったです。味はやはり例年通り、間違いありませんでした。いずれにせよ来週ぐらいには収穫しようかなと考えているところです。
 話は変わりますが、畑では夏野菜が育っています。ジャガイモはすっかり茎が倒れていて、通常であればもう掘っても良いという合図です。
話は変わりますが、畑では夏野菜が育っています。ジャガイモはすっかり茎が倒れていて、通常であればもう掘っても良いという合図です。でも、先日来2、3株掘ってみましたがまだ少し早いような感じです。今年はちょっと調子が悪いかも…。でも食べたら、甘くてすごくおいしかったです。味はやはり例年通り、間違いありませんでした。いずれにせよ来週ぐらいには収穫しようかなと考えているところです。
2017.06.06
「ベニマツ」

 吸い付き桟の加工です。今回はシンプルな脚部デザインにしたので、なおさらのこと精度が必要になってきます。慎重に加工を進めます。
吸い付き桟の加工です。今回はシンプルな脚部デザインにしたので、なおさらのこと精度が必要になってきます。慎重に加工を進めます。
今回はわけあって、この段階で天板の表側も鉋掛けをします。ベニマツを使って家具を作る場合、私は基本的にサンディングをしません。鉋掛けが仕上げとなります。ですから鉋掛けをした後は傷がつかないように、汚れないように大変神経を使って扱うことになります。(やわらかい木ですので、ちょっとのことで傷がついてしまいます。例えば少しゴミをかんだだけでも傷になってしまいます。)
ところでこのベニマツという木ですが、私は大好きな木です。我が家の家具もカップボード、ソファベンチ、サイドテーブル、子どものベッド2台などベニマツで作ってきました。「ベニマツの家具に囲まれて暮らしたい」と思ってきました。そのくらい好きなのです。
やわらかいから傷つきやすいし、木目がきれいだとか面白いわけでもないし、オイルを塗っても濡れ色がつかないから変わり映えがしないし…なのになぜ好きなのかということです。
やわらかいから傷つきやすいし、木目がきれいだとか面白いわけでもないし、オイルを塗っても濡れ色がつかないから変わり映えがしないし…なのになぜ好きなのかということです。

 一つは、完成した時よりも経年変化で徐々に飴色に変化して味わいが深まって行くことです。
一つは、完成した時よりも経年変化で徐々に飴色に変化して味わいが深まって行くことです。完成した時は色白です。それはそれでいいですが、長年使っていくうちにこんな感じに色が深まっていい感じになります。(写真では分かりにくいと思いますが…)
 二つ目は、「松」として優良であるということです。第一にシベリアという寒い大地で育ってきたため、非常に木目が緻密です。また節も非常に少ないです。通常松というと節が多く入っているイメージですが、これだけの大きさの板でもほとんど節が見られません。
二つ目は、「松」として優良であるということです。第一にシベリアという寒い大地で育ってきたため、非常に木目が緻密です。また節も非常に少ないです。通常松というと節が多く入っているイメージですが、これだけの大きさの板でもほとんど節が見られません。第二に松と言えば「ヤニ」があるものですが、このベニマツは大変ヤニが少ないです。あっても部分的に固まっているので、米松などのように板全体からヤニが吹いてくるということがありません。そんな素晴らしい松です。
またこれは制作しているものだけの特権ですが、鉋掛けをしたり切ったりするとすごく良い香りがします。甘いというかバラの香りにも近い良い香りです。制作中は工房にその香りが充満します。そんなわけで、完成するのを自らわくわくしながら作業に向かっています。
<追伸>
本日「ホールベンチ(CHR011)」についてお問い合わせをいただいたN様、メールアドレスが間違っているようで、返信ができません。一度ご確認いただき、再度お問い合わせをいただきますようお願いいたします。
もしくは、携帯の迷惑メール設定が「パソコンからのメールを受信しない」設定になっている可能性がございますので、その場合は設定を解除してくださいますようお願いいたします。
本日「ホールベンチ(CHR011)」についてお問い合わせをいただいたN様、メールアドレスが間違っているようで、返信ができません。一度ご確認いただき、再度お問い合わせをいただきますようお願いいたします。
もしくは、携帯の迷惑メール設定が「パソコンからのメールを受信しない」設定になっている可能性がございますので、その場合は設定を解除してくださいますようお願いいたします。
2017.05.31
「とっておきの…」
 さて、現在はダイニングテーブルの制作に取り掛かっています。材料は長く大事にとっておいた「シベリア産ベニマツ」です。そのベニマツの幅広の板を2枚接ぎ合わせて幅90cm×長さ190cm(板厚4.5~5cm)のダイニングテーブルを作ります。
さて、現在はダイニングテーブルの制作に取り掛かっています。材料は長く大事にとっておいた「シベリア産ベニマツ」です。そのベニマツの幅広の板を2枚接ぎ合わせて幅90cm×長さ190cm(板厚4.5~5cm)のダイニングテーブルを作ります。
実はこの「シベリア産ベニマツ」という木ですが…私が工房を始めた頃から既にそうでしたが、シベリアの動物(アムールトラ)を保護するために伐採は制限されていました。ですから当時から既に入手は困難で、何かの拍子で(たとえば公共事業か何かが行われて?)たまたま伐採されたものが、数少ないですが日本に入ってくるというぐらいでした。しかも、日本では唯一富山港にしか入ってこなかったようでした。
ところが2010年に完全にこのベニマツが伐採禁止となり、新たに丸太を入手することは
出来なくなりました。
 私は工房を始めた当時からこのベニマツという木が大好きで、いずれはこの木で素敵な家具を作りたいと思っていました。(もちろんこれまでにもいくつかは作ってきました。)
私は工房を始めた当時からこのベニマツという木が大好きで、いずれはこの木で素敵な家具を作りたいと思っていました。(もちろんこれまでにもいくつかは作ってきました。)
ですから、私は工房を始めた当初に富山港へ行き、直径60cm級の4m丸太を4本購入しておきました。既に20年の乾燥期間を経ていますので、その点でも完璧です。
そんなわけで、今回そのとっておきのシベリア産ベニマツで2枚接ぎのダイニングテーブルを作るということなんです。先に書きましたが、今回は幅90cm×長さ190cm(板厚4.5~5cm)という大きさのテーブルですが、まだ在庫があり、同じ(それ以上も可能)大きさのテーブルが一つ、さらに厚みが7.5cmという分厚くて幅の広い板もありますので、もっと大きなテーブル(2枚接ぎで)もできます。
ところで、このベニマツという木ですが、それはそれは素晴らしい木です。詳しくはまた次回に書くつもりです。
ところが2010年に完全にこのベニマツが伐採禁止となり、新たに丸太を入手することは
出来なくなりました。
 私は工房を始めた当時からこのベニマツという木が大好きで、いずれはこの木で素敵な家具を作りたいと思っていました。(もちろんこれまでにもいくつかは作ってきました。)
私は工房を始めた当時からこのベニマツという木が大好きで、いずれはこの木で素敵な家具を作りたいと思っていました。(もちろんこれまでにもいくつかは作ってきました。)ですから、私は工房を始めた当初に富山港へ行き、直径60cm級の4m丸太を4本購入しておきました。既に20年の乾燥期間を経ていますので、その点でも完璧です。
そんなわけで、今回そのとっておきのシベリア産ベニマツで2枚接ぎのダイニングテーブルを作るということなんです。先に書きましたが、今回は幅90cm×長さ190cm(板厚4.5~5cm)という大きさのテーブルですが、まだ在庫があり、同じ(それ以上も可能)大きさのテーブルが一つ、さらに厚みが7.5cmという分厚くて幅の広い板もありますので、もっと大きなテーブル(2枚接ぎで)もできます。
ところで、このベニマツという木ですが、それはそれは素晴らしい木です。詳しくはまた次回に書くつもりです。
 話は変わります。先日の日曜日は私も所属している「農事組合法人」の共同作業(草刈り)がありました。法人が管理している広い田んぼを、みんなで一緒に草刈をします。これから秋までに3回ほど行われる予定です。
話は変わります。先日の日曜日は私も所属している「農事組合法人」の共同作業(草刈り)がありました。法人が管理している広い田んぼを、みんなで一緒に草刈をします。これから秋までに3回ほど行われる予定です。日頃はオペレーターにお任せっきりなので、こんな時ぐらいは出ていって作業をします。作業の後はバーベキューで酒盛りとなりました。
 畑では、先日玉ねぎを半分ぐらい収穫しました。今年はまずまずうまく育ったようです。とりたての玉ねぎは辛みも少なくておいしいです。サラダ玉ねぎを薄くスライスして鰹節をかけ、しょうゆをかけて食べるとすごくおいしいです。ビールのつまみにもいいです。
畑では、先日玉ねぎを半分ぐらい収穫しました。今年はまずまずうまく育ったようです。とりたての玉ねぎは辛みも少なくておいしいです。サラダ玉ねぎを薄くスライスして鰹節をかけ、しょうゆをかけて食べるとすごくおいしいです。ビールのつまみにもいいです。
 一方、「jagar's garden」ですが、デルフィニウム、バラ、アヤメなどの華々しい花も終わりを告げようとしております。これからはハーブ、タチアオイ、ホタルブクロ、アジサイ、ダリアなどが順次咲く予定です。
一方、「jagar's garden」ですが、デルフィニウム、バラ、アヤメなどの華々しい花も終わりを告げようとしております。これからはハーブ、タチアオイ、ホタルブクロ、アジサイ、ダリアなどが順次咲く予定です。それにしても一番きれいな時期を過ぎたので、来週25人ほどの見学者を迎える予定ですが満足してもらえるかどうか心配です。
さぁ、せめて草引きぐらいしておかなくては…。
2017.05.22
「久しぶりの…」
5月5日のオープンガーデン以来、我が「jagar's garden」は見学にみえるお客さんが多くなりました。今日もまた電話があり、「来月5日に20人ぐらいで見せていただきに行きます」とのことでした。もちろん大変うれしいことです。恥ずかしいような素人の庭ですが、たくさんの方と交流ができることが楽しいです。
ただ…本当のことを言えば「庭は今が盛りです!」。見に来られるなら今が一番かなという感じです。現在はシャクヤクが盛りで、バラも咲き始め、デルフィニウム、オルレアなどが相変わらず賑やかで、それらを取り囲んで足元にキンセンカや(峠は過ぎましたが)ビオラ、ワスレナグサ、ミヤコワスレなどが咲いています。鉢の寄せ植えもきれいに育ってきました。水回りに植えたアヤメやギボウシも涼しげです。
バラもこれから1週間ちょっとぐらいが見ごろになるでしょう。
 もちろんその後もまた主役がアジサイやハーブなどへと変わっていき、ホタルブクロ、ペンステモン、タチアオイ、ダリアなども咲いて、それはそれで緑濃き夏の庭としての良さを見せてくれるとは思います。ただ、華やかな庭という意味ではやはり今が最盛期ということになるでしょう。
もちろんその後もまた主役がアジサイやハーブなどへと変わっていき、ホタルブクロ、ペンステモン、タチアオイ、ダリアなども咲いて、それはそれで緑濃き夏の庭としての良さを見せてくれるとは思います。ただ、華やかな庭という意味ではやはり今が最盛期ということになるでしょう。
 ところで、久しぶりに「πチェア」を作っています。この椅子は大変手間がかかり、工程が複雑です。それに各工程で「こつ」というものが大事になってくるのです。ですので、長く作っていないとそれらを思い出すのに少し時間がかかったりします。(工程を書くのも大変なので書いてはいません。体と頭に覚えさせています。)
ところで、久しぶりに「πチェア」を作っています。この椅子は大変手間がかかり、工程が複雑です。それに各工程で「こつ」というものが大事になってくるのです。ですので、長く作っていないとそれらを思い出すのに少し時間がかかったりします。(工程を書くのも大変なので書いてはいません。体と頭に覚えさせています。)
以前このホームページに「この椅子(πチェア)のできるまで」というページを作って載せようと思いましたが、あまりにも工程が複雑で多すぎて載せることを断念しました。
そういうわけで今回も何とかようやく完成に近づきました。アームの形が少しづつ出来上がっていきます。
2017.05.15
「畑と庭と…」
前回の里山だよりからずいぶんと時が経ってしまいました。その間いろいろなことがありましたが、工房の周りの風景は相変わらず穏やかに美しく推移しています。
 ゴールデンウィークの初日には畑に夏野菜の苗を植えました。第一農園にはトマト、ナス、スイカ、トウモロコシ、ゴーヤー、ミニメロン、サツマイモ、ズッキーニ、まくわ瓜などを植えておきました。それから2週間ほど経って、現在はこんな感じです。
ゴールデンウィークの初日には畑に夏野菜の苗を植えました。第一農園にはトマト、ナス、スイカ、トウモロコシ、ゴーヤー、ミニメロン、サツマイモ、ズッキーニ、まくわ瓜などを植えておきました。それから2週間ほど経って、現在はこんな感じです。
 ゴールデンウィークの初日には畑に夏野菜の苗を植えました。第一農園にはトマト、ナス、スイカ、トウモロコシ、ゴーヤー、ミニメロン、サツマイモ、ズッキーニ、まくわ瓜などを植えておきました。それから2週間ほど経って、現在はこんな感じです。
ゴールデンウィークの初日には畑に夏野菜の苗を植えました。第一農園にはトマト、ナス、スイカ、トウモロコシ、ゴーヤー、ミニメロン、サツマイモ、ズッキーニ、まくわ瓜などを植えておきました。それから2週間ほど経って、現在はこんな感じです。
 ゴールデンウィークの終わりごろからイチゴも取れ始めました。ただ、猿の襲来に合って3回ほどやられてしまいました。
ゴールデンウィークの終わりごろからイチゴも取れ始めました。ただ、猿の襲来に合って3回ほどやられてしまいました。ですので、この頃は猿に取られる前に早めに取るようにしています。(本当はしっかり熟してから取りたいのですが、それを待っていると猿に取られてしまいそうです。)
 ジャガイモはだいぶん大きくなってきました。すでに花が咲いています。(花は千切って取ってしまいます。)
収穫まではもう少しかかりますが、楽しみです。しかし、隣の畑ではジャガイモも猿に取られたみたいで、心配です。
ジャガイモはだいぶん大きくなってきました。すでに花が咲いています。(花は千切って取ってしまいます。)
収穫まではもう少しかかりますが、楽しみです。しかし、隣の畑ではジャガイモも猿に取られたみたいで、心配です。
 5月3日には県内の垂井町という町の曳山祭りを見に行ってきました。なかなか大した大きな山車(だし)で、すごかったです。全国あちこちに曳山祭りはありますが、山車の上で子どもたちが歌舞伎を演ずるというのは珍しいのではないでしょうか。
5月3日には県内の垂井町という町の曳山祭りを見に行ってきました。なかなか大した大きな山車(だし)で、すごかったです。全国あちこちに曳山祭りはありますが、山車の上で子どもたちが歌舞伎を演ずるというのは珍しいのではないでしょうか。聞けば、この歌舞伎を演ずる子どもたちは2週間前からほとんど学校も休んで練習を繰り返してきたとのことです。(学校は公欠扱いだそうです。)
 そういう伝統が残っているのも今では珍しいでしょう。例えば演目の一つは「一条大蔵」という有名なものでした。これを演ずるのに1時間以上かかります。それをその日場所を変えて6回ほど演ずるのだとか…すごい!もちろん歌舞伎はすごく上手で、大人顔負けでした。それに可愛かったです。
そういう伝統が残っているのも今では珍しいでしょう。例えば演目の一つは「一条大蔵」という有名なものでした。これを演ずるのに1時間以上かかります。それをその日場所を変えて6回ほど演ずるのだとか…すごい!もちろん歌舞伎はすごく上手で、大人顔負けでした。それに可愛かったです。
 前回の里山だよりで少し書きましたが、5日には知り合いの人に声をかけたりして「プチオープンガーデン」をしました。20人ぐらいの人が来て下さり、庭で花を見ながら、ピザも食べて頂いてのんびりと過ごしていただきました。(途中から酒盛りに変わりましたが…)
残念ながら私はピザを焼くのに忙しく写真を一枚も取れませんでした。
前回の里山だよりで少し書きましたが、5日には知り合いの人に声をかけたりして「プチオープンガーデン」をしました。20人ぐらいの人が来て下さり、庭で花を見ながら、ピザも食べて頂いてのんびりと過ごしていただきました。(途中から酒盛りに変わりましたが…)
残念ながら私はピザを焼くのに忙しく写真を一枚も取れませんでした。

 モッコウバラも、ハンカチの木もオープンガーデンに間に合ってくれました。
モッコウバラも、ハンカチの木もオープンガーデンに間に合ってくれました。それから10日ほど経ちますが、盛りを過ぎて散っていくものもあれば新たに花を開くものもあり、日々変化しながら庭をにぎわせてくれています。
これからシャクヤク、バラ、クレマチス、アヤメやショウブ、そしてアジサイというように主役が次から次へと変わっていきます。楽しみはまだまだ続きます。以下、庭の様子です。
2017.04.19
「ちょこっと ~jagar's gardenオープン~」

 数日前までは満開に咲き誇っていた裏手の桜もそろそろ散り始め、葉桜となりつつあります。
数日前までは満開に咲き誇っていた裏手の桜もそろそろ散り始め、葉桜となりつつあります。この間当工房へお出で頂いたお客様にもこの桜の美しさを堪能していただくことが出来ました。
先日の土曜日には今年第2回目のピザ会を開催しました。久しぶりのメンバーが集まり、楽しく盛り上がりました。
畑ではイチゴやジャガイモが順調に育っています。ジャガイモの方は第1回目の追肥、土寄せをしておきました。また、再来週ぐらいには夏野菜の苗を植える予定なので、畑に牛糞堆肥を混ぜて起こしておきました。
 工房では犬山市のお客様のウォールナット2枚接ぎこたつ座卓が塗装に入っています。現在は山口県周南市のお客様の本立てと大阪市のお客様の桜のπチェアの制作に入りました。
工房では犬山市のお客様のウォールナット2枚接ぎこたつ座卓が塗装に入っています。現在は山口県周南市のお客様の本立てと大阪市のお客様の桜のπチェアの制作に入りました。…ところで、こっそりと告知をします。来るゴールデンウィークの5月5日、「プチオープンガーデン(ついでにオープン工房)」をします。
庭づくりを始めて5年目になります。まだまだ胸を張ってお見せできるような庭ではありませんが、知り合いの奥様の「いいのよ、そんな立派な庭でなくても!むしろあんまり立派すぎない庭の方がいいのよ!」という声に勇気づけられて、ちょこっとオープンガーデンをすることにします。ですから、周りの景色も雑草も含めて我が庭だということで…。(汗) まぁ静かな里でしばしのんびりした時間を味わっていただければいいかなと…。

 現在はこんな感じです。
現在はこんな感じです。
庭を見て頂くことがメインですが、ピザ窯でピザも焼いて少しお出ししようかと考えています。とにかく今年はひっそりと、近隣の知人や友人に声をかけてお誘いしようかと考えています。そんなわけで、もし他にもお越しいただける方があれば、前もってメール、電話などでご連絡いただけるとありがたいです。
もちろん5月5日だけでなく、当工房自体はいつでもご来房大歓迎です。ただし、ゴールデンウィーク中は5月3日(水)のみお休みとさせていただきます。よろしくお願いします。
「まだまだ5年目ですが… ~jagar's garden プチオープンガーデン~」
日時: 5月5日(金) 10:30~16:00 ※ピザ試食はお昼頃(量に限りはあります)
場所: 半布里工房 jagar's garden
日時: 5月5日(金) 10:30~16:00 ※ピザ試食はお昼頃(量に限りはあります)
場所: 半布里工房 jagar's garden
もちろん5月5日だけでなく、当工房自体はいつでもご来房大歓迎です。ただし、ゴールデンウィーク中は5月3日(水)のみお休みとさせていただきます。よろしくお願いします。
2017.04.04
「春先」
 工房の周りにも少しづつ春の花が咲き始めました。4月に入り、いよいよ春だなという感じです。
工房の周りにも少しづつ春の花が咲き始めました。4月に入り、いよいよ春だなという感じです。まずはスイセンなどの球根植物がいろいろ出そろい始めました。アネモネが咲き、チューリップももう少しで咲きそうです。クリスマスローズも盛りを迎えています。

 畑ではエンドウがすくすく育っています。以前書きましたが、ほとんど全部猿にかじられてしまった玉ねぎも、元気に生き延びて大きく育っています。
畑ではエンドウがすくすく育っています。以前書きましたが、ほとんど全部猿にかじられてしまった玉ねぎも、元気に生き延びて大きく育っています。
 大根やカブはすでに終末を迎え、花が咲き始めています。それでも大根は下半分ぐらいはまだ食べれます。例年は大半を捨ててしまいますが、今年は近所で鶏を飼い始めた人がみえるので餌として差し上げています。
大根やカブはすでに終末を迎え、花が咲き始めています。それでも大根は下半分ぐらいはまだ食べれます。例年は大半を捨ててしまいますが、今年は近所で鶏を飼い始めた人がみえるので餌として差し上げています。これで、もったいないことをしないで済みます。そのお返しと言って、その鶏が産んだ卵をいただきました。おいしくいただきました。
2017.03.15
「小物作り」
 きれいに草引きをした後で、玉ねぎは猿にもう食べられないように、覆いをかけておきました。そして全体を管理機で起こしておきました。これも草対策です。
きれいに草引きをした後で、玉ねぎは猿にもう食べられないように、覆いをかけておきました。そして全体を管理機で起こしておきました。これも草対策です。
少し暖かくなってきて、庭ではクロッカス、アネモネなどが咲きだしました。庭のあちらこちらに植えたチューリップもたくさん芽を出しています。

 千切り(チギリ)の加工です。治具を使ってトリマーで穴を掘り、ノミで隅をきれいに仕上げます。
千切り(チギリ)の加工です。治具を使ってトリマーで穴を掘り、ノミで隅をきれいに仕上げます。
裏側の縁を斜めにカットします。赤い線は削るときの目印です。昇降盤という機械で大まかにカットした後、鉋で削ります。
2017.03.08
「結婚記念日」
 二十数年目の結婚記念日でした。いつもは特に何もしないのですが、急に「おいしいものでも食べに行こうか」と言って家族で近くの鰻屋さんへ行き、「ひつまぶし」を食べました。
二十数年目の結婚記念日でした。いつもは特に何もしないのですが、急に「おいしいものでも食べに行こうか」と言って家族で近くの鰻屋さんへ行き、「ひつまぶし」を食べました。このお店のオーナーは名古屋の名店「蓬莱軒」で修業をされた方ということです。おいしかったです。
さて前回の里山だよりからちょっと日が空いてしまいましたが、制作中だった学習机セット2セットもほぼ完成となりました。
 以下、制作の様子をまとめて一挙出しです。前回「気が遠くなりそうです」と書いた12杯の引き出しの「天秤差し(蟻組み)」加工です。
以下、制作の様子をまとめて一挙出しです。前回「気が遠くなりそうです」と書いた12杯の引き出しの「天秤差し(蟻組み)」加工です。
のこぎりでコツコツと挽き込み作業をします。12杯分すべての部材の挽き込み回数は、おそらく1000以上になるのではないでしょうか。さすがに肩がちょっと疲れました。
 以下、制作の様子をまとめて一挙出しです。前回「気が遠くなりそうです」と書いた12杯の引き出しの「天秤差し(蟻組み)」加工です。
以下、制作の様子をまとめて一挙出しです。前回「気が遠くなりそうです」と書いた12杯の引き出しの「天秤差し(蟻組み)」加工です。のこぎりでコツコツと挽き込み作業をします。12杯分すべての部材の挽き込み回数は、おそらく1000以上になるのではないでしょうか。さすがに肩がちょっと疲れました。
ノミ作業です。同じ姿勢(作業台の上に乗り、腰を少しかがめたような姿勢)で延々何時間(何十時間?)も続けると、本当に腰が痛くなります。作業台の下には格闘の跡が…。

 1昼夜置いて、ボンドが固まったら削って仕上げ、仕込みを行います。
1昼夜置いて、ボンドが固まったら削って仕上げ、仕込みを行います。
 裏側(側板と向う板との組み合わせ部)は、いつもと同じように「あられ組み」です。
裏側(側板と向う板との組み合わせ部)は、いつもと同じように「あられ組み」です。
本立ても完成しました。蟻組みの部分には当て木を当ててクランプで締めますが、当て木にもちょっとした工夫が必要です。
2017.02.24
「時代おくれの新しさ」

 一昨日飛騨市の材木店と電話で話をしていたら、また40cmも雪が降ったとのことでびっくりしました。高山に住んでいた頃のことを思い出しました。
一昨日飛騨市の材木店と電話で話をしていたら、また40cmも雪が降ったとのことでびっくりしました。高山に住んでいた頃のことを思い出しました。当地ではチューリップや球根植物が地面からむっくりと芽を出し、クロッカスもきれいに咲きだして、いよいよ春間近という感じです。
先日、何気なしにNHKにチャンネルを回したら「阿久 悠」を放送してました。既にエンディングに近かったのでちゃんと見たわけではありませんが、阿久
悠さんの書いた詩に目が留まりました。
1998年に明治大学の卒業式で学生に送られた詩だそうです。わたし、結構「パス」してます。
 さて工房では学習机セットのデスクサイドチェストの制作中です。部材の加工と仕上げ、部分組立てが済み本組み立てとなりますが、その前に後からでは塗装がしにくくなる内部の部分だけあらかじめ塗装をしておきます。
さて工房では学習机セットのデスクサイドチェストの制作中です。部材の加工と仕上げ、部分組立てが済み本組み立てとなりますが、その前に後からでは塗装がしにくくなる内部の部分だけあらかじめ塗装をしておきます。
時代おくれの新しさ
時代に遅れないように
というのがモットーで
そればかり考えて来たが
近頃になって
どうしたら上手に
時代に遅れられるだろうかと
懸命に考えている
時代という不確かなものが
まるで被害妄想のように
お色直しをくり返しているが
ずっとそれにつき合っていては
ぼくらは風邪をひいてしまうし
また
折角着たものに馴染むひまもない
だからといって
時代ばなれでいいわけではなく
走りまわる時代を
きちんと見つめながら
「勝手にジタバタしなさいよ」
ぐらいのことは言っていい段階
ということである
変わらなくてもいい変化
不必要な新しさ
人間を馬鹿にした進歩
それらを正確により分け
すぐに腐る種類の新しさや
単なる焦りからの変化には
「パス」
と叫んでも悪くない
しかし
そのためには
新しがるよりもっと正確に
時代の知識が必要になる
一歩先へ行って
時代遅れを選択する
やっぱり
幸福を考えたいから
時代に遅れないように
というのがモットーで
そればかり考えて来たが
近頃になって
どうしたら上手に
時代に遅れられるだろうかと
懸命に考えている
時代という不確かなものが
まるで被害妄想のように
お色直しをくり返しているが
ずっとそれにつき合っていては
ぼくらは風邪をひいてしまうし
また
折角着たものに馴染むひまもない
だからといって
時代ばなれでいいわけではなく
走りまわる時代を
きちんと見つめながら
「勝手にジタバタしなさいよ」
ぐらいのことは言っていい段階
ということである
変わらなくてもいい変化
不必要な新しさ
人間を馬鹿にした進歩
それらを正確により分け
すぐに腐る種類の新しさや
単なる焦りからの変化には
「パス」
と叫んでも悪くない
しかし
そのためには
新しがるよりもっと正確に
時代の知識が必要になる
一歩先へ行って
時代遅れを選択する
やっぱり
幸福を考えたいから
1998年に明治大学の卒業式で学生に送られた詩だそうです。わたし、結構「パス」してます。
 さて工房では学習机セットのデスクサイドチェストの制作中です。部材の加工と仕上げ、部分組立てが済み本組み立てとなりますが、その前に後からでは塗装がしにくくなる内部の部分だけあらかじめ塗装をしておきます。
さて工房では学習机セットのデスクサイドチェストの制作中です。部材の加工と仕上げ、部分組立てが済み本組み立てとなりますが、その前に後からでは塗装がしにくくなる内部の部分だけあらかじめ塗装をしておきます。
 これからいよいよ引き出しの制作に入ります。机の分も合わせて2セット分12杯の引き出しです。すべてに「天秤差し(蟻組み)」加工をします。気が遠くなりそうです(笑)
これからいよいよ引き出しの制作に入ります。机の分も合わせて2セット分12杯の引き出しです。すべてに「天秤差し(蟻組み)」加工をします。気が遠くなりそうです(笑)
2017.02.17
「ジャガイモの植えつけ」
今年は暖冬だと思っていたのに全くさにあらず、1ヶ月ほどずっと寒い日が続きました。工房の薪ストーブは近年では一番の稼働状態で、在庫の薪(端材、残材のストック)のストックも乏しくなってきました。今日もしとしと雨が降って寒いので薪ストーブを焚いて仕事をしています。
でも、そろそろ暖かくなってくるでしょう。畑や野山の草花が伸び始めており、春の気配を感じさせます。
 ジャガイモの種イモの植えつけはまだ先とのんびり構えていたのですが、たまたまJAから買っておいた種イモを見てみたらもうすでに芽が出始めていました。これはいけないということで急遽畑を準備して植え付けをしました。
ジャガイモの種イモの植えつけはまだ先とのんびり構えていたのですが、たまたまJAから買っておいた種イモを見てみたらもうすでに芽が出始めていました。これはいけないということで急遽畑を準備して植え付けをしました。
詳しいことは過去の里山だより(2010年3月16日と2013年3月6日)にも書いてあるのでそちらをご覧いただければと思いますが、今年も例年通り男爵の種イモを7列(約140個ほど)と、新たにお店が薦めてくれた十勝黄金という種類の種イモを1列(20個ほど)植えました。これで1年分の我が家のじゃがいもになります。
先にも書いたように種イモがもう芽を出し始めていたのでこんなに早くなってしまっただけで、もっと後の方が良いと思うのですが…仕方ありません。芋の都合です。心配なのは早く植えすぎると「晩霜」にやられちゃうんじゃないかということです。気を付けなければいけません。
さて、制作中の学習机セット2セットの方は、デスクサイドチェストの加工に入っています。

 机の方は天板裏の吸い付き桟の加工を終え、整形と仕上げをして完成しています。
机の方は天板裏の吸い付き桟の加工を終え、整形と仕上げをして完成しています。
でも、そろそろ暖かくなってくるでしょう。畑や野山の草花が伸び始めており、春の気配を感じさせます。
 ジャガイモの種イモの植えつけはまだ先とのんびり構えていたのですが、たまたまJAから買っておいた種イモを見てみたらもうすでに芽が出始めていました。これはいけないということで急遽畑を準備して植え付けをしました。
ジャガイモの種イモの植えつけはまだ先とのんびり構えていたのですが、たまたまJAから買っておいた種イモを見てみたらもうすでに芽が出始めていました。これはいけないということで急遽畑を準備して植え付けをしました。詳しいことは過去の里山だより(2010年3月16日と2013年3月6日)にも書いてあるのでそちらをご覧いただければと思いますが、今年も例年通り男爵の種イモを7列(約140個ほど)と、新たにお店が薦めてくれた十勝黄金という種類の種イモを1列(20個ほど)植えました。これで1年分の我が家のじゃがいもになります。
先にも書いたように種イモがもう芽を出し始めていたのでこんなに早くなってしまっただけで、もっと後の方が良いと思うのですが…仕方ありません。芋の都合です。心配なのは早く植えすぎると「晩霜」にやられちゃうんじゃないかということです。気を付けなければいけません。
さて、制作中の学習机セット2セットの方は、デスクサイドチェストの加工に入っています。

 机の方は天板裏の吸い付き桟の加工を終え、整形と仕上げをして完成しています。
机の方は天板裏の吸い付き桟の加工を終え、整形と仕上げをして完成しています。
2017.02.10
「復活」
先週の火曜日頃からのどが痛く、鼻水が出るのでおかしいなと思っていました。それでも熱は無いので普通に仕事もしていましたが、どんどんそれがひどくなってきたので、医者へ行きました。しかし、普通の風邪と診断され薬を出されましたので、それを飲んで過ごしていましたが…一向に治りません。
そんな時に息子がやはり医者へ行き、「インフルエンザやった」と言って帰ってきました。木曜日のことです。次の日、自分も心配になって医者に聞きましたが、「熱が出ないと検査をしても無駄ですよ」と言われ、結局そのままにしていましたが症状はひどくなる一方で…からだもだるく、金曜日、土曜日と仕事になりませんでした。
そして、ついに日曜日になって熱が高くなってきました。「やはり」ということで「休日診療」に行きました。しかし、検査の結果は陰性で、一応その時点ではインフルエンザとは診断されませんでしたが、医者に「どうしますか?」と聞かれたので「状況から考えてインフルエンザの可能性が高いと思いますし、今服用している薬は一向に効かないのでインフルエンザの薬をください」と頼みました。(結局自分で診断を下したみたいな格好になりました。)
そして日曜日、月曜日と完全に休養して寝ていました。熱も高くなり汗もすごくかきました。ようやく火曜日ぐらいから仕事を開始しましたが、火曜日はさすがにまだえらかったので、早めに終わりました。そして水曜日ぐらいから何とか仕事に復帰したという感じです。結局先週の火曜日から1週間ぐらい風邪にやられていたという感じになります。
家内の実家の方の言い伝えにこんな言葉があります。
実は私は先週の火曜日に床屋にカットに行きました。最近髪の毛が伸びすぎて、うっとおしいなと思っていたところでした。そしたら風邪をひきました。これは偶然でしょうか?ほかにも面白い言い伝えはいっぱいあります。また今度書きます。
そんな時に息子がやはり医者へ行き、「インフルエンザやった」と言って帰ってきました。木曜日のことです。次の日、自分も心配になって医者に聞きましたが、「熱が出ないと検査をしても無駄ですよ」と言われ、結局そのままにしていましたが症状はひどくなる一方で…からだもだるく、金曜日、土曜日と仕事になりませんでした。
そして、ついに日曜日になって熱が高くなってきました。「やはり」ということで「休日診療」に行きました。しかし、検査の結果は陰性で、一応その時点ではインフルエンザとは診断されませんでしたが、医者に「どうしますか?」と聞かれたので「状況から考えてインフルエンザの可能性が高いと思いますし、今服用している薬は一向に効かないのでインフルエンザの薬をください」と頼みました。(結局自分で診断を下したみたいな格好になりました。)
そして日曜日、月曜日と完全に休養して寝ていました。熱も高くなり汗もすごくかきました。ようやく火曜日ぐらいから仕事を開始しましたが、火曜日はさすがにまだえらかったので、早めに終わりました。そして水曜日ぐらいから何とか仕事に復帰したという感じです。結局先週の火曜日から1週間ぐらい風邪にやられていたという感じになります。
家内の実家の方の言い伝えにこんな言葉があります。
髪の毛がのびると風邪をひく
実は私は先週の火曜日に床屋にカットに行きました。最近髪の毛が伸びすぎて、うっとおしいなと思っていたところでした。そしたら風邪をひきました。これは偶然でしょうか?ほかにも面白い言い伝えはいっぱいあります。また今度書きます。
2017.01.27
「ルーティーン」
誰にでも何がしか「ルーティーン」というのはあるものでしょう。私の場合、朝の日課は大体決まっています。「朝はパン」…なんかCMで聞いたようなフレーズですが、これはもう大学時代から変わりません。
学生の時2年ほど住んでいた学生寮の朝食は、決まって「トーストとキャベツに目玉焼き」でした。1年365日変わらずでした。その寮には留学生のアメリカ人もいて、その人たちはなぜか目玉焼きが2個だったのがうらやましかったことを思い出します。(考えてみたら完全に差別ですよね。アメリカ人は体が大きいからだとかナントカ…テキトウなことをおばちゃんは言ってました。) とにかくその時からずっと「朝はパン」です。
 工房へは朝7時ごろ入ります。工房に入るとこの時期はまずストーブに火をつけることから始まります。このところずっと寒い日が続いているので、薪ストーブが欠かせません。写真の左側のおが屑ストーブの方は最近ちょっと出番が少なくなっています。(薪ストーブと比べるとやはり火力が落ちるからです。)
工房へは朝7時ごろ入ります。工房に入るとこの時期はまずストーブに火をつけることから始まります。このところずっと寒い日が続いているので、薪ストーブが欠かせません。写真の左側のおが屑ストーブの方は最近ちょっと出番が少なくなっています。(薪ストーブと比べるとやはり火力が落ちるからです。)
学生の時2年ほど住んでいた学生寮の朝食は、決まって「トーストとキャベツに目玉焼き」でした。1年365日変わらずでした。その寮には留学生のアメリカ人もいて、その人たちはなぜか目玉焼きが2個だったのがうらやましかったことを思い出します。(考えてみたら完全に差別ですよね。アメリカ人は体が大きいからだとかナントカ…テキトウなことをおばちゃんは言ってました。) とにかくその時からずっと「朝はパン」です。
 工房へは朝7時ごろ入ります。工房に入るとこの時期はまずストーブに火をつけることから始まります。このところずっと寒い日が続いているので、薪ストーブが欠かせません。写真の左側のおが屑ストーブの方は最近ちょっと出番が少なくなっています。(薪ストーブと比べるとやはり火力が落ちるからです。)
工房へは朝7時ごろ入ります。工房に入るとこの時期はまずストーブに火をつけることから始まります。このところずっと寒い日が続いているので、薪ストーブが欠かせません。写真の左側のおが屑ストーブの方は最近ちょっと出番が少なくなっています。(薪ストーブと比べるとやはり火力が落ちるからです。)
誰にで 薪(日頃家具作りで出る端材、残材です)は別の物置の方にストックしてあるので、そちらから持って来ます。今年は結構使いました。あと残りは20数袋となっています。このまま寒い日が1ヶ月も続くと無くなってしまいそうです。まぁ、おが屑ストーブと両方をうまく使いながらやっていきます。
薪(日頃家具作りで出る端材、残材です)は別の物置の方にストックしてあるので、そちらから持って来ます。今年は結構使いました。あと残りは20数袋となっています。このまま寒い日が1ヶ月も続くと無くなってしまいそうです。まぁ、おが屑ストーブと両方をうまく使いながらやっていきます。
 薪(日頃家具作りで出る端材、残材です)は別の物置の方にストックしてあるので、そちらから持って来ます。今年は結構使いました。あと残りは20数袋となっています。このまま寒い日が1ヶ月も続くと無くなってしまいそうです。まぁ、おが屑ストーブと両方をうまく使いながらやっていきます。
薪(日頃家具作りで出る端材、残材です)は別の物置の方にストックしてあるので、そちらから持って来ます。今年は結構使いました。あと残りは20数袋となっています。このまま寒い日が1ヶ月も続くと無くなってしまいそうです。まぁ、おが屑ストーブと両方をうまく使いながらやっていきます。

 さて前回書いた小物の制作です。まずは「小箱」。底板を張って全体を鉋掛けしてから上蓋と底とに2つにカットします。その後で内枠を取り付けます。
さて前回書いた小物の制作です。まずは「小箱」。底板を張って全体を鉋掛けしてから上蓋と底とに2つにカットします。その後で内枠を取り付けます。

 次に裏側を削っていきます。裏側の中心には丸いつかみの穴を作り、外側を丸めて削っていきます。そして、最後はサンドペーパーをあてて滑らかに仕上げていきます。
次に裏側を削っていきます。裏側の中心には丸いつかみの穴を作り、外側を丸めて削っていきます。そして、最後はサンドペーパーをあてて滑らかに仕上げていきます。この後、ひっくり返して表側の整形をしていくのです。(まぁ、ぼちぼちやっていくことにします。)
なんだか端折って(はしょって)書きましたが、細かいことを言えばここまででも結構な手間になります。私はこれは本業ではなくあくまでも端材、残材がもったいないので作っているというくらいですから…あまり売るつもりは無いです。またどうせ誰かに分けてあげたりしちゃうのでしょう。
でも、つくづく思いました。これを本業としてやっていくなら、何はともあれ「スピード」命だなと。
でも、つくづく思いました。これを本業としてやっていくなら、何はともあれ「スピード」命だなと。
2017.01.23
「小物、小物…」

 庭のロウバイが黄色い可愛らしい花を咲かせています。少しだけ手折って玄関やトイレの中の一輪挿しに挿してみました。すると周りにすごく良い香りが広がりました。ロウバイの香りっていいものですね。
庭のロウバイが黄色い可愛らしい花を咲かせています。少しだけ手折って玄関やトイレの中の一輪挿しに挿してみました。すると周りにすごく良い香りが広がりました。ロウバイの香りっていいものですね。この間工房でネジなどの金物を整理にかかったところ、結構大変な手間になってしまいました。
2017.01.16
「再び、学習机のこと」

 前回の里山だよりで「暖冬」と書いたとたんに大雪です。ここ数日は我が里も雪に埋もれました。天をそしる(謗る)とこういうことになります。
前回の里山だよりで「暖冬」と書いたとたんに大雪です。ここ数日は我が里も雪に埋もれました。天をそしる(謗る)とこういうことになります。全国各地の様子を見るとそれはそれは大変な被害のようでお気の毒ですが、当地はせいぜい5cm~10cmほどの積雪でしたので大したことはありませんでした。
そんな中お友達がみえたので、雪の中から野菜を掘り出して少しおすそ分けをしました。ついでに焼き芋もしてあげました。今年は以前ビニールハウスの中に掘って作ったサツマイモ保存用の穴がいい具合で、大活躍です。
 私の制作スタイルではいわゆる「作り置き」というのはほとんどしません。(理由はポリシーやら仕事の内容にかかわることなので、このことはいずれまた書くつもりです。)
私の制作スタイルではいわゆる「作り置き」というのはほとんどしません。(理由はポリシーやら仕事の内容にかかわることなので、このことはいずれまた書くつもりです。)しかし、物によっては話が違ってきて、引き出しのつまみやら、ストッパーなど(ほかに「千切り」などもそうですが)は一度にたくさん作っておきます。
そして本体の塗装にも入り、いよいよ最後のアイテムである「KOSI-KAKE」の制作に取り掛かります。
ところで…今年も何人ものお客様から年賀状(メールの年賀状もありました)をいただきましたが、その中に以前学習机を作って差し上げたお子さんからの年賀状もありました。
一人の方はすでに中学生ですので、7年ほど前に作らせていただいたことになります。この女の子からは毎年年賀状を頂きます。勉強を頑張っていることやお稽古事のフィギュアスケートを頑張っていること。昨年は中学受験の勉強に一生懸命なことが書かれていたり、今年は無事(私立)中学に合格した喜びも書かれていました。そしてその中学で部活や勉強にも一生懸命取り組んでいる様子が(もちろん写真入りで)書かれていました。
そして、現在制作中のご注文主であるお子さんからは完成を楽しみにしていること、そのお姉さん(2年前に同じように制作させていただきました)からも勉強を頑張っていることが書き添えてありました。
どの方のお便りももちろん嬉しく、一介の家具屋に年賀状をいただけること自体本当にありがたいことだと感じていますが、お子さんから頂くこうした年賀状もまた嬉しいものです。
以前書いたと思いますが、学習机は私にとってはやはり特別な家具であることに変わりはありません。引き出しの「天秤差し(蟻組み)」加工や天板の「吸い付き桟」加工など、学習机というアイテムに対しては他のメーカー(工房)ではあまりやっていないことだと思います。
結構手間がかかることなので、時には正直言って「大変だなあ」と感じることもあります。しかし、この学習机の向こう側にご注文主となるお子さんの姿を思い浮かべると、「いかん、いかん、頑張らなくっちゃ!」という気になるのであります。そういう気持ちを後押ししてくれるのが、上に書いたようなお子さんからの手紙であったり、納品時に見せてくれるお子さんの素直な喜びであったりするのです。
ところで…今年も何人ものお客様から年賀状(メールの年賀状もありました)をいただきましたが、その中に以前学習机を作って差し上げたお子さんからの年賀状もありました。
一人の方はすでに中学生ですので、7年ほど前に作らせていただいたことになります。この女の子からは毎年年賀状を頂きます。勉強を頑張っていることやお稽古事のフィギュアスケートを頑張っていること。昨年は中学受験の勉強に一生懸命なことが書かれていたり、今年は無事(私立)中学に合格した喜びも書かれていました。そしてその中学で部活や勉強にも一生懸命取り組んでいる様子が(もちろん写真入りで)書かれていました。
そして、現在制作中のご注文主であるお子さんからは完成を楽しみにしていること、そのお姉さん(2年前に同じように制作させていただきました)からも勉強を頑張っていることが書き添えてありました。
どの方のお便りももちろん嬉しく、一介の家具屋に年賀状をいただけること自体本当にありがたいことだと感じていますが、お子さんから頂くこうした年賀状もまた嬉しいものです。
以前書いたと思いますが、学習机は私にとってはやはり特別な家具であることに変わりはありません。引き出しの「天秤差し(蟻組み)」加工や天板の「吸い付き桟」加工など、学習机というアイテムに対しては他のメーカー(工房)ではあまりやっていないことだと思います。
結構手間がかかることなので、時には正直言って「大変だなあ」と感じることもあります。しかし、この学習机の向こう側にご注文主となるお子さんの姿を思い浮かべると、「いかん、いかん、頑張らなくっちゃ!」という気になるのであります。そういう気持ちを後押ししてくれるのが、上に書いたようなお子さんからの手紙であったり、納品時に見せてくれるお子さんの素直な喜びであったりするのです。
うちの場合は学習机もリピーターのお客様からのご注文であることが多いので、年間にそれほど多く作っているわけではありませんが、一つ一つ精一杯作らせていただいているのであります。
2017.01.10
「暖冬」
新年は1日から工房に入り、年末にやり残した片づけや整理をして過ごし、3日から本格的に仕事を開始いたしました。
 まずは年末から続いている北名古屋市のお客様の学習机セットの制作です。学習机とデスク下ワゴンの本体と本立てはすでに完成し、塗装を待っています。
まずは年末から続いている北名古屋市のお客様の学習机セットの制作です。学習机とデスク下ワゴンの本体と本立てはすでに完成し、塗装を待っています。
 まずは年末から続いている北名古屋市のお客様の学習机セットの制作です。学習机とデスク下ワゴンの本体と本立てはすでに完成し、塗装を待っています。
まずは年末から続いている北名古屋市のお客様の学習机セットの制作です。学習机とデスク下ワゴンの本体と本立てはすでに完成し、塗装を待っています。

 現在は引き出しの加工に入っています。例によって「天秤差し(蟻組み)」の加工です。
現在は引き出しの加工に入っています。例によって「天秤差し(蟻組み)」の加工です。
ところで…今までにどれだけの蟻組み(天秤差しを含む)加工をしてきたことだろう。数え切れませんが、引き出しだけでもおそらく優に100杯以上、大きな箱物本体の蟻組み(留形隠し蟻組みも含め)も40か所以上は作ってきたと思います。
 うちの場合は言うまでもなく、それをすべて手加工でやることにしています。ですから、やはり常にこれをやっていないと勘は鈍ってくるものと思いますが、ありがたいことに年に何回かはこの加工をする機会をお客様から頂いているので、一応腕が鈍るということは無いようです。
うちの場合は言うまでもなく、それをすべて手加工でやることにしています。ですから、やはり常にこれをやっていないと勘は鈍ってくるものと思いますが、ありがたいことに年に何回かはこの加工をする機会をお客様から頂いているので、一応腕が鈍るということは無いようです。
この引き出しの加工と仕込が終わると、次はKOSI-KAKEの制作に入っていきます。M様、もう少しです。
 うちの場合は言うまでもなく、それをすべて手加工でやることにしています。ですから、やはり常にこれをやっていないと勘は鈍ってくるものと思いますが、ありがたいことに年に何回かはこの加工をする機会をお客様から頂いているので、一応腕が鈍るということは無いようです。
うちの場合は言うまでもなく、それをすべて手加工でやることにしています。ですから、やはり常にこれをやっていないと勘は鈍ってくるものと思いますが、ありがたいことに年に何回かはこの加工をする機会をお客様から頂いているので、一応腕が鈍るということは無いようです。この引き出しの加工と仕込が終わると、次はKOSI-KAKEの制作に入っていきます。M様、もう少しです。

 話は変わり…暖冬です。当地では今年はまだ本格的な雪が降っていません。それどころか寒中だというのに春の気配を感じるぐらい暖かいです。
話は変わり…暖冬です。当地では今年はまだ本格的な雪が降っていません。それどころか寒中だというのに春の気配を感じるぐらい暖かいです。イチゴは昨年のうちから花を咲かせてしまっています。もちろんこの花が甘いイチゴになるはずもないので千切って取っています。ナバナもすでに花を咲かせ始めています。

 庭でもスイセンやデルフィニウムが花を咲かせています。デルフィニウムが開花していることを話したら園芸店の店員さんもびっくりしていました。
庭でもスイセンやデルフィニウムが花を咲かせています。デルフィニウムが開花していることを話したら園芸店の店員さんもびっくりしていました。しかし、これも良いわけがありません。普通なら今はまだ地上部は枯れてしまっているようでなければいけません。
 白菜も例年なら凍みるのを防ぐために上部をしばっておいたりするのですが、今年は全くそんなことをする必要がありません。おかしいです。エンドウや玉ねぎは順調に育っています。でも、やはりもっと寒くならないと野菜はうまく育たないだろうと思います。
白菜も例年なら凍みるのを防ぐために上部をしばっておいたりするのですが、今年は全くそんなことをする必要がありません。おかしいです。エンドウや玉ねぎは順調に育っています。でも、やはりもっと寒くならないと野菜はうまく育たないだろうと思います。
さて冬の楽しみの一つは工房の薪ストーブです。薪ストーブに火をくべると穏やかな気持ちになります。そして薪ストーブで焼き芋をしたり、お餅を焼いたりして食べるとすごくおいしいです。べにはるかや安納芋の焼き芋です。どちらも甘くておいしいですが、べにはるかの方が異常に甘くておいしいです。
2017.01.01
「年始のあいさつ」
先日、知り合いの方が「佐藤さんオープンガーデンはやらないの?」と言われました。庭づくりを初めて4年…そろそろかな?果たして実現や如何に?(私次第ですね) そんな時は当然オープン工房も同時に行います。(こっちの方が大事?)