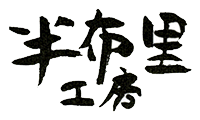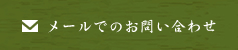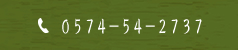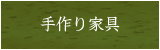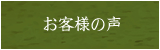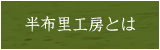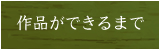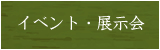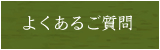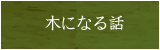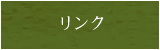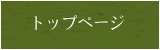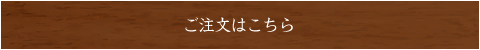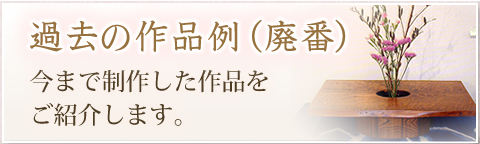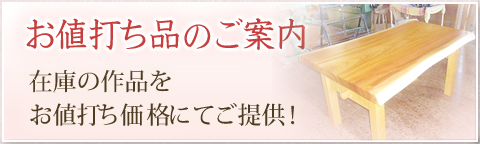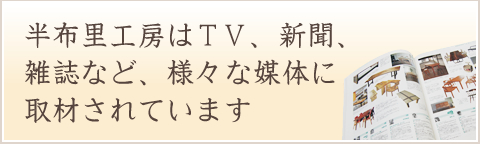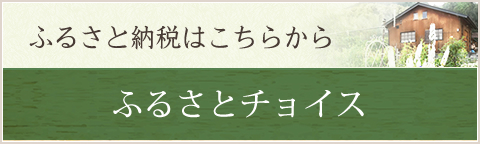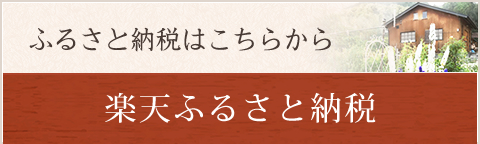- トップページ
- 里山便り2022
「年末の挨拶」
2022.12.26
「木工体験 カッティングボードを作ろう!」
2022.12.19
一昨日の土曜日、木工体験「世界に一つ 自分だけのカッティングボードを作ろう!」というイベントを開催しました。一言で言って、夢中で楽しく終わることができました。結構がっつり「木工」をしていただいたのですが、皆さんよく頑張りました。
今回は2組4名の方に参加していただき、朝9時過ぎから、途中昼食タイムをはさんで午後2時過ぎまでみっちりやっていただきました。
 まずは好きな板を選びます。あらかじめ用意した中からいろいろ迷ってみえましたが、お気に入りの板を選んでいただきました。
まずは好きな板を選びます。あらかじめ用意した中からいろいろ迷ってみえましたが、お気に入りの板を選んでいただきました。
そして、その後いきなり難しい「鉋掛け」作業をやっていただきました。選ばれた板が固い板が多かったので最初は苦戦されていましたが、少しずつ慣れて皆さんがんばって削り上げました。(私も夢中になってしまい、写真を撮り忘れてしまいました。残念。)
木には「順目(ならいめ)」と「逆目(さかめ)」があるということも知りました。寒い日でしたが、鉋掛けをすると体が熱くなってきたようでした。
今回は2組4名の方に参加していただき、朝9時過ぎから、途中昼食タイムをはさんで午後2時過ぎまでみっちりやっていただきました。
 まずは好きな板を選びます。あらかじめ用意した中からいろいろ迷ってみえましたが、お気に入りの板を選んでいただきました。
まずは好きな板を選びます。あらかじめ用意した中からいろいろ迷ってみえましたが、お気に入りの板を選んでいただきました。そして、その後いきなり難しい「鉋掛け」作業をやっていただきました。選ばれた板が固い板が多かったので最初は苦戦されていましたが、少しずつ慣れて皆さんがんばって削り上げました。(私も夢中になってしまい、写真を撮り忘れてしまいました。残念。)
木には「順目(ならいめ)」と「逆目(さかめ)」があるということも知りました。寒い日でしたが、鉋掛けをすると体が熱くなってきたようでした。
 これは思ったよりも簡単みたいでした。その後、穴をあけたり、サンディングをしたり、切り出し刀で面取りをしたりして仕上げました。
これは思ったよりも簡単みたいでした。その後、穴をあけたり、サンディングをしたり、切り出し刀で面取りをしたりして仕上げました。「水引き研磨」というのもやっていただきましたが、結構本格的な木工体験になりました。
その後、お客様から感想の言葉をメールでいただきました。
(T.A様より)
こんにちは。昨日はとっても素敵な時間をありがとうございました!1からのものづくり、とっても楽しかったです。木の家具づくりはとても手間がかかっていることをとても実感しました。作業の道具や収納などもいろいろ工夫されて、手作りされているものもたくさんあって驚きました。
なんでも考えて、工夫して、1から作られていて、家具以外にも工房を使いやすくされている様子にもとても感動しました。だからこそ素晴らしい家具たちが生まれているんだなあ。
佐藤さんの作られる家具が我が家に欲しい!とワークショップを通して強く思いました。特に、難しいけれど鉋掛けが楽しかったです!(夢中になって鉋掛けの最中の写真を撮り忘れてました。)
ありがとうございました。
こんにちは。昨日はとっても素敵な時間をありがとうございました!1からのものづくり、とっても楽しかったです。木の家具づくりはとても手間がかかっていることをとても実感しました。作業の道具や収納などもいろいろ工夫されて、手作りされているものもたくさんあって驚きました。
なんでも考えて、工夫して、1から作られていて、家具以外にも工房を使いやすくされている様子にもとても感動しました。だからこそ素晴らしい家具たちが生まれているんだなあ。
佐藤さんの作られる家具が我が家に欲しい!とワークショップを通して強く思いました。特に、難しいけれど鉋掛けが楽しかったです!(夢中になって鉋掛けの最中の写真を撮り忘れてました。)
ありがとうございました。
初めての試みでしたが、皆さんに楽しんでいただけたようで本当に良かったです。また第2回、第3回と続けてやっていこうかなと思っています。
ちなみに…すでに次回開催は決まっています!3月3日、4日、5日です。毎年行っている「富加町いなか舎てくてくめぐり」の時に、今年はこのワークショップを行います。詳しくはまた年が明けたらこのホームページとインスタグラムで告知します。皆さんぜひご参加ください。
PS.最後は半布里工房自家製の「焼き芋」を薪ストーブで焼いて食べて(持ち帰って)いただきました。「甘い」「おいしい」と言いながら、お客様が「焼き芋屋のおじさんみたい(笑)」と笑ってみえました。シメがそれでよかったのかな?…まぁ楽しかったから良かったことにしよう!
ちなみに…すでに次回開催は決まっています!3月3日、4日、5日です。毎年行っている「富加町いなか舎てくてくめぐり」の時に、今年はこのワークショップを行います。詳しくはまた年が明けたらこのホームページとインスタグラムで告知します。皆さんぜひご参加ください。
PS.最後は半布里工房自家製の「焼き芋」を薪ストーブで焼いて食べて(持ち帰って)いただきました。「甘い」「おいしい」と言いながら、お客様が「焼き芋屋のおじさんみたい(笑)」と笑ってみえました。シメがそれでよかったのかな?…まぁ楽しかったから良かったことにしよう!
「リンちゃんありがとう…さようなら」
2022.12.14
 ところで…そのカッティングボードですが、今週末に「木工体験 世界に一つ自分だけのカッティングボードを作ろう」を開催予定です。
ところで…そのカッティングボードですが、今週末に「木工体験 世界に一つ自分だけのカッティングボードを作ろう」を開催予定です。応募者も埋まり、どんな風になるのか私自身も楽しみにしています。良い天気だといいのですが…。
 さて、ここからは私事になります。すみません。前回の里山だよりにも書きましたが、病気で死にそうになっていた愛猫「リンちゃん」が通院、看病の甲斐もなく息を引き取ってしまいました。
さて、ここからは私事になります。すみません。前回の里山だよりにも書きましたが、病気で死にそうになっていた愛猫「リンちゃん」が通院、看病の甲斐もなく息を引き取ってしまいました。
ジャガーは子猫のころにうちに住み着いた猫で、もともと野良ネコですが、リンちゃんはれっきとしたうちの猫です。それなのにどちらかというとあまりなつかなくて、いつもおどおどとしたところがありました。それでもどうかすると(私一人でいるときとか、妻が一人でいると)べったり引っ付いてくるという本当は甘えん坊の猫でもありました。夜は必ず妻の布団の上で一緒に寝ていました。
「介護の日々」
2022.11.25
 先日お伝えしていました「栗(クリ)拭き漆スライド棚」の拭き漆が仕上がりました。やはり拭き漆仕上げはいいですね。思っていたよりもいい感じです。
先日お伝えしていました「栗(クリ)拭き漆スライド棚」の拭き漆が仕上がりました。やはり拭き漆仕上げはいいですね。思っていたよりもいい感じです。
 今書きましたが、漆は年月とともに明るく(色が薄く)なって透明感が出てきます。我々はそれを「抜ける」といいますが、それがまたいい味になっていきます。
今書きましたが、漆は年月とともに明るく(色が薄く)なって透明感が出てきます。我々はそれを「抜ける」といいますが、それがまたいい味になっていきます。もちろん、漆ですから塗膜の固さも強くなっていきます。これも漆の良さですね。
L字に折り曲げた形で使ってもいいです。
 ところで、ここ1ヶ月ほど私は介護の日々を続けております。…といっても、家族の誰かが悪くなったわけじゃありません。ペットの猫の「リンちゃん」です。
ところで、ここ1ヶ月ほど私は介護の日々を続けております。…といっても、家族の誰かが悪くなったわけじゃありません。ペットの猫の「リンちゃん」です。どうやら脳に異常を来たしたらしく、歩くこともおぼつかず食欲もなくなりました。おまけに目も見えなくなり、どうやら匂いもしていないようです。そんなわけで、病院通いを続けています。
仕方がないので、食事は病院で買った療法食(柔らかい)を注射器に入れて口の中に入れてあげます。水もこうやって飲ませます。

 目が見えず、匂いもしないのでトイレも無理です。放っておくと家じゅうあちらこちらでおしっこをしてしまいますので、まずはやむなくペットゲージを買ってきました。
目が見えず、匂いもしないのでトイレも無理です。放っておくと家じゅうあちらこちらでおしっこをしてしまいますので、まずはやむなくペットゲージを買ってきました。ずっとこの中に居させるのはかわいそうなので時々出してやるのですが(といっても歩くのもフラフラなのですが)、さらにおむつも買ってきて付けています。
リンちゃんは「ジャガーちゃん」の子供ですが、もうすでに18歳以上になっています。かなりの高齢です。(ちなみにジャガーちゃんは20歳以上?) さすがに今回ばかりは(脳の病気ということもあり)先生も「元通りになる可能性は低いでしょう」と言われます。(高齢で、しかもこの状態ですから手術や麻酔の必要な検査はリスクが大きいということのようです。)
あとは私たち家族の気持ち次第ということのようです。本当に悩ましいですが、やはりかわいい家族の一員です。ジャガーの時と同じようにできる限りのことはしてやりたいと思っています。(ジャガーも4年前に肝臓病で一時死にそうになったのですが一命をとりとめ、だいぶん良くなっています。まだ2週間に1回ぐらい病院通いは続けていますが…。)
それにしても思います。ペットの保険は入っておいた方がいいですよ。
あとは私たち家族の気持ち次第ということのようです。本当に悩ましいですが、やはりかわいい家族の一員です。ジャガーの時と同じようにできる限りのことはしてやりたいと思っています。(ジャガーも4年前に肝臓病で一時死にそうになったのですが一命をとりとめ、だいぶん良くなっています。まだ2週間に1回ぐらい病院通いは続けていますが…。)
それにしても思います。ペットの保険は入っておいた方がいいですよ。
「無垢一枚板こたつ座卓」
2022.11.09

 このところ、秋らしい好天が続いて気持ちがいいです。そんな中、久しぶりに家族で庭でピザを焼いて食べました。
このところ、秋らしい好天が続いて気持ちがいいです。そんな中、久しぶりに家族で庭でピザを焼いて食べました。やはり「好天」と「素晴らしい景色」そして「おいしい食事」と「良い家族」…これだけがあればあとは何も要らないです。

 さて、工房では「栃(トチ)無垢一枚板こたつ座卓」の制作が進んでいます。
さて、工房では「栃(トチ)無垢一枚板こたつ座卓」の制作が進んでいます。天板の大きな穴の開いた部分を千切りデザインで埋めます。まずはトリマーなどを使って穴を掘ります。いろんな大きさの千切りですのでテンプレートも数種類作ってから掘ります。
「流行(はやり)?流行りに見向きもしない?それとも時代遅れ?」
2022.10.21
それにしても大きな穴です。腐った部分をきれいに取ってしまうとまたかなり大きな穴に広がりそうです。最近は「レジン」という液体が流行りで、こういう穴などがあるとレジンを流し込んで固めてしまうということをやる人たちが多いです。
全国展開をしているある大きな一枚板の会社なども盛んにそんなことをやってますし、今一枚板のテーブルを作る仕事をたくさんやっている会社や材木店もそんなようなやり方をすることが多いです。レジンばかりではありませんがそういう樹脂を流し込むというやり方です。
中にはひどい場合はレジンの海の中に欠点だらけの木材の塊を突っ込み、固めてしまう(ほぼレジンの板)という…あるいは寸法の足りない板を隙間をあけて並べその間にレジンを入れて隙間を埋めてレジンでつないで幅広の板にしてしまうという…こうなるともう木の家具とは呼べないような感じになっています。(写真を載せたいのですが、他社のですので…)
今回のお客様も出来ればそういう風にはしたくないと言われ、私ももちろんできる限りそれは避けたいという気持ちもありましたので、違う方法でこの穴を料理することにしました。よほど手間はかかりますが…。
これまでも何回かやってきましたが、大きめの千切りをはめ込んで(隙間は空いてしまいますが)あらかた穴をふさぎ、少なくともその上に物が置けるようにするというものです。(例:欅センターテーブル、栃無垢一枚板 ダイニングテーブル)
言うのは簡単ですが、今回のはかなり大きな厄介な形の穴ですので、結構悩みます。
全国展開をしているある大きな一枚板の会社なども盛んにそんなことをやってますし、今一枚板のテーブルを作る仕事をたくさんやっている会社や材木店もそんなようなやり方をすることが多いです。レジンばかりではありませんがそういう樹脂を流し込むというやり方です。
中にはひどい場合はレジンの海の中に欠点だらけの木材の塊を突っ込み、固めてしまう(ほぼレジンの板)という…あるいは寸法の足りない板を隙間をあけて並べその間にレジンを入れて隙間を埋めてレジンでつないで幅広の板にしてしまうという…こうなるともう木の家具とは呼べないような感じになっています。(写真を載せたいのですが、他社のですので…)
今回のお客様も出来ればそういう風にはしたくないと言われ、私ももちろんできる限りそれは避けたいという気持ちもありましたので、違う方法でこの穴を料理することにしました。よほど手間はかかりますが…。
これまでも何回かやってきましたが、大きめの千切りをはめ込んで(隙間は空いてしまいますが)あらかた穴をふさぎ、少なくともその上に物が置けるようにするというものです。(例:欅センターテーブル、栃無垢一枚板 ダイニングテーブル)
言うのは簡単ですが、今回のはかなり大きな厄介な形の穴ですので、結構悩みます。
 まずは腐ってぼそぼそになっている部分を、ノミや彫刻刀などを使ってこそぎ落とします。
まずは腐ってぼそぼそになっている部分を、ノミや彫刻刀などを使ってこそぎ落とします。すべてをきれいに落とすわけにはいきませんが(そんなことをすると大変な穴になってしまいます)、手で触って問題がない程度まで落とします。
ところで…10月の半ばも過ぎ、今年もあと2か月ほどで終わりとなります。早いものですね。例年今頃になると「ふるさと納税」の方も本格的に注文が増えてきます。
 我が工房では売れ筋の商品である「カッティングボード」が在庫が無くなってきましたので、急遽作ることになりました。とりあえず50枚ほど木取りをして削っておきました。またこちらも進めていくことになります。
我が工房では売れ筋の商品である「カッティングボード」が在庫が無くなってきましたので、急遽作ることになりました。とりあえず50枚ほど木取りをして削っておきました。またこちらも進めていくことになります。
P.S.カッティングボードは栗材の新商品も追加してありますし、レーザー加工機で作った「とみぱんコースター」なども追加してあります。よかったら見てやってください。
 我が工房では売れ筋の商品である「カッティングボード」が在庫が無くなってきましたので、急遽作ることになりました。とりあえず50枚ほど木取りをして削っておきました。またこちらも進めていくことになります。
我が工房では売れ筋の商品である「カッティングボード」が在庫が無くなってきましたので、急遽作ることになりました。とりあえず50枚ほど木取りをして削っておきました。またこちらも進めていくことになります。P.S.カッティングボードは栗材の新商品も追加してありますし、レーザー加工機で作った「とみぱんコースター」なども追加してあります。よかったら見てやってください。

 さて、このところ秋らしい好天が続いています。畑や庭の作業もしやすいです。畑では冬野菜が成長中です。
さて、このところ秋らしい好天が続いています。畑や庭の作業もしやすいです。畑では冬野菜が成長中です。ハクサイ、キャベツ、大根、カブ、ニンジン、ブロッコリー、レタス、正月菜、小松菜、ほうれん草、ナバナなど、種をまいたものが大きくなってきました。
ところで、よく「有機無農薬野菜」と言います。うちも有機肥料ばかりではないですが、無農薬です。でも、無農薬で作るということは虫に食われることは覚悟しなければいけません。全く虫がつかない野菜なんて逆に危なくて食べられないのだから。
虫の力はすごくて、何もしないとほとんど食べれるものには育ってきません。できるだけ虫に食われないようにするために、防虫ネットなどはしておきます。(10年ほど前まではそんなものをしなくてもけっこううまく育ったのですが、年々ダメになってきて、今では必ず防虫ネットを使うようになりました。温暖化のせいでしょう。)
 しかし、防虫ネットをしていてもカブなどは全くダメで、虫にやられています。こんなありさまです。
しかし、防虫ネットをしていてもカブなどは全くダメで、虫にやられています。こんなありさまです。
食われすぎて葉脈だけになっているものも…まぁ、ダメならあきらめるしかないですな。
虫の力はすごくて、何もしないとほとんど食べれるものには育ってきません。できるだけ虫に食われないようにするために、防虫ネットなどはしておきます。(10年ほど前まではそんなものをしなくてもけっこううまく育ったのですが、年々ダメになってきて、今では必ず防虫ネットを使うようになりました。温暖化のせいでしょう。)
 しかし、防虫ネットをしていてもカブなどは全くダメで、虫にやられています。こんなありさまです。
しかし、防虫ネットをしていてもカブなどは全くダメで、虫にやられています。こんなありさまです。食われすぎて葉脈だけになっているものも…まぁ、ダメならあきらめるしかないですな。
 苗を植えるのに必要な土は、自分で配合して作っています。赤玉土、腐葉土、牛糞たい肥、燻炭そして秘密の粉(?)を混ぜて作ります。
苗を植えるのに必要な土は、自分で配合して作っています。赤玉土、腐葉土、牛糞たい肥、燻炭そして秘密の粉(?)を混ぜて作ります。「秘密の粉」とは大げさですが、「ケイ酸塩白土」(別名ソフトシリカ?)というものです。これを混ぜると、根張りが良くなったり、虫に強くなったり、肥料分の吸収力が強くなったりという良いことがあるのです。
「栗の棚 制作佳境」
2022.10.11
 この組み立てに使用している当て木ですが、実は少し工夫がしてあります。
この組み立てに使用している当て木ですが、実は少し工夫がしてあります。マジックで線を引いてある方を板にあてるのですが、実はこちらの面は中凸に作ってあります。目で見てもわからないぐらい微妙なアールがつけてあります。
そうすることによって締め付けたときに真ん中あたりに余計に力が加わるので、結果的に全体に均等に力が加わってすべての面がくっつくという、良い締め付けができるのです。
今回も、蟻組み(天秤指し)の部分はうまくできました。ちょっと胸をなでおろしている感じです。
直角に曲げて置いた場合はこのようになります。
「秋の味覚」
2022.10.06
工房では宮崎県宮崎市のお客様ご注文の「栗のスライド棚」の制作が進んでいます。接ぎ合わせが完了した板を所定の厚み、幅、長さに仕上げます。
 そして、まずは「蟻組み(天秤指し)」の加工から始めます。
そして、まずは「蟻組み(天秤指し)」の加工から始めます。
ピンピンに先をとがらせた鉛筆で蟻組みの線を書きます。あとで修正しなくてもすむように、精度の高い墨線を引きます。
 そして、まずは「蟻組み(天秤指し)」の加工から始めます。
そして、まずは「蟻組み(天秤指し)」の加工から始めます。ピンピンに先をとがらせた鉛筆で蟻組みの線を書きます。あとで修正しなくてもすむように、精度の高い墨線を引きます。

 その墨線に沿って、鋸で切っていきます。
その墨線に沿って、鋸で切っていきます。
この作業の様子を動画に取りましたのでご覧ください。
「ちょっと変わった棚」
2022.09.30
 座板の座ぐりは、いつもの通り四方反り台鉋でせっせと削ります。削り跡はそのまま残しますので、最後は丁寧に仕上げます。
座板の座ぐりは、いつもの通り四方反り台鉋でせっせと削ります。削り跡はそのまま残しますので、最後は丁寧に仕上げます。
シンプルなデザインの椅子ですが、座り心地がよく、比較的軽量で安価です。私的にはおススメの椅子です。今回はあるところに展示するために急遽1脚作りましたが、そのことはまたお知らせします。
続いての仕事ですが…当初は「栃(トチ)無垢一枚板こたつ座卓(延長座卓付き)」の制作予定でしたが急遽順番が変更となり、まずはちょっと変わった棚の制作に取り掛かりました。
和室に置くスライド棚で、拭き漆仕上げにします。伸びたり縮んだり、はたまた直角に折り曲げることができたりと、なかなか変わった棚です。それだけに難しさもあります。
材料は拭き漆仕上げということや少しでも軽量になるようにということから、栗を使うことにしました。
 まずは板の接ぎ合わせ作業からです。たくさん枚数が必要なので、接ぎ合わせ作業も2回に分けて行いました。
まずは板の接ぎ合わせ作業からです。たくさん枚数が必要なので、接ぎ合わせ作業も2回に分けて行いました。
接ぎ合わせ面を「手押し鉋盤」で削ります。
和室に置くスライド棚で、拭き漆仕上げにします。伸びたり縮んだり、はたまた直角に折り曲げることができたりと、なかなか変わった棚です。それだけに難しさもあります。
材料は拭き漆仕上げということや少しでも軽量になるようにということから、栗を使うことにしました。
 まずは板の接ぎ合わせ作業からです。たくさん枚数が必要なので、接ぎ合わせ作業も2回に分けて行いました。
まずは板の接ぎ合わせ作業からです。たくさん枚数が必要なので、接ぎ合わせ作業も2回に分けて行いました。接ぎ合わせ面を「手押し鉋盤」で削ります。
「残暑」
2022.09.20

 在庫商品ですので、よかったら買ってください。こちらのクルミの円卓のサイズは直径100cmです。
在庫商品ですので、よかったら買ってください。こちらのクルミの円卓のサイズは直径100cmです。

 そして…ちょっと変わったものですが、花器を制作しました。衣桁(いこう)、あるいは屏風のように直角に開いて立てて使うものです。
そして…ちょっと変わったものですが、花器を制作しました。衣桁(いこう)、あるいは屏風のように直角に開いて立てて使うものです。穴の開いたところに竹筒をさして、その中に花を立てます。細かなものですが、そういうものこそ意外と作るのが難しかったりします。
お客様のところにお届けする日も近いです。
 そして…その間に、実は我が家のものも作っていました。ずっと前から(何十年にもなりますが)「作らねば…」と思っていたものです。坪庭の目隠しとなる垣根です。お隣が急にすっきりして丸見え状態になってしまったので、さすがに落ち着かなくなり急に思い立って作ることにしました。
そして…その間に、実は我が家のものも作っていました。ずっと前から(何十年にもなりますが)「作らねば…」と思っていたものです。坪庭の目隠しとなる垣根です。お隣が急にすっきりして丸見え状態になってしまったので、さすがに落ち着かなくなり急に思い立って作ることにしました。
思い立ったら早いです。まずは水平にレベルを出して基礎石を固定します。これに約半日。簡単に図面を引いて材料を買い出しに行き、工房で加工します。これに約2日。防腐剤を塗装してから組み立てます。これに約2日。…そんな感じで、2日ほどで完成しました。
 そして…その間に、実は我が家のものも作っていました。ずっと前から(何十年にもなりますが)「作らねば…」と思っていたものです。坪庭の目隠しとなる垣根です。お隣が急にすっきりして丸見え状態になってしまったので、さすがに落ち着かなくなり急に思い立って作ることにしました。
そして…その間に、実は我が家のものも作っていました。ずっと前から(何十年にもなりますが)「作らねば…」と思っていたものです。坪庭の目隠しとなる垣根です。お隣が急にすっきりして丸見え状態になってしまったので、さすがに落ち着かなくなり急に思い立って作ることにしました。思い立ったら早いです。まずは水平にレベルを出して基礎石を固定します。これに約半日。簡単に図面を引いて材料を買い出しに行き、工房で加工します。これに約2日。防腐剤を塗装してから組み立てます。これに約2日。…そんな感じで、2日ほどで完成しました。

 ところで、8月末から9月中旬にかけては畑仕事も忙しい時期になります。秋冬野菜の植え付けの準備です。
ところで、8月末から9月中旬にかけては畑仕事も忙しい時期になります。秋冬野菜の植え付けの準備です。ところが、結構雨続きでなかなか思ったようにできませんでした。天気を見つつ日々を過ごし、「今日しかない」という日に畑仕事を進めました。

 やらなければいけないのは、秋じゃがの植え付け、イチゴの苗の仮植え、ダイコン・カブ・ナバナ・ほうれん草などの種まき、キャベツやレタスなどの苗植え、ハクサイ・ネギ・玉ねぎの苗づくりなどなど…。
やらなければいけないのは、秋じゃがの植え付け、イチゴの苗の仮植え、ダイコン・カブ・ナバナ・ほうれん草などの種まき、キャベツやレタスなどの苗植え、ハクサイ・ネギ・玉ねぎの苗づくりなどなど…。畑の草をきれいに引いて、たい肥や肥料を混ぜて起こし、畝を作って準備をしなければなりません。なんとかできてよかったです。
「暇つぶし」
2022.08.23
今年は史上最高に暑い夏だとか…。私の感覚では2018年の方が暑かったようにも思えるのですが…。まぁ、それでも毎日暑い…というか蒸し暑い日が続いています。
夏野菜もそろそろ終わりに近づき、ナスもお盆ごろに剪定をして秋ナスの準備をしました。まだまだたくさんナスの実はついていて、まだまだ収穫は出来そうな感じでしたが、時期が遅れると秋ナスにならないので思い切ってやってしまいました。

 すべての実と花を取ってしまってから、アーチパイプに添ってざっくりと切り落とします。
すべての実と花を取ってしまってから、アーチパイプに添ってざっくりと切り落とします。
1ヵ月後、おいしい秋ナスが食べられるのを楽しみにします。
夏野菜もそろそろ終わりに近づき、ナスもお盆ごろに剪定をして秋ナスの準備をしました。まだまだたくさんナスの実はついていて、まだまだ収穫は出来そうな感じでしたが、時期が遅れると秋ナスにならないので思い切ってやってしまいました。

 すべての実と花を取ってしまってから、アーチパイプに添ってざっくりと切り落とします。
すべての実と花を取ってしまってから、アーチパイプに添ってざっくりと切り落とします。1ヵ月後、おいしい秋ナスが食べられるのを楽しみにします。
また、椅子2脚も無事納品が完了しました。お客様も大変喜んでくださいました。
 そして仕事の方ですが、まずは花器のご注文。ちょっと変わった花器です。指物仕事の感じですが、まずは部材を木取りし、少し分厚めに削った状態でシーズニング。1週間ほどこのまま放置します。
そして仕事の方ですが、まずは花器のご注文。ちょっと変わった花器です。指物仕事の感じですが、まずは部材を木取りし、少し分厚めに削った状態でシーズニング。1週間ほどこのまま放置します。(シーズニングというのは木を環境にならすということで、ある程度放置してねじれや反りを出させておくことです。その後で正式にまっすぐに削って仕上げます。)
 次に「寄せ蟻」の加工です。天板の裏にルーターで蟻溝を掘っていきます。
次に「寄せ蟻」の加工です。天板の裏にルーターで蟻溝を掘っていきます。
「いろいろ」
2022.08.08
どの方向から見ても滑らかな曲線になるように丁寧に仕上げていきます。最後はサンディングをして滑らかに仕上げます。
塗装を終えて完成です。
πチェアは旦那様の椅子ですが、これから奥様用のウォールナットの「KOSI-KAKE」の制作に入ります…と言いたいところですが、その前にちょっと…もうすぐ1歳になる孫娘の誕生日プレゼントに娘からリクエストされたものが2つ。
 一つは当工房の定番商品である「木馬」です。名前を彫刻してあげます。
一つは当工房の定番商品である「木馬」です。名前を彫刻してあげます。
 一つは当工房の定番商品である「木馬」です。名前を彫刻してあげます。
一つは当工房の定番商品である「木馬」です。名前を彫刻してあげます。
 そしてもう一つは「コンポート(ケーキスタンド)」です。直径30cm×高さは10cmぐらいの大きさのものです。工房にある材料で余分にいくつか作ることにしました。
そしてもう一つは「コンポート(ケーキスタンド)」です。直径30cm×高さは10cmぐらいの大きさのものです。工房にある材料で余分にいくつか作ることにしました。例によって木工旋盤で成形していきます。まずは上のお皿部分から。
他にもいろんな花が咲いています。特にバラの2番花がたくさん咲いてきれいです。少し前に与えた特製の肥料が効いたのだと思います。
猛暑の中でもきれいに咲いてくれる花たちに感謝です。シュウメイギクも咲き始めました。
「πチェア」
2022.08.01

 次に「南京鉋」で削って形を仕上げていきます。
次に「南京鉋」で削って形を仕上げていきます。ちなみにこの南京鉋は、同じ町内(富加町加治田)に住む鉋制作者から購入したものです。まだ若い方で、もともと木工を志す中で道具制作の道へと進んでおられる方です。
私の家から自転車で数分という本当にご近所に住んでおられます。(歩いても10分ぐらいです。)
正確に言うと数年前にこの地に引っ越して来られて、創作を続けてみえます。私が住むこの富加町加治田地区というところはもともと中山道の脇街道であって、今もその雰囲気が残っています。その中に造り酒屋であったり、大庄屋のお屋敷跡があったり、大工さんも多くいらっしゃいます。
また刀鍛冶も現在2人ほどいらっしゃって、現役で刀制作をしてみえます。 その刀鍛冶のお宅に空き家があったのでその場所を借りて鉋を作ってみえるというわけです。なんかご縁を感じますね。「富加町加治田」という地区の名前…ぜひ覚えておいてください。(加治田の町のことはまたいずれ書こうかと思っています。)
また刀鍛冶も現在2人ほどいらっしゃって、現役で刀制作をしてみえます。 その刀鍛冶のお宅に空き家があったのでその場所を借りて鉋を作ってみえるというわけです。なんかご縁を感じますね。「富加町加治田」という地区の名前…ぜひ覚えておいてください。(加治田の町のことはまたいずれ書こうかと思っています。)

 なかなか使いやすい南京鉋で重宝しています。他にも2本ほど南京鉋を持っているのですが、それは馴染みの新潟の道具屋さんから購入したものです。
なかなか使いやすい南京鉋で重宝しています。他にも2本ほど南京鉋を持っているのですが、それは馴染みの新潟の道具屋さんから購入したものです。でも、すぐ近くに良い道具屋さんがおられるというのは大変ラッキーなことです。それにそういう方がこの古くからの町加治田というところへ住んで、伝統を受け継いで行くということはうれしいことであります。
しかし残念ながら、近々よそへ引っ越しをされるという予定でみえるみたいです。せっかくなので、こちらにみえる間にもう一本注文をしようかと考えているところです。
さて成形が終わりましたので、サンディングをして仕上げます。
「好きこそものの…」
2022.07.26
 型紙で印をつけて丸く切り抜いていきます。ここで使う機械は帯鋸という機械です。しかも曲線切り用(我々は「回し挽き」と呼んだりしていますが)の帯鋸です。
型紙で印をつけて丸く切り抜いていきます。ここで使う機械は帯鋸という機械です。しかも曲線切り用(我々は「回し挽き」と呼んだりしていますが)の帯鋸です。長い帯になった鋸刃が高速で大きく回転しています。それだけでも慣れていないと少し怖いですが、さらに(この肘のように)アールがきつい曲線を無理やり切っていると「バンッ!!」と大きな音がしてこの鋸刃が切れたりすることもあるので(その音がまた怖い)、十分気を付けて作業します。
昔木工所で働いていたころはベテランの工場長なんかは全くこの作業が上手で、名人のようにすいすいと曲線を切り抜いていたことを思い出します。
 そして、再び帯鋸で切り抜いていきます。今度はまた細かい切り抜きで、しかも曲面になったものを切り抜いていくのでより難しい作業になります。
そして、再び帯鋸で切り抜いていきます。今度はまた細かい切り抜きで、しかも曲面になったものを切り抜いていくのでより難しい作業になります。安全カバーを付けたままだと材料が当たってしまって切れないので、安全カバーを外して作業をします。またまたちょっと怖い?

 ところで毎日暑い日が続きます。こんなに暑いと人間も動植物もばててしまいます。畑の野菜も通常「なり疲れ」といって、ここらで少し実の収量が落ちるものです。
ところで毎日暑い日が続きます。こんなに暑いと人間も動植物もばててしまいます。畑の野菜も通常「なり疲れ」といって、ここらで少し実の収量が落ちるものです。そんな中、我が畑ではナスもトマトも頑張って実をならせてくれています。

 さらにトマトの茎全体を下に下して天井にくっつくのを避けるようにしています。ですからもうすでに全長は3メートルを超えていると思います。
さらにトマトの茎全体を下に下して天井にくっつくのを避けるようにしています。ですからもうすでに全長は3メートルを超えていると思います。しかも2本仕立て(大玉トマト)、3本仕立て(ミニトマト)なのですごい生育力だと感心します。
とりあえずこんな風に毎日収穫できているのは、今年使ってみた肥料(活力液?)にも原因があると思います。花でも同じですが、人間でも「夏バテ」があるように夏の暑い時期にはあまり食欲がわかないことがあります。あまりこってりしたものは食べたくない。そんなときに無理に固形(粒状)肥料を施肥しても植物は吸収する力が落ちているからだめですし、人間でいうところの「腹をこわす」みたいな状態になりかねません。

 粒状肥料も適当に必要ですが、それを補うために液体肥料(活力剤)を与えることが効果があるようです。私が今年初めて使ったのがこんな活力剤です。ミネラルをたくさん含んだものです。500〜1000倍に水で薄めて葉面散布してやります。
粒状肥料も適当に必要ですが、それを補うために液体肥料(活力剤)を与えることが効果があるようです。私が今年初めて使ったのがこんな活力剤です。ミネラルをたくさん含んだものです。500〜1000倍に水で薄めて葉面散布してやります。
前に書きましたが、適当な時期に粒状肥料と苦土石灰を追肥として与えることと、このミネラルを与えることは今のところ効果が出ているように思われます。

 粒状肥料も適当に必要ですが、それを補うために液体肥料(活力剤)を与えることが効果があるようです。私が今年初めて使ったのがこんな活力剤です。ミネラルをたくさん含んだものです。500〜1000倍に水で薄めて葉面散布してやります。
粒状肥料も適当に必要ですが、それを補うために液体肥料(活力剤)を与えることが効果があるようです。私が今年初めて使ったのがこんな活力剤です。ミネラルをたくさん含んだものです。500〜1000倍に水で薄めて葉面散布してやります。前に書きましたが、適当な時期に粒状肥料と苦土石灰を追肥として与えることと、このミネラルを与えることは今のところ効果が出ているように思われます。

 そして、ネギの伏せなおしも(全部ではありませんが)しました。天気を見て「今日しかない!」という感じでやりました。
そして、ネギの伏せなおしも(全部ではありませんが)しました。天気を見て「今日しかない!」という感じでやりました。今日やったのは「九条太ネギ」の伏せなおしです。抜いたネギの皮を一皮むいて中の白い部分をあらわにします。
この作業が面倒くさいです。妻がいれば一緒にやるのですが、あいにく不在だったので一人でやりました。妻は私の2倍ぐらい早くこの作業をやります。
私はよく人に「器用ですね」と言われますが、実は全然器用ではなくて本当に細かいことが苦手、不器用です。子どものころからそうでした。図画工作なんかでも大体人より遅く、最後までやっているということが多かったです。逆に言えばそれだけ集中していたのかもしれませんし、こだわって作っていたのかもしれませんが…。(ものは思いよう)
そんな不器用な人間がなぜこんな家具製作をしているのかというと、ただ一言…「好きだからできる」のだと思います。「好きこそものの上手なれ」とよく言いますが、私に言わせれば「好きこそものの我慢ができる」(好きであれば我慢ができる)です。なんでも我慢して続けていればそのうちそれなりにできるようになっていくものだと思います。そんな考えが持てるようになったのはこの仕事についてからです。若いころはそんなことは分からなかったです。
 おっと、またまた話が脱線しました。そんな風にしてネギの皮をむき終えて畑に伏せました。雨が降る前にできて良かったです。
おっと、またまた話が脱線しました。そんな風にしてネギの皮をむき終えて畑に伏せました。雨が降る前にできて良かったです。
そんな不器用な人間がなぜこんな家具製作をしているのかというと、ただ一言…「好きだからできる」のだと思います。「好きこそものの上手なれ」とよく言いますが、私に言わせれば「好きこそものの我慢ができる」(好きであれば我慢ができる)です。なんでも我慢して続けていればそのうちそれなりにできるようになっていくものだと思います。そんな考えが持てるようになったのはこの仕事についてからです。若いころはそんなことは分からなかったです。
 おっと、またまた話が脱線しました。そんな風にしてネギの皮をむき終えて畑に伏せました。雨が降る前にできて良かったです。
おっと、またまた話が脱線しました。そんな風にしてネギの皮をむき終えて畑に伏せました。雨が降る前にできて良かったです。
「とってある」
2022.07.19
 完成した胡桃(クルミ)のダイニングセットを、一昨日お客様のところへ納品に行ってきました。
完成した胡桃(クルミ)のダイニングセットを、一昨日お客様のところへ納品に行ってきました。
 約1ヵ月強の制作期間の間に毎週末工房に見学&木工体験に来られたお客様でしたので、納品の日を待ちわびる気持ちは人一倍だったと思われました。
約1ヵ月強の制作期間の間に毎週末工房に見学&木工体験に来られたお客様でしたので、納品の日を待ちわびる気持ちは人一倍だったと思われました。「実際に置くと、工房で見た時以上に存在感があっていいですね」と喜んでいただけました。
 ビスケットを間に挟んで(雇い実の代わり)、接着し、はたがねで締めて一昼夜置きます。
ビスケットを間に挟んで(雇い実の代わり)、接着し、はたがねで締めて一昼夜置きます。
このπチェアは本当に手間がかかり、制作が難しい椅子です。先ほど座板の制作から始めると言いましたが、実はそれと同時進行で他の部材も作っていかなくてはなりません。脚も、幕板も、背板(肘)も同時に制作を進めていくのです。
その制作手順やコツなどは文章で書いてありません(書くことが困難です)。すべて私の頭の中に入っています。図面はありますが、それを見ただけではこの椅子を作ることはできません。図面には書けないこと(コツというか勘所、注意点など)がたくさんあるのです。
 そんなわけで、肘(背板)の制作も進めます。まず角材を(接ぎ合わせて)作ってから所定の大きさにカットし、雇い実を要れる溝(小穴)を切っていきます。
そんなわけで、肘(背板)の制作も進めます。まず角材を(接ぎ合わせて)作ってから所定の大きさにカットし、雇い実を要れる溝(小穴)を切っていきます。
その制作手順やコツなどは文章で書いてありません(書くことが困難です)。すべて私の頭の中に入っています。図面はありますが、それを見ただけではこの椅子を作ることはできません。図面には書けないこと(コツというか勘所、注意点など)がたくさんあるのです。
 そんなわけで、肘(背板)の制作も進めます。まず角材を(接ぎ合わせて)作ってから所定の大きさにカットし、雇い実を要れる溝(小穴)を切っていきます。
そんなわけで、肘(背板)の制作も進めます。まず角材を(接ぎ合わせて)作ってから所定の大きさにカットし、雇い実を要れる溝(小穴)を切っていきます。
座板、肘(背板)の接着剤が乾くのを待っている間に今度は脚を作っていきます。後脚の制作です。

 こうして、とりあえずここまで出来ました。このあと座板に反り止めを加工したり(幕板が反り止めとなります)…書ききれないぐらいいろんな工程があります。
こうして、とりあえずここまで出来ました。このあと座板に反り止めを加工したり(幕板が反り止めとなります)…書ききれないぐらいいろんな工程があります。あわてずじっくりと、しかも素早く作業を進めていきたいと思います。とにかく暑い日が続くのであまりゆっくりとしていられないのです。

 さて、ここからは「じじバカ」の話になります。我が初孫も来月で1歳になります。早いですね。昨年の夏の暑い日に生まれてきたことを思い出します。
さて、ここからは「じじバカ」の話になります。我が初孫も来月で1歳になります。早いですね。昨年の夏の暑い日に生まれてきたことを思い出します。ある意味、我が子の誕生以上に感動しました。小さく生まれたので初めは少し心配もしましたが、すっかり大きくなって本当に可愛いです。
もう「かわいい」という言葉しか出ません。ときどき来てくれるのを楽しみにしています。
 その孫がうちに来るときのために、いろんなものが必要になりました。例えばベビーベッド。生まれた当初1ヵ月ほど我が家に里帰りしていたのでベビーベッドが必要だったのですが、実はこれ…我が娘と息子が生まれたときに使っていたものです。
その孫がうちに来るときのために、いろんなものが必要になりました。例えばベビーベッド。生まれた当初1ヵ月ほど我が家に里帰りしていたのでベビーベッドが必要だったのですが、実はこれ…我が娘と息子が生まれたときに使っていたものです。それがとってあったので出してきて組み立てました。全くきれいなもので、全然壊れていなくて十分使えました。むしろ昔のものなので、少し広めで良いくらいです。
 そして、お風呂に入れるのが私の仕事ですが、初めはたらいに入れてやりました。そのたらい(?)もこれ、娘と息子が使ったものです。まだまだきれいです。
そして、お風呂に入れるのが私の仕事ですが、初めはたらいに入れてやりました。そのたらい(?)もこれ、娘と息子が使ったものです。まだまだきれいです。こちらも広くて使いやすいです。(今のものは住宅事情を反映して小さめですね。)
 こんなおもちゃもとってあります。木でできたおもちゃです。これは娘(長女)が生まれたとき、わざわざ京都府宇治市のお店まで買いに行ったものです。北欧製の木製おもちゃです。
こんなおもちゃもとってあります。木でできたおもちゃです。これは娘(長女)が生まれたとき、わざわざ京都府宇治市のお店まで買いに行ったものです。北欧製の木製おもちゃです。今でこそ木の知育玩具は結構ありますが、30年以上も昔はなかなかありませんでした。(その頃はまだ私もこの仕事はしていませんでしたので…) これで娘も息子もよく遊んだものです。
 取ってあると言えばもう一つ、木馬も…。木馬は当工房の定番商品として載せてありますが、実はこの木馬、娘が生まれたときに作ってあげたものです。
取ってあると言えばもう一つ、木馬も…。木馬は当工房の定番商品として載せてありますが、実はこの木馬、娘が生まれたときに作ってあげたものです。その後息子も使いました。写真の手前が娘や息子が使った木馬で、奥の方がショールームに飾ってある未使用品です。
「もどき(擬き)」
2022.07.12
本当によく似ているので見落としてしまいそうですが、それが彼ら(草達)の生き延びる術なのです。人間に抜かれないように花に似せた形をして生えてくる…生命力の強さです。
こういう「擬き(もどき)」の植物がよく見られます。考えると植物だけでなく人間にもそういうことはよくあります。例えば私たちの業界でも「もどき」と言いたくなるような人もいます。(この場合「もどき」と言うのは、プロと呼ぶにはちょっと技術、知識、経験共にいかがなものかと思いたくなるような人のこと)
でも、実はそういう人の方がたくましくこの業界内でも生きていたりします。現代は必ずしも「良い仕事ができる」からといって必ずしも成功するとは限りません。
ある人がこんなことを言ってました。「プロとアマの違いは、生業にしているかどうかではない。なぜなら素晴らしい仕事ができても食べることができない素晴らしい人は世界中にたくさんいるのだから…」
そう思うと「もどき」はごく当たり前になって、「もどき」という言葉もそのうち消えていってしまうのかもしれません。いいか悪いかはともかくとして…。

 さて庭から畑に目を移しますが、トマトもそろそろ赤くなってき始めました。
さて庭から畑に目を移しますが、トマトもそろそろ赤くなってき始めました。
トマトの棚はジャングルのようになっています。
こういう「擬き(もどき)」の植物がよく見られます。考えると植物だけでなく人間にもそういうことはよくあります。例えば私たちの業界でも「もどき」と言いたくなるような人もいます。(この場合「もどき」と言うのは、プロと呼ぶにはちょっと技術、知識、経験共にいかがなものかと思いたくなるような人のこと)
でも、実はそういう人の方がたくましくこの業界内でも生きていたりします。現代は必ずしも「良い仕事ができる」からといって必ずしも成功するとは限りません。
ある人がこんなことを言ってました。「プロとアマの違いは、生業にしているかどうかではない。なぜなら素晴らしい仕事ができても食べることができない素晴らしい人は世界中にたくさんいるのだから…」
そう思うと「もどき」はごく当たり前になって、「もどき」という言葉もそのうち消えていってしまうのかもしれません。いいか悪いかはともかくとして…。

 さて庭から畑に目を移しますが、トマトもそろそろ赤くなってき始めました。
さて庭から畑に目を移しますが、トマトもそろそろ赤くなってき始めました。トマトの棚はジャングルのようになっています。
娘や息子に持たせると必ずといっていいくらい「野菜、ありがとう。おいしかったよ。」と言って食卓の写真を送ってくれます。こちらこそ使ってくれてありがとう…ですが。
今回はテーブルもベンチも「木組みの技がデザインになっているダイニングセットを…」というお客様の希望を受けて作らせていただいたものです。

 ですから、テーブルは通常のI型を楔止めのデザインに変えたものにしましたし、ベンチは定番の「木組みベンチ」を基本として、背もたれをお客様のご希望のように変更したものにしました。
ですから、テーブルは通常のI型を楔止めのデザインに変えたものにしましたし、ベンチは定番の「木組みベンチ」を基本として、背もたれをお客様のご希望のように変更したものにしました。

 ですから、テーブルは通常のI型を楔止めのデザインに変えたものにしましたし、ベンチは定番の「木組みベンチ」を基本として、背もたれをお客様のご希望のように変更したものにしました。
ですから、テーブルは通常のI型を楔止めのデザインに変えたものにしましたし、ベンチは定番の「木組みベンチ」を基本として、背もたれをお客様のご希望のように変更したものにしました。
 また「千切り」もお客様がお気に入りだったのでベンチの方に、穴埋めとして、少し入れさせていただきました。
また「千切り」もお客様がお気に入りだったのでベンチの方に、穴埋めとして、少し入れさせていただきました。近々納品の予定となっています。喜んでいただけることを祈っています。そしてこれから、次の注文である椅子2脚(πチェア フラット肘型とKOSI-KAKE)の制作に取り掛かっていきます。
「お客様からの手紙」
2022.07.07
現在制作中の胡桃(クルミ)のダイニングセットをご注文いただいたお客様ですが、これまでほぼ毎週末になると工房にみえて制作の様子を見学していかれます。「自分たちの注文したテーブルがどんなふうに出来上がっていくのか見たい」というのがその理由ですが、それだけでなく私どもの家具製作の技術にも大変興味をお持ちのようです。
 そのお客様からお手紙をいただきました。詳しくは「お客様の声(岐阜県各務原市T.Y.様)」に載せてありますのでご覧ください。
そのお客様からお手紙をいただきました。詳しくは「お客様の声(岐阜県各務原市T.Y.様)」に載せてありますのでご覧ください。
今回のお客様はよく配慮のできるお方ですので、通常であればあまり歓迎しにくい制作中の様子の見学も、お互いに楽しくできました。
一つの作品がさまざまな過程を経て(たくさんの手間をかけて)出来上がっていくことや、細かな技術や知識、そして何よりも経験の積み重ねである様子も見て分かっていただけるということを考えると、こんな風にお客様に(ご注文をいただいているお客様はもちろん、ご注文を検討しておられるお客様も)制作の様子を見学していただくことは大切なことだなと感じます。ただし、今回のように配慮のできるお客様であることが前提にはなりますが…。
 そのお客様からお手紙をいただきました。詳しくは「お客様の声(岐阜県各務原市T.Y.様)」に載せてありますのでご覧ください。
そのお客様からお手紙をいただきました。詳しくは「お客様の声(岐阜県各務原市T.Y.様)」に載せてありますのでご覧ください。今回のお客様はよく配慮のできるお方ですので、通常であればあまり歓迎しにくい制作中の様子の見学も、お互いに楽しくできました。
一つの作品がさまざまな過程を経て(たくさんの手間をかけて)出来上がっていくことや、細かな技術や知識、そして何よりも経験の積み重ねである様子も見て分かっていただけるということを考えると、こんな風にお客様に(ご注文をいただいているお客様はもちろん、ご注文を検討しておられるお客様も)制作の様子を見学していただくことは大切なことだなと感じます。ただし、今回のように配慮のできるお客様であることが前提にはなりますが…。
 さて、そのダイニングセットですが…ベンチ2台の制作が完成に近づいています。座板の座刳り(ざぐり)をします。まずは機械で大まかに凹面を作ります。
さて、そのダイニングセットですが…ベンチ2台の制作が完成に近づいています。座板の座刳り(ざぐり)をします。まずは機械で大まかに凹面を作ります。とはいっても、この作業が結構大変です。約2ミリづつずらし、鋸刃の出も微妙に変えつつ送るという作業を行います。一つの座板でこの作業を約200回、2つ分ですので400回ぐらいは行ったことになります。
大きな板ですので重さもありますから、なかなか大変でした。たっぷり数時間かかりました。
背柱の成形をします。鉋を使います。平鉋、反り台鉋、南京鉋などいろんな種類の鉋を使います。
脚部の部材はあらかじめ塗装を済ませておきます。それから座板に組み込みます。
 話は変わります。我が"jagar's garden"には古ぼけたこんな椅子が置いてあります。ずっと外に置いてあったので朽ちて壊れそうになっていますが、我が愛猫ジャガーのお気に入りの場所となっています。いつも大体この上に座っています。
話は変わります。我が"jagar's garden"には古ぼけたこんな椅子が置いてあります。ずっと外に置いてあったので朽ちて壊れそうになっていますが、我が愛猫ジャガーのお気に入りの場所となっています。いつも大体この上に座っています。なぜこんな古びた椅子を捨てずに置いてあるかというと…それは、思い出の椅子だからです。この椅子は私がまだこの仕事を始める前(30年以上も前)、趣味で木工を始めたときに作ったものです。いわば私の第1号作品です。
機械なんて何もなく、ほとんど鉋や鋸、ノミといった手工具だけで、仕事の休みの日に何ヵ月もかけて作ったものです。通しほぞやくさび止めなど、それなりに凝った作りで作ったものです。固い楢(ナラ)の木でしたので、苦労して作ったことを覚えています。
出来上がってみると、少しぐらぐらしてあまり出来は良くなかったし、座り心地もそんなに良くはなかったですが、初めての作品が完成した喜びは今でも思い出せます。実用的ではなかったので、何かを置く台として使ってみたり、最後はこのように庭に置いてオブジェのようにしていました。
それがいよいよ朽ち果てて、壊れてばらばらになってしまいました。今日お別れをしました。なんだか淋しい気もします。私をこの道に導いてくれたものの一つです、ありがとう。
「週末は恒例の…」
2022.06.29
 ここのところ週末になるとご注文主のお客様が「制作の様子を見たい」と言われ、工房にお越しになるのが恒例となっています。先日の日曜日もまた来られて、ベンチの制作を見ていかれました。
ここのところ週末になるとご注文主のお客様が「制作の様子を見たい」と言われ、工房にお越しになるのが恒例となっています。先日の日曜日もまた来られて、ベンチの制作を見ていかれました。ついでに脚の貫先のサンディングなども一緒に体験していただきました。
前回の里山だよりにも書きましたが、私が制作している様子を逐次写真や動画に撮っておられ、それを送っていただきました。
今回で3回目(4回目?)の見学となり、お客様も(私も?)もう慣れた感じになっています。木くずが出たらさっとエアーで吹いてくれたり、床の掃除をしておられたり…毎回「楽しかったです」と言って帰っていかれます。

 さて、ベンチの制作は脚部が完成し、背もたれの制作に移っています。
さて、ベンチの制作は脚部が完成し、背もたれの制作に移っています。
背柱を建てるほぞ穴をノミで掘って…

 さて、ベンチの制作は脚部が完成し、背もたれの制作に移っています。
さて、ベンチの制作は脚部が完成し、背もたれの制作に移っています。背柱を建てるほぞ穴をノミで掘って…
しかし、庭では暑さに強い花たちががんばって咲いてくれています。フロックス、エキナセア、スーパーランタナ、スーパートレニア、ダリア、桔梗、アジサイ、そしてハーブのベルガモットなどなど…。
バラも2番花が咲いています。レディーオブシャーロット、アリスターステラグレイ、ピエールドゥロンサールなどなど…。
それをつるして乾かすのですが、その場所が問題で、いろいろつるしてみた結果「ここが一番いい」と選んだのが居間と次の間の境のところ。少し前もニゲラを切ってここにつるしていました。まるで花のカーテンみたい…。正直、ちょっと邪魔くさい…。
でも完成すれば美しいもので、これで花の命もまた新たな形で生かされ、長く鑑賞することができます。
さて話を戻し…猛暑の中ですが、畑の方はそんな中でも2〜3ヵ月後のことを見越して土作りです。大量にもみ殻と米糠を撒いて管理機で混ぜくっておきます。こうして土の中で自然発酵をさせてふかふかで良い土へと変わっていくのです。
猛暑と言えば、私が指を怪我したのも猛暑が続いた2018年のことです。連日のように38℃、39℃、40℃が続いたあの年を忘れることはありません。でもそれは7月下旬のことだったはず…今年はまだ6月です。この先一体どうなってしまうのでしょう。とにかく気を付けて無理をしないようにやっていこうと思います。
「父の日」
2022.06.21
 19日(日)は父の日でした。毎年ですが、娘と息子が何かしらプレゼントをくれます。今年も娘からはドリンクセット、息子からはミスタードーナッツとビールのつまみをもらいました。(ドーナッツとつまみは食べてしまい、写真を撮り忘れてしまいました。)
19日(日)は父の日でした。毎年ですが、娘と息子が何かしらプレゼントをくれます。今年も娘からはドリンクセット、息子からはミスタードーナッツとビールのつまみをもらいました。(ドーナッツとつまみは食べてしまい、写真を撮り忘れてしまいました。)本当にうれしいです。よくもまぁこんな出来の悪い父に毎年毎年くれるものだと思い、感謝の気持ち以外ありません。自分のことを振り返ると、私は若い頃父や母にプレゼントなんてしたことが無いような出来の悪い息子でした。まぁあの頃は「父の日」自体が無かったのかもしれませんが…。
それにしても、今さらながらもう少し親孝行をしておけばよかったと反省ばかりの今日この頃です。(私の父母はすでに20数年も前、私が工房を開業した年に相次いで病死しました。ですから、私がこのような仕事を始めて、ろくに仕事も無い様子しか見ていないので、心配ばかりしてあの世へ行ったのだと思います。生きていれば、少しは仕事ももらえるようになった私の姿や、それ以上に大きく立派に育ったかわいい孫(我が娘と息子)の姿を見て本当に喜んでくれたことでしょう。)
 さて工房ですが、引き続き胡桃(クルミ)のダイニングセットの制作を進めています。そのご注文主であるお客様が「制作の様子をまた見たい」と言ってお越しになりました。3度目です。
さて工房ですが、引き続き胡桃(クルミ)のダイニングセットの制作を進めています。そのご注文主であるお客様が「制作の様子をまた見たい」と言ってお越しになりました。3度目です。今回はベンチの反り止めと千切り制作でしたが、その様子を見学され写真や動画を撮ってくださいました。

 ズッキーニは相変わらず毎日数本ずつ取れてきます。
ズッキーニは相変わらず毎日数本ずつ取れてきます。しかも、うちのは大きめなのでそれを使い切るのも大変です。(取れすぎるので少し放っておくとすぐに大きくなってしまうのです。朝と夕方とでは大きさが1.5倍ほどの違いになってしまいます。)
「草引きは手で」
2022.06.16

 木端(こば)の仕上げです。自然な表情をそのまま生かすためには、一手間(ひとてま)が必要です。
木端(こば)の仕上げです。自然な表情をそのまま生かすためには、一手間(ひとてま)が必要です。彫刻刀やブラシなどを使って丁寧に木の皮をはがしていきます。これをサンダーなどでダァーッとやってしまっては、せっかくの自然の表情が生かされません。

 そして、塗装に入りました。お客様が「また見に行ってもいいですか?」と言って、再度工房においでになりました。ちょうど2回目の塗装をするところだったので、(天板だけですが)一緒に塗装を体験していただきました。
そして、塗装に入りました。お客様が「また見に行ってもいいですか?」と言って、再度工房においでになりました。ちょうど2回目の塗装をするところだったので、(天板だけですが)一緒に塗装を体験していただきました。残念ながらまたまた写真は撮り忘れましたが、喜んでいただけました。
 接ぎ合わせをします。テーブルと同じように雇い実(やといざね)とビスケットジョイントの加工をします。
接ぎ合わせをします。テーブルと同じように雇い実(やといざね)とビスケットジョイントの加工をします。
さて…話が変わりますが、庭や畑仕事は草引き抜きではできません。特にこの時期は草がどんどん生えて育ってきます。少し放っておくと庭も畑も草だらけになってしまいます。草引きは大変ですが、以前書きましたように草引きも楽しいと思えるぐらいにならないと畑も庭もやってられません。
 まあ、私の場合、毎朝7時前から動き出しますが、まずは庭や畑を見に行くことから一日をスタートします。そこで1時間ぐらい花や野菜の世話をしたり、草引きをするのを日課にしています。そうやって毎日少しづつやっていれば広い畑も庭も何とかやっていくことが出来ます。
まあ、私の場合、毎朝7時前から動き出しますが、まずは庭や畑を見に行くことから一日をスタートします。そこで1時間ぐらい花や野菜の世話をしたり、草引きをするのを日課にしています。そうやって毎日少しづつやっていれば広い畑も庭も何とかやっていくことが出来ます。
そうやって動いているうちに寝ぼけた頭や体が起きてきて動き出し、8時半ぐらいから仕事に取り掛かっていくのですから、ウォーミングアップにはちょうどいいという感じなのです。
草引きが面倒くさいからと言って、草刈り機でだーっとやってしまう人も結構いらっしゃいます。また、畑などは草もそのまま耕運機でだーっと土に混ぜ込んでしまう人も多いと思います。人それぞれですし、それなりの言い分もあると思うのでいいと思いますが、私は草を手で引かないと気がすみません。畑でもまずは草を手で引いてきれいにしてから、管理機(耕運機)で起こします。庭はもちろん絶対に草刈り機は使いません。そんなことをしたら美しい庭は作れないと思います。
手で引いていると草の間から花の芽が出ていたりします。それを抜かないように残してやります。あるいは「この草(花)はかわいいから少し残しておこう」とか「この花の芽はあとで移植してやろう」とか、庭全体の景色を思い描きながらやっていきます。
 例えばこれは千日紅の芽です。昨年のこぼれ種でいっぱい出てきます。あまり多すぎてもいけないので適当に抜いて残してやります。
例えばこれは千日紅の芽です。昨年のこぼれ種でいっぱい出てきます。あまり多すぎてもいけないので適当に抜いて残してやります。
 まあ、私の場合、毎朝7時前から動き出しますが、まずは庭や畑を見に行くことから一日をスタートします。そこで1時間ぐらい花や野菜の世話をしたり、草引きをするのを日課にしています。そうやって毎日少しづつやっていれば広い畑も庭も何とかやっていくことが出来ます。
まあ、私の場合、毎朝7時前から動き出しますが、まずは庭や畑を見に行くことから一日をスタートします。そこで1時間ぐらい花や野菜の世話をしたり、草引きをするのを日課にしています。そうやって毎日少しづつやっていれば広い畑も庭も何とかやっていくことが出来ます。そうやって動いているうちに寝ぼけた頭や体が起きてきて動き出し、8時半ぐらいから仕事に取り掛かっていくのですから、ウォーミングアップにはちょうどいいという感じなのです。
草引きが面倒くさいからと言って、草刈り機でだーっとやってしまう人も結構いらっしゃいます。また、畑などは草もそのまま耕運機でだーっと土に混ぜ込んでしまう人も多いと思います。人それぞれですし、それなりの言い分もあると思うのでいいと思いますが、私は草を手で引かないと気がすみません。畑でもまずは草を手で引いてきれいにしてから、管理機(耕運機)で起こします。庭はもちろん絶対に草刈り機は使いません。そんなことをしたら美しい庭は作れないと思います。
手で引いていると草の間から花の芽が出ていたりします。それを抜かないように残してやります。あるいは「この草(花)はかわいいから少し残しておこう」とか「この花の芽はあとで移植してやろう」とか、庭全体の景色を思い描きながらやっていきます。
 例えばこれは千日紅の芽です。昨年のこぼれ種でいっぱい出てきます。あまり多すぎてもいけないので適当に抜いて残してやります。
例えばこれは千日紅の芽です。昨年のこぼれ種でいっぱい出てきます。あまり多すぎてもいけないので適当に抜いて残してやります。
 こちらはケイトウの芽です。これはまた後で場所を変えて植えてやります。そんなふうにして、手作業で美しい庭(畑も)を作っていこうと毎日思っています。
こちらはケイトウの芽です。これはまた後で場所を変えて植えてやります。そんなふうにして、手作業で美しい庭(畑も)を作っていこうと毎日思っています。私の仕事である家具製作も手仕事なので同じです。「畑と庭と家具づくり」は根っこで(同じ思想で)つながっているのです。
さて、長く載せてこなかった我が「jagar's garden」ですが、5月以来いろんな花ががんばって咲いてくれました。
 まずはバラやクレマチスたち。…とはいえ、今年はバラがいまいちでした。
まずはバラやクレマチスたち。…とはいえ、今年はバラがいまいちでした。
師匠(と私が勝手に思っている人)に聞いたところいろんな問題点が分かりました。バラは奥が深い…まだまだひよっこです。クレマチスは今年は結構きれいに咲いてくれました。
 まずはバラやクレマチスたち。…とはいえ、今年はバラがいまいちでした。
まずはバラやクレマチスたち。…とはいえ、今年はバラがいまいちでした。師匠(と私が勝手に思っている人)に聞いたところいろんな問題点が分かりました。バラは奥が深い…まだまだひよっこです。クレマチスは今年は結構きれいに咲いてくれました。
そのほか、ゴテチャ、源平シモツケ、ペンステモン、カラーなどなど…。
コレオプシス、エキナセア、アンゲロニアなど暑さに強い花たちも咲き始めました。
6月と言えばアジサイです。アナベル、てまりてまりなども咲いています。「万華鏡」もうまく冬越しをして咲いてくれました。でもふと気が付いたのですが、うちはアジサイが少ない!?… これからもう少し増やそうかなと考えています。
ハーブなども成長していよいよ夏かなという感じになってきました。
「ジャガイモの収穫」
2022.06.06
 T様の胡桃(クルミ)2枚接ぎダイニングテーブルの制作が続きます。
T様の胡桃(クルミ)2枚接ぎダイニングテーブルの制作が続きます。表側も鉋掛けをしておきました。一つも欠点が見られない素晴らしい胡桃(クルミ)2枚接ぎの天板です。同じ丸太の板ですから色合いや表情も馴染んでいます。
 ここで一度仮組みをします。あとで接着剤を付けて組み立てるときのことも考えて、ちょうど良い固さになるように調整をしておきます。
ここで一度仮組みをします。あとで接着剤を付けて組み立てるときのことも考えて、ちょうど良い固さになるように調整をしておきます。ゆるすぎたらおしまいですし、逆に固すぎたら接着剤を塗ったときに最悪の場合入らないということもありますので…。
 部材のすべてを鉋で仕上げた後は面取りをし(今回も小さな坊主面)、サンディングをして仕上げます。
部材のすべてを鉋で仕上げた後は面取りをし(今回も小さな坊主面)、サンディングをして仕上げます。
さて…前回の里山だよりに畑のことを書きましたが、一昨日の土曜日にジャガイモの収穫をしてしまいました。例年より1週間ほど早いのですが、今年は試し掘りを何回かしてきたところ、出来が良いので少し早めでも良いと思ったのです。
それに最近猿の襲来が続いていたので、猿に取られることの無いように早く取ってしまおうと思ったのもあります。それに早い方がジャガイモが(肌が)きれいですし…。
 そんなわけで、土曜日は天気が良いということだったので朝から掘り始めました。
そんなわけで、土曜日は天気が良いということだったので朝から掘り始めました。
私一人で8列(150株ほど)掘ってもいいのですが、息子夫婦に「掘る?」と聞いたら、「行く」という返事だったので息子たちと一緒に楽しく掘ることができました。
それに最近猿の襲来が続いていたので、猿に取られることの無いように早く取ってしまおうと思ったのもあります。それに早い方がジャガイモが(肌が)きれいですし…。
 そんなわけで、土曜日は天気が良いということだったので朝から掘り始めました。
そんなわけで、土曜日は天気が良いということだったので朝から掘り始めました。私一人で8列(150株ほど)掘ってもいいのですが、息子夫婦に「掘る?」と聞いたら、「行く」という返事だったので息子たちと一緒に楽しく掘ることができました。
 あと1週間置いておいたら大変なことになっていたでしょう。いいタイミングで収穫できたと思っています。
あと1週間置いておいたら大変なことになっていたでしょう。いいタイミングで収穫できたと思っています。味は?…言うまでもなくものすごく甘くてほくほくしていておいしいです。前にも書きましたが、我が菜園でとれる野菜の中でジャガイモが一番の自慢です。どこのジャガイモにも負けないおいしさだと自負しています。
そんなわけで我が家の一大イベント「ジャガイモ掘り」が、無事楽しく終わりました。めでたし、めでたし…。
キュウリも今のところ順調です。いつも決まって病気になってしまう(ベと病)ので、今年は対策の一つとしてお酢にニンニクと鷹の爪を漬けておいて、それを500倍に希釈した溶液を時々葉っぱにかけてやっています。

 そのせいかどうかわかりませんが今のところ虫に食われることも少なく、葉がきれいに成長しています。
そのせいかどうかわかりませんが今のところ虫に食われることも少なく、葉がきれいに成長しています。

 そのせいかどうかわかりませんが今のところ虫に食われることも少なく、葉がきれいに成長しています。
そのせいかどうかわかりませんが今のところ虫に食われることも少なく、葉がきれいに成長しています。
 ところでもう一つ…庭のジューンベリーの実がいっぱい生ったので、取ってジャムにしました。本当にたくさんついていてボウルに3杯たっぷりとりましたが、それでもまだたくさん残っています。残りは鳥さんにあげようと思います。
ところでもう一つ…庭のジューンベリーの実がいっぱい生ったので、取ってジャムにしました。本当にたくさんついていてボウルに3杯たっぷりとりましたが、それでもまだたくさん残っています。残りは鳥さんにあげようと思います。
「畑の季節」
2022.05.31
「胡桃(クルミ)2枚接ぎダイニングセット」の制作が進んでいます。ご依頼者のお客様が「制作の様子を見てみたい」と言われ、先日の土曜日に工房へおいでになりました。2枚接ぎの接ぎ合わせが済んだところだったので、裏面の鉋掛けをする様子をご覧いただきました。
その途中でお客様ご自身も「やってみたい」と言われたので、少し鉋掛けを体験していただくことができました。(残念ながら写真は撮ってありませんが…。) 「また来てもいいですか!?」と言われたので「またどうぞ」とお返事をしておきました。今度はどんな場面を見ていただくことになるのでしょうか?
 さてその後、いよいよこのテーブルの肝となります「寄せ蟻」(反り止め)の加工に入りました。
さてその後、いよいよこのテーブルの肝となります「寄せ蟻」(反り止め)の加工に入りました。
まずはルーターという工具に「ストレートビット」を付けて1回目の荒掘りをします。
その途中でお客様ご自身も「やってみたい」と言われたので、少し鉋掛けを体験していただくことができました。(残念ながら写真は撮ってありませんが…。) 「また来てもいいですか!?」と言われたので「またどうぞ」とお返事をしておきました。今度はどんな場面を見ていただくことになるのでしょうか?
 さてその後、いよいよこのテーブルの肝となります「寄せ蟻」(反り止め)の加工に入りました。
さてその後、いよいよこのテーブルの肝となります「寄せ蟻」(反り止め)の加工に入りました。まずはルーターという工具に「ストレートビット」を付けて1回目の荒掘りをします。
 まずは、こちらもトリマーという工具で余分な部分を欠き取っていきます。全部取ってしまわずに、真ん中部分がある程度の幅で残ります。
まずは、こちらもトリマーという工具で余分な部分を欠き取っていきます。全部取ってしまわずに、真ん中部分がある程度の幅で残ります。これを「支端(しば)残し」と言います。全部取ってしまうより強度が出るので私はいつもこのやり方をします。
何度も何度も繰り返して絶妙な嵌めあいにします。(ゆるくてはもちろんだめですし、結構きつくてちょうどいいという感じになるように少しづつ加工を進めていきます。) こうして寄せ蟻は無事加工を終えました。
 さて…話は変わりますが、畑の方も今が盛期に入っています。今年もたくさんの夏野菜を植えてあります。まずは第1農園から。キャベツ、すくなかぼちゃ、ズッキーニ、ナス、トマト、ミニトマト、サツマイモ、ゴーヤなどを植えました。
さて…話は変わりますが、畑の方も今が盛期に入っています。今年もたくさんの夏野菜を植えてあります。まずは第1農園から。キャベツ、すくなかぼちゃ、ズッキーニ、ナス、トマト、ミニトマト、サツマイモ、ゴーヤなどを植えました。今までずっと作ってきたスイカとメロンは、今年はやめました。理由は猿に取られることと、そんなに作っても結局夫婦2人ではあまり食べないということです。
 ナスは黒陽、庄屋大長、あげてトルコの3種類です。昨年からこんなふうに仕立てることにしましたが、これ…なかなかいいです。
ナスは黒陽、庄屋大長、あげてトルコの3種類です。昨年からこんなふうに仕立てることにしましたが、これ…なかなかいいです。ナスは肥料食い、水食いと言われますので、追肥と潅水をこまめにします。普通の肥料のほかに苦土石灰も時々追肥としてあげます。ここがポイントです。マグネシウム補充です。
 トマトの棚は、昨年から少し高くして大きくしました。いつも私の身長をはるかに超えるぐらい伸びるので、天井のビニールにくっついてしまうからです。
トマトの棚は、昨年から少し高くして大きくしました。いつも私の身長をはるかに超えるぐらい伸びるので、天井のビニールにくっついてしまうからです。それともう一つは猿対策です。全体を網で囲んでしまうので、その中で作業がしやすいように幅広く作りました。そして、支柱をやめてひもに誘因することにしました。こうすると後で下に少しおろすことが出来るからです。
「胡桃(クルミ)2枚接ぎダイニングセット」
2022.05.26
そして引き続き、「胡桃(クルミ)2枚接ぎダイニングテーブルセット」(テーブルとベンチ2脚)の制作に取り掛かりました。今回のお客様は作り方や手仕事に強い購入動機をお持ちのお客様で、我が工房の制作・作品スタイルに共感していただきご注文となりました。
材料となる胡桃(クルミ)はちょうど工房に在庫で置いてあった大径(直径50cm強)の胡桃丸太で、ほぼすべて共木での制作となります。とても木味も良い良材です。
近年(ここ10年ぐらい)胡桃(クルミ)の大きな丸太というのはほとんで出ることもなくなって(あってもせいぜい直径30cmぐらいなものです)、入手が困難になっています。そういう意味で、貴重な丸太ということになります。
 まずは土場に広げて木取り(きどり)からです。これが大変重要な作業です。どの部分にどの板を使おうかと、じっくり悩みながら決めていきます。
まずは土場に広げて木取り(きどり)からです。これが大変重要な作業です。どの部分にどの板を使おうかと、じっくり悩みながら決めていきます。
たっぷり半日かかりました。
材料となる胡桃(クルミ)はちょうど工房に在庫で置いてあった大径(直径50cm強)の胡桃丸太で、ほぼすべて共木での制作となります。とても木味も良い良材です。
近年(ここ10年ぐらい)胡桃(クルミ)の大きな丸太というのはほとんで出ることもなくなって(あってもせいぜい直径30cmぐらいなものです)、入手が困難になっています。そういう意味で、貴重な丸太ということになります。
 まずは土場に広げて木取り(きどり)からです。これが大変重要な作業です。どの部分にどの板を使おうかと、じっくり悩みながら決めていきます。
まずは土場に広げて木取り(きどり)からです。これが大変重要な作業です。どの部分にどの板を使おうかと、じっくり悩みながら決めていきます。たっぷり半日かかりました。
 接ぎ合わせをするため、木端(こば)面を手押し鉋で削ってまっすぐ平らにします。
接ぎ合わせをするため、木端(こば)面を手押し鉋で削ってまっすぐ平らにします。正確に言うと完全な平らではなく、中凹になるように(機械を微調整して)削るのですが、大きな板だけに非常に難しいです。しかも重いので、これは体力仕事です。
 いつものように「隠し雇い実接ぎ」を加工していきます。ルーターで溝を切っていきます。(我々の業界では「小穴を突く」と言います。)
いつものように「隠し雇い実接ぎ」を加工していきます。ルーターで溝を切っていきます。(我々の業界では「小穴を突く」と言います。)
「ゴールデンウィークそして庭の季節」
2022.05.12
そして、欅(ケやキ)のスツール2脚も制作中です。木工旋盤で脚を挽いているところです。
ところで…前回の里山だよりから3週間も経ってしまいました。その間にゴールデンウィークがありましたが、私のゴールデンウィークは家のことであっという間に終わっていった感じです。第一に家族の一大行事。その準備も含めて数日落ち着かない日々を過ごしました。私自身にも一つ大きな仕事があり、緊張しましたがどうにか終わりました。

 孫もよく遊びに来てくれました。
孫もよく遊びに来てくれました。

 孫もよく遊びに来てくれました。
孫もよく遊びに来てくれました。
本当にこの時期は、一年で一番庭がにぎやかになる時期です。「庭を見たい」と言って、お客様が十数名ほど団体でいらっしゃった日もありました。この後もいよいよバラが開花し始め、ますます華やいでくれると思います。当分楽しみは尽きません。
「ジャガーズガーデン庭めぐり」
2022.04.21
今日の庭の様子の動画を撮りましたのでご覧ください。
「レーザー加工機」
2022.04.18
 ところで…実はもう1ヵ月以上前に工房に迎え入れていたのですが、紹介していなかったものがあります。それは…ジャーン!「レーザー加工機」です。シブいでしょう?カッコいいでしょう?
ところで…実はもう1ヵ月以上前に工房に迎え入れていたのですが、紹介していなかったものがあります。それは…ジャーン!「レーザー加工機」です。シブいでしょう?カッコいいでしょう?以前の里山だよりで書いた「秘密の小部屋」はこの機械を置いて使う部屋だったのです。ホコリ厳禁、室温管理が必要ということで作る必要があったのです。
なぜこの機械を導入することになったかというと…詳しくは言えませんが、簡単に言うと「ふるさと納税」がきっかけです。昨年末に急にある話が入り、急遽レーザー加工機を思いついて、それから色々調べ始めて何とか今年度末の3月半ばに導入しました。これを使って「ふるさと納税」の返礼品はもちろん、他にもいろいろ制作していく予定です。
とはいえ、ハイテク機械ですから簡単には使いこなせませんでした。パソコンにつないで使うものです。その設定やらなんやら、当初は全くちんぷんかんぷんで…一応説明書はついていますが、それだけでは全然使えません。(一応国産の機械なので、説明書が日本語である程度は詳しく書いてあります。一般的によく使われている外国産のレーザー加工機だと説明書自体が判読不可ではないかと思います。)
分からないことをメーカーに聞こうと思っても電話対応は無しです。すべてメールでのやり取り…何十回とメールのやり取りをしたと思いますが、返ってくる内容もまた専門的な用語のオンパレードでよくわからず、また聞き返す…みたいな…。
 illustrater(イラストレーター)などというソフトをちゃんと使ったのも初めてです。(持っていたのですが、宝の持ち腐れでした。) その使い方も日頃お世話になっているホームページの管理人の方にいろいろ教えてもらいながら少しづつ覚えました。
illustrater(イラストレーター)などというソフトをちゃんと使ったのも初めてです。(持っていたのですが、宝の持ち腐れでした。) その使い方も日頃お世話になっているホームページの管理人の方にいろいろ教えてもらいながら少しづつ覚えました。妻曰く「よくそういう新しいことに挑戦できるね(その年になって)」だそうで…。でも、私としてはいつも前向きに生きていたいと思っているだけで…。まぁ、難しくてもちょうどボケ防止になっていいかも…?
そんな感じで、四苦八苦しながら何とか使えるようになりました。カットをしたり、イラストや文字、絵や写真を彫刻したり…名入れなども簡単に出来ます。
 また、すでに「ふるさと納税」には、このレーザー加工機を使って「名入れサービス」を付加した新商品が掲載してあります。よかったら見てください。
また、すでに「ふるさと納税」には、このレーザー加工機を使って「名入れサービス」を付加した新商品が掲載してあります。よかったら見てください。今回この「レーザー加工機」を導入することにしたのは、そうすることによって、これから先、今までの仕事プラス(ずうっと思っていた)もう少し幅広い展開をしていこうと考えたからです。それはまた今後紹介していきます。
「いろいろ忙しい」
2022.04.01
 今年は寒かったせいか、いつもよりは少し遅いですがジャガイモの芽も出始めました。そろそろ畑を片付けて(冬野菜を抜いて、草引きもして)夏野菜を植えるための畑の準備をしなければいけませんが、なかなかやっている暇がないので焦っています。
今年は寒かったせいか、いつもよりは少し遅いですがジャガイモの芽も出始めました。そろそろ畑を片付けて(冬野菜を抜いて、草引きもして)夏野菜を植えるための畑の準備をしなければいけませんが、なかなかやっている暇がないので焦っています。
さて、前回の里山だよりに書きました「胡桃(クルミ)の円卓」は東京へと旅立ちました。お客様が「搬入が難しいかもしれないので持ってきて組み立てて欲しい」と言われましたので直接納品に伺いましたが、周りはマンションや各国大使館が建ち並ぶ閑静な住宅街でした。
「すごい!思った以上です」と喜んでいただけました。現場で「寄せ蟻」による組み立ての様子も見ていただき、感動してみえました。何はともあれ無事納品出来てよかったです。
「すごい!思った以上です」と喜んでいただけました。現場で「寄せ蟻」による組み立ての様子も見ていただき、感動してみえました。何はともあれ無事納品出来てよかったです。

 そしてもう一つ。3月に入ってひそかに進行中の「ふるさと納税返礼品」の新商品が完成し、サイトに載せました。「さくらのコースター」2人用と5人用の2種類です。
そしてもう一つ。3月に入ってひそかに進行中の「ふるさと納税返礼品」の新商品が完成し、サイトに載せました。「さくらのコースター」2人用と5人用の2種類です。自分たちで普段使いにはもちろんのこと、結婚式や記念日などのプレゼント用としてもいいかなと思います。(おしゃれな箱に入っています。)
屋根部分を削り上げ、ようやくここまで来ました。
ここからまだもうひと頑張りです。
「円卓」
2022.03.08
 そのあと木端(こば)面を鉋できれいに仕上げます。ここで使う鉋は「反り台鉋」というものです。
そのあと木端(こば)面を鉋できれいに仕上げます。ここで使う鉋は「反り台鉋」というものです。

 脚の部材の加工も進めます。脚下の飾りもちょっとした見せ所。「際がんな」という鉋や彫刻刀を使って飾りを彫りだしていきます。
脚の部材の加工も進めます。脚下の飾りもちょっとした見せ所。「際がんな」という鉋や彫刻刀を使って飾りを彫りだしていきます。
 天板の角の面も取っておきます。ここで使用するのは「面取り鉋」という鉋です。
天板の角の面も取っておきます。ここで使用するのは「面取り鉋」という鉋です。

 蝶ネジを緩めたり締めたりして、自由に面の大きさが変えられます。もちろん普通の平鉋でもできますが、こちらの方が同じ大きさの面を、しかも正確に45度(留)の面をきれいに作れます。
蝶ネジを緩めたり締めたりして、自由に面の大きさが変えられます。もちろん普通の平鉋でもできますが、こちらの方が同じ大きさの面を、しかも正確に45度(留)の面をきれいに作れます。またトリマーという工具でもできますが、こちらの方がうんときれいに出来ます。
かくして仕上げまで完成したので、塗装に入りました。もう少しで完成です。
そして、いよいよこれから「欅(ケヤキ)の厨子」の制作に入ります。完成が楽しみです。
「ひこつい」
2022.03.01
 そして、引き続き「胡桃(クルミ)の円卓 直径110cm」の制作に入りました。3月に入りましたが、今月中に完成させなければならない案件がたくさんあってお尻に火が付いています。
そして、引き続き「胡桃(クルミ)の円卓 直径110cm」の制作に入りました。3月に入りましたが、今月中に完成させなければならない案件がたくさんあってお尻に火が付いています。
そして畑ではジャガイモの植え付けをしました。今年は寒かったのでもう少し後の方がいいかなとも思っていましたが、すでに種芋の芽が動き始めていましたので、やることにしました。種芋を半分に切って(芽をよく見ながら切ります)、藁灰を切り口につけておきます。こうして1日置きます。
今年も畝を8本、約150個ぐらいの種芋を植え付けました。
ところで…以前の里山だより(2010年3月16日と2013年3月6日)にも書きましたが、我が家のジャガイモの植え付け方(畝の作り方)はちょっと違います。うちのようなやり方をする人はあまり見たことがありません。
一般的には溝を浅く掘ってそこに種芋を置き、両側から土を寄せていくという感じでしょう。園芸の本やネットなどを見ると大体そんな感じです。
 ですが、私のやり方は昔(30数年も前)祖母に教えてもらったやり方です。このやり方はやってみるととてもよく考えられたやり方だと感じるので、ずっとそうやっています。
ですが、私のやり方は昔(30数年も前)祖母に教えてもらったやり方です。このやり方はやってみるととてもよく考えられたやり方だと感じるので、ずっとそうやっています。
ところで…以前の里山だより(2010年3月16日と2013年3月6日)にも書きましたが、我が家のジャガイモの植え付け方(畝の作り方)はちょっと違います。うちのようなやり方をする人はあまり見たことがありません。
一般的には溝を浅く掘ってそこに種芋を置き、両側から土を寄せていくという感じでしょう。園芸の本やネットなどを見ると大体そんな感じです。
 ですが、私のやり方は昔(30数年も前)祖母に教えてもらったやり方です。このやり方はやってみるととてもよく考えられたやり方だと感じるので、ずっとそうやっています。
ですが、私のやり方は昔(30数年も前)祖母に教えてもらったやり方です。このやり方はやってみるととてもよく考えられたやり方だと感じるので、ずっとそうやっています。
 祖母と言えばもう一つ。本日ネギの苗も伏せました。延々と単純作業をしていると、しながらいろんなことを考えます。今日は祖母のことを思い出していました。
祖母と言えばもう一つ。本日ネギの苗も伏せました。延々と単純作業をしていると、しながらいろんなことを考えます。今日は祖母のことを思い出していました。今回も種をまいて育てた苗が3種類。それを植えるのですが、これも昔祖母に教えてもらったやり方です。祖母が言うには「2本づつまとめて植える」のだそうです。
 なぜかって?知りません。祖母がそう言ったからそうやっているのです。…というと「わけも分からずやっているなんて」と馬鹿にされそうですから、一応自分なりにもその理由も考えてみたことは言っておきます。
なぜかって?知りません。祖母がそう言ったからそうやっているのです。…というと「わけも分からずやっているなんて」と馬鹿にされそうですから、一応自分なりにもその理由も考えてみたことは言っておきます。ですが、考えてみると昔の人は「何故か」なんていうことは言わないことが多かったと思います。木工業界、あるいは職人の世界もそうです。親方は懇切丁寧に教えてくれません。「盗め」「背中を見て覚える」などと…どうしてそうやってやるのかなんていう理由は言いません。聞く方が野暮というものです。
私の住む田舎では、昔から「ひこつい」という言葉があります。決していい意味の言葉ではありません。「ひこつい奴やな」「お前はひこついことを言うからあかん!」などと…簡単に言うと「理屈っぽい」とか「(いいニュアンスではない)頭がいい」というような意味でしょうか…そういうことを言う人間は、私の住む田舎ではよく思われません。
実をいうと(独断と偏見かもしれませんが)我が木工業界、特に「木工家」「家具工房」の世界の人たちはそういう種類の人間が多いと思います。一つには高学歴の人が多いということ。東大卒、京大卒、東京の有名大学卒業などの人や、超有名企業に勤めていた方、マスコミ関係、テレビ業界に勤めていた方などなど…結構そうそうたる経歴の方が多くみえます。
かつて友人の陶芸家(超有名な陶芸家です)が言っていたのですが、「木工の人は…」…何をか言わんやです。陶芸家の人たちはまた全然違います。この方も中学校を卒業して地元の陶業研究所(木工で言うと技能訓練校のようなもの)で研修した後、現場で修業を積まれただけです。決して高学歴ではありません。
私自身は(自分に対する戒めもあって)そういう(ひこつい)感じになることは言わないように気を付けようと思っていましたので、この世界に入ってそういう人を見るとあまりいい感じはしませんでした。
話がどんどん脱線してしまいましたが、理由はわからずとも良いものは何かしら「わけ(理由)」があるから生き続けるのです。そういうものは残していきたいと思っています。
「お雛様」
2022.02.16
以前の里山だよりにもちょっと書きましたが、今年は初孫の初節句です。お雛様を買って娘宅に届けました。
 そんな折、近所に住むお客様(もうすぐ厨子を制作することになっています)が、何やら風呂敷包みを持って御出でになりました。
そんな折、近所に住むお客様(もうすぐ厨子を制作することになっています)が、何やら風呂敷包みを持って御出でになりました。
「うちではもう飾ることはないから佐藤さん飾ってみて」と言って置いて行かれました。自分の娘さんに使い、さらにお孫さんに使い、今ではもう使われなくなっているとか…。年季の入った感じの箱に入っていました。
 そんな折、近所に住むお客様(もうすぐ厨子を制作することになっています)が、何やら風呂敷包みを持って御出でになりました。
そんな折、近所に住むお客様(もうすぐ厨子を制作することになっています)が、何やら風呂敷包みを持って御出でになりました。「うちではもう飾ることはないから佐藤さん飾ってみて」と言って置いて行かれました。自分の娘さんに使い、さらにお孫さんに使い、今ではもう使われなくなっているとか…。年季の入った感じの箱に入っていました。
ばらばらにすると後になって元通りに納めることが難しそうなので、まずしっかり写真に撮ってから飾り付けをしてみました。
 この写真を娘にLINEで送ったところ、「もう少し小さくてもいいから、〇〇ちゃん(孫)にも作って」という返事が…他にもあれこれ作ってほしいとねだられ、「〇〇ちゃんの誕生日までにケーキも作って」などと…私なら何でも作れると思っているらしいです。
この写真を娘にLINEで送ったところ、「もう少し小さくてもいいから、〇〇ちゃん(孫)にも作って」という返事が…他にもあれこれ作ってほしいとねだられ、「〇〇ちゃんの誕生日までにケーキも作って」などと…私なら何でも作れると思っているらしいです。孫には弱い私…作ろうかな?……いや、作ろう!作るぞ!!急にやる気になってしまいました。
これまでも家具は巨大なものから小さいものまでいろいろ作ってきたのはもちろん、家(工房)、車庫、庭の東屋、小さなとんがり屋根の家、そして庭の様々な造作物、カヌー、ピザ窯などなど…いろんなものを作ってきた私。またまた「なんでも作りたい病」が出てきてしまいました。今度は木のおもちゃ作りになりそうです。
「欅の円座卓」
2022.02.10
我がジャガーズガーデンではたくさんの植物が相変わらず凍みた土の中で冬ごもり中です。


 しかし、中にはちらほらと芽を出し始めている植物もあります。
しかし、中にはちらほらと芽を出し始めている植物もあります。
アリウムギガンチウムの芽が出ていたり、アジサイの芽が出ていたり…。


 しかし、中にはちらほらと芽を出し始めている植物もあります。
しかし、中にはちらほらと芽を出し始めている植物もあります。アリウムギガンチウムの芽が出ていたり、アジサイの芽が出ていたり…。
デルフィニウム、ジギタリスも元気。ラナンキュラスはもうだいぶん前から芽を出しています。
 さて工房の方ですが、前回書きました工房内の小部屋も完成しました。
さて工房の方ですが、前回書きました工房内の小部屋も完成しました。

 シベリア産ベニマツで作ったドアもばっちり納まっていい感じです。ドアの羽目板もベニマツの幅30cmぐらいの柾目の無垢一枚板です。なかなか無い貴重な板を使っています。
シベリア産ベニマツで作ったドアもばっちり納まっていい感じです。ドアの羽目板もベニマツの幅30cmぐらいの柾目の無垢一枚板です。なかなか無い貴重な板を使っています。またこの小部屋の入口に看板をぶら下げようと思っています。

 地松の一枚板のテーブルもいい感じです。この前に座って今里山だよりを書いていますが、贅沢でいい気分です。
地松の一枚板のテーブルもいい感じです。この前に座って今里山だよりを書いていますが、贅沢でいい気分です。あっ、椅子はとりあえず娘が子供のころ使っていた回転椅子を拝借して置いています。いずれちゃんとしたのを置こうかと思っています。
 天板は、この後木端(こば)面を蛇腹面に仕上げていきます。
天板は、この後木端(こば)面を蛇腹面に仕上げていきます。
 そして同時に、在庫切れで送ることができなかった残り分のカッティングボード(ふるさと納税)も30枚ほど追加制作しています。
そして同時に、在庫切れで送ることができなかった残り分のカッティングボード(ふるさと納税)も30枚ほど追加制作しています。カッティングボードはまた40枚ほど注文が入っているので、それはまた3月になったら作るつもりでいます。そして、このあと注文分の円卓や欅の厨子も制作しつつふるさと納税の新製品も作ってアップしていきます。
そうこうしていたら、ネットショップ(iichi)の方から「胡桃のお盆はもう無いですか?」「山桜の大皿はもうありませんか?」「山桜のどら鉢の在庫はもう無いですか?」…などたくさんリクエストが来ています。(今のところほとんどsold outになってしまっていますので。)
「春になったら作りますのでそれまでしばらくお待ちください」とお返事をしています。それについても制作していかなくてはなりません。忙しいことはありがたいことです。
「春になったら作りますのでそれまでしばらくお待ちください」とお返事をしています。それについても制作していかなくてはなりません。忙しいことはありがたいことです。
「作業場の改造」
2022.02.04
続いて「欅(ケヤキ)無垢一枚板の円座卓」の制作へとかかりました。まずは天板をフラットに削って円形にカット…と思ったところで、いったんストップ。機械屋さんに修理を頼んでいたバンドソーの部品が来たので、ついでにバンドソーを大移動して、あることを実行することにしました。
 まずはバンドソーを置く場所の確保です。材木を大量に立てかけてあったところを整理して、いらない木(使わないであろうと思われる端材みたいなもの)を大量に処分しました。処分というのは捨てることではなく、薪ストーブの薪にするために切って袋に詰めてしまっておきました。
まずはバンドソーを置く場所の確保です。材木を大量に立てかけてあったところを整理して、いらない木(使わないであろうと思われる端材みたいなもの)を大量に処分しました。処分というのは捨てることではなく、薪ストーブの薪にするために切って袋に詰めてしまっておきました。
そして、スペースができたところへバンドソーを移動しました。
 まずはバンドソーを置く場所の確保です。材木を大量に立てかけてあったところを整理して、いらない木(使わないであろうと思われる端材みたいなもの)を大量に処分しました。処分というのは捨てることではなく、薪ストーブの薪にするために切って袋に詰めてしまっておきました。
まずはバンドソーを置く場所の確保です。材木を大量に立てかけてあったところを整理して、いらない木(使わないであろうと思われる端材みたいなもの)を大量に処分しました。処分というのは捨てることではなく、薪ストーブの薪にするために切って袋に詰めてしまっておきました。そして、スペースができたところへバンドソーを移動しました。
 続いて、バンドソーが置いてあったところを仕切って一坪ほどの部屋に改造します。そのためにまたまたいろんなものを片付けにかかりました。そんなわけで工房の中はぐちゃぐちゃになってしまいました。
続いて、バンドソーが置いてあったところを仕切って一坪ほどの部屋に改造します。そのためにまたまたいろんなものを片付けにかかりました。そんなわけで工房の中はぐちゃぐちゃになってしまいました。でも、おかげで長い間使っていなかったものを思い切って捨てることができました。私はどちらかというとなかなか捨てられない性格で、いろんなものを「まだ使えるだろう」と思って取っておくことが多いです。例えば使い古しのサンディングペーパー。まだ使える部分があるからと思って取っておくのです。
また、納品の際に包んでいったプチプチ。「一回使っただけだからもったいない、また再利用しよう」と思って取っておくのです。そんなようなものが工房の中にいっぱいたまっていました。その他にも、もう使わないだろうと思われる治具など。とにかく、この際思い切って捨てることにしました。

 そして、少しすっきりしてから作業を開始。柱を立て、桟を打ち付けて壁を貼り、天井を貼って形になりました。そして、電気屋さんに配線をしてもらって部屋は完成しました。(写真を撮り忘れるほど一心不乱に作業を進めていました。)
そして、少しすっきりしてから作業を開始。柱を立て、桟を打ち付けて壁を貼り、天井を貼って形になりました。そして、電気屋さんに配線をしてもらって部屋は完成しました。(写真を撮り忘れるほど一心不乱に作業を進めていました。)と、簡単に書きましたが、なかなか大変な作業でした。ここまでの所要時間は2日!結構早業でしょ?
天板をどうしようと考えていたところ、「あっ、そういえばあれがあったわ!」と…実は以前ある方に、京都の有名なお寺を改築したときに捨てられそうになっていた建具や調度品の部材をいただいたのです。「佐藤さん、捨てるのももったいないから使えるものなら使ってやって」と。
その中に真っ黒になっている古びた大きな板(幅90cmぐらい、長さ190cmぐらい)がありました。「多分接ぎ合わせ板だろ?」と思っていましたが、よく見たらなんと大きな松(地松)の一枚板でした。30mmほどの薄い板でしたので、裏側には反り止めが入っていました。
 その板を表だけざっと削って仕上げました。ヤニが入っていてすごい模様ですが、迫力のある表情です。ところどころ小さな割れもありますが、そんなことは気にしません。とにかく、何百年前のものか知りませんが、すごい歴史を感じる松の一枚板です。
その板を表だけざっと削って仕上げました。ヤニが入っていてすごい模様ですが、迫力のある表情です。ところどころ小さな割れもありますが、そんなことは気にしません。とにかく、何百年前のものか知りませんが、すごい歴史を感じる松の一枚板です。
もうこれ以上狂うことはないだろうと、そのまま仕上げて脚部に取り付けました。無塗装で使います。作業机にするにはもったいないぐらいのテーブルが完成しました。ちなみにテーブルを作るのにかかった時間も2日。早業です。
そして、最後の作業は入口のドア制作です。どうせ工房内の扉だからなんでもいいからありあわせのドアか、ホームセンターのアウトレットの安いのを買ってくるか…と思っていましたが、結局ちょうどのものが無くて、自分で作ることにしました。
その中に真っ黒になっている古びた大きな板(幅90cmぐらい、長さ190cmぐらい)がありました。「多分接ぎ合わせ板だろ?」と思っていましたが、よく見たらなんと大きな松(地松)の一枚板でした。30mmほどの薄い板でしたので、裏側には反り止めが入っていました。
 その板を表だけざっと削って仕上げました。ヤニが入っていてすごい模様ですが、迫力のある表情です。ところどころ小さな割れもありますが、そんなことは気にしません。とにかく、何百年前のものか知りませんが、すごい歴史を感じる松の一枚板です。
その板を表だけざっと削って仕上げました。ヤニが入っていてすごい模様ですが、迫力のある表情です。ところどころ小さな割れもありますが、そんなことは気にしません。とにかく、何百年前のものか知りませんが、すごい歴史を感じる松の一枚板です。もうこれ以上狂うことはないだろうと、そのまま仕上げて脚部に取り付けました。無塗装で使います。作業机にするにはもったいないぐらいのテーブルが完成しました。ちなみにテーブルを作るのにかかった時間も2日。早業です。
そして、最後の作業は入口のドア制作です。どうせ工房内の扉だからなんでもいいからありあわせのドアか、ホームセンターのアウトレットの安いのを買ってくるか…と思っていましたが、結局ちょうどのものが無くて、自分で作ることにしました。

 材料は大好きな「シベリア産ベニマツ」。今では手に入らない超貴重な木材です。そういう木材であるベニマツに敬意を表して、しっかり作ることにしました。(工房の中のドアなのに?)
材料は大好きな「シベリア産ベニマツ」。今では手に入らない超貴重な木材です。そういう木材であるベニマツに敬意を表して、しっかり作ることにしました。(工房の中のドアなのに?)仕口も一応「馬乗りほぞ」という仕口を使います。ここも手仕事でやります。
ところで…「何の部屋を作ってるんだ?」とお思いでしょう。遊び場ではないですよ。まだ内緒ですが、もうすぐある機械がやってきます。それをこの部屋に入れるのです。
ホコリ厳禁、ある程度の室温管理も必要…とのことなので、こうして部屋を作っているのです。その機械がここに入ったらまた紹介するつもりです。
ホコリ厳禁、ある程度の室温管理も必要…とのことなので、こうして部屋を作っているのです。その機械がここに入ったらまた紹介するつもりです。
「年末年始そして今」
2022.01.21
 もう1月の下旬となります。今さらですが昨年の里山だよりでは書けなかった年末年始の我が家の出来事をちょっと…。
もう1月の下旬となります。今さらですが昨年の里山だよりでは書けなかった年末年始の我が家の出来事をちょっと…。まずはクリスマスのこと。今年もまたサンタクロースから突然電話が。「また(今年も)鳥の丸(1匹)を持っていくで!」と…そして、やはり届いた若鳥の丸1匹。今年もダッチオーブンで丸焼きを作ることになりました。
 大晦日は息子夫婦も帰って来てくれたので、夫婦二人の寂しい年越しではなく、にぎやかな年越しとなりました。焼きイワシと年越しの煮物は定番です。
大晦日は息子夫婦も帰って来てくれたので、夫婦二人の寂しい年越しではなく、にぎやかな年越しとなりました。焼きイワシと年越しの煮物は定番です。お嫁さんが「真夜中の初もうでに行ってみたい!」と言ってくれたので、久しぶりに家族全員で歩いて近くの神社に初もうでに行けました。
 年が明けて、名古屋の熱田神宮と岐阜のお千代保稲荷(おちょぼさん)に初もうでに行きました。
年が明けて、名古屋の熱田神宮と岐阜のお千代保稲荷(おちょぼさん)に初もうでに行きました。熱田神宮で引いたおみくじはナント「大吉」!すべてうまくいくという内容だったので大喜び。でも内容があまりにも良すぎてちょっと怖くなったので、いつも以上に今年は身を引き締めて過ごそうと思ったのでした。
 そんな感じで駆け足で年末年始の我が家を振り返りましたが、仕事の方はやはり年末年始は「ふるさと納税」に追われます。
そんな感じで駆け足で年末年始の我が家を振り返りましたが、仕事の方はやはり年末年始は「ふるさと納税」に追われます。今年も1月7日時点で(工芸品・装飾品の部5000点以上のうち)全国10位(昨年は6位)、岐阜県1位となっており、けっこうたくさんの注文をいただきました。

 そして、ちゃぶ台の制作へと移りました。相変わらず手仕事で「天秤指し(蟻組み)」の組み手加工をしております。
そして、ちゃぶ台の制作へと移りました。相変わらず手仕事で「天秤指し(蟻組み)」の組み手加工をしております。